薬の代謝機能は当然ながら、年齢によっても異なります。
抗がん剤を使用する場合でも、同様の注意点があります。
基本的な薬物代謝を知ることは、患者さんの病態把握にも役立ちますし、頓服薬を使用したい場合など、どのような代謝過程で、どれくらい影響する可能性があるかという判断材料にもなります。
例えば、腎機能障害が強く出る抗がん剤治療を行う高齢者の方がいるとします。
当然薬によって腎機能は悪くなるだろうと予測できるのですが、加えて加齢による腎機能低下があって、治療前から機能低下が軽度みられていたとしたら、どの程度の薬剤量が許容できるか、という視点を持つことができます。
また、高齢者は症状を自覚しにくい傾向があります。
よって、予防的に対策を早めにしておく必要がありますし、看護師の普段の観察・問診に工夫が必要になってくるのです。
テストではないので一つ一つを覚える必要はないのですが、状況判断のために知っておくことが必要なのです。
薬物投与において注意が必要な患者
高齢者
高齢者では、各種の生理機能が低下します。
加齢に伴う生理機能の低下は、薬剤の体内での動きと作用に影響を与えます。
①胃酸分泌の低下:薬剤の吸収に影響
②体内の総水分量の減少、体脂肪率の増加:脂溶性薬剤の体内分布の増加、排泄低下
③肝臓重量と肝血流量の減少:薬剤を分解する代謝能力の減少
④腎臓ネフロン数と腎血流量の減少:糸球体濾過速度と尿細管分泌能の低下、腎排泄速度の減少
吸収
高齢者では、加齢によって①胃酸分泌量の低下、②消化管運動機能の低下、③消化管血流量の低下・消化管粘膜表面積の減少が起こります。
①胃酸分泌量の低下
胃酸には殺菌作用と消化促進作用があり、胃酸分泌量の低下による胃内pH上昇によって、吸収率が変化する薬物があります。
しかし、高齢者では胃酸やペプシン分泌の低下はわずかであり、臨床的には影響は少ないと考えられています。
②消化管運動機能の低下
薬物の主な吸収部位である小腸へ胃からの輸送時間が延長し、最高血中濃度に達する時間(Tmax)が遅延することがあります。
③消化管血流量の低下
消化観血流量の低下や、薬物が吸収される部位である消化管粘膜表面積の減少が起こることがあります。
いずれも臨床的には、影響は少ないと考えられています。
分布
加齢に伴い、筋肉量が減少し、体脂肪率が増加するとともに、体内総水分量が減少します。
よって脂溶性薬物の分布は増加し、体内からの消失が遅くなります。
一方、エタノールのような水溶性薬物の分布は減少し、最高血中濃度が高くなる可能性があります。
ただし、疾患やタンパク結合率によっても薬物の分布は変化します。
血液中では、薬物は主にアルブミンやα1酸性糖タンパクといった血漿タンパクと結合している状態(結合型)と、結合していない状態(遊離型)とで存在しています。
この遊離型の薬物だけが細胞膜を通過して組織中に移行し、作用を発現します。
高齢者では、血漿中アルブミン濃度が低下していることが多いため、アルブミンと結合する薬物では、遊離型の割合が高くなり、薬理作用が強く現れることがあります。
一方、α1酸性糖タンパクは、加齢に伴って増加することが多いです。
必要な場合には、遊離型濃度を測定し、臨床に役立てることが必要となるでしょう。
薬物が体液に均一に分布していると考えた場合の溶解液容積のことです。
分布容積が大きいということは、薬物の体内分布が広範囲にわたっているか、組織への取り込みが大きいことを意味しています。
一方、分布容積が最少の時は血漿容積(体重の約5%)と同じ時であり、血液中にしか存在しないこととなります。
分布容積が数百Lと体重よりはるかに大きい時は、組織に濃縮して取り込まれていると考えられます。例えば、体重60kgの成人男性の体液容積を見てみると、脈管内液は約3%(体重の5%)、細胞外液(血液5%を含む)は、約12L(体重の20%)、細胞内液は約24L(体重の40%)です。
総体液量は約36L(体重の60%)で、ほぼ0.6/kgです。
代謝
加齢に伴って肝重量が減少し、肝血流量も減少することによって、肝代謝能が低下します。
したがって、高齢者では多くの薬物の代謝が低下することとなります。
特に酸化代謝を受け、肝臓で初回通過効果を大きく受ける薬物では、肝血流量の減少と代謝能の低下により、初回通過効果が減少するので、経口投与後の血中濃度が上昇する可能性があります。
排泄
加齢に伴い、腎臓のネフロン(糸球体および尿細管)の数や腎血流量は減少し、糸球体濾過率および尿細管分泌能(血液から尿管腔への分泌)が低下しますので、腎排泄型の薬物の消失速度が遅くなります。
したがって、腎臓から排泄される割合の高い薬物では、腎機能低下により体内消失速度が遅延し、薬物血中濃度が高くなります。
年齢とともに筋肉量が減少し、クレアチニンの生成が低下するので、高齢者では血清クレアチニンが腎機能の低下を反映しないことがあります。
血清クレアチニン血が正常範囲内にある場合でも、糸球体濾過値(GFR)が低下していることがあるので注意が必要です。
高齢者の特徴
高齢者は、運動能力などの低下により転倒しやすくなりますが、転倒の危険因子の1つとして向精神薬や起立性低血圧を起こす薬物などの服用が挙げられます。
よって、以下の点に留意する必要があります。
①薬物の投与量を少量から開始する
②服用方法を単純化する
③併用薬の数を最小限にする
④効果の判定や薬物血中濃度測定を含めた評価を行う
⑤副作用の発現に注意する
- 理解力の低下により、飲み忘れ、過量服用の危険性がある
- 視力や運動機能などの障害がある場合、1回量包装の使用や口腔内崩壊錠を使用するなどの配慮が必要
- 健康食品やサプリメントを摂取していることがあり、相互作用を有するものがないか注意する
- 複数の疾患に罹患し、多くの薬物を併用していることが多いため、重複投与、同効薬の投与、薬物相互作用に配慮する必要がある
- 原疾患が多い場合、薬による副作用かどうか判断がつきにくい場合も多い
新生児
出生時から27日(生後1~2週間)を新生児期といいます。
新生児の諸機関の成熟度は在胎期間によって異なります。
在胎週数は、最終月経第1日から起算した満週数で表します。
早産児:在胎37週未満で出生した児
正期産児:在胎37週以上42週未満で出生した児
過期産児:在胎42週以上で出生した児
低出生体重児:出生体重2500g未満の児
新生児期から成人に達するまで、生体や諸臓器の機能が著しく変化するのに伴い、薬物の体内動態が大きく変動します。
また、早産児では各機能が新生児よりも未熟であり、薬物の代謝や排泄も低下しています。
吸収
新生児期には、胃酸酸性が少なく、胃内pHが高いので、弱酸性の薬物はイオン化しやすく、イオン型薬物は脂質膜を透過できないので、吸収が低下します。
胃内pHは生後2~3年で成人の値に達するので、新生児期は生後日数により薬物の吸収が変わる可能性があります。
在胎週数32週未満の早産児では、胃酸酸性能は低く、新生児ではいないよう物の排出時間が長くなる傾向があります。
そのため、最高血中濃度に達する時間が遅れることがあります。
新生児期は表皮も薄く、皮膚からの吸収は成人の数倍と大きく、ステロイド薬の塗布などで全身的な影響が出ることがあります。
新生児の皮膚消毒にポピドンヨード剤を使用し、甲状腺機能低下症などが起きた報告もあります。
分布
新生児期には体水分量が多く(約80%)、体脂肪量、筋肉量は少ないため、水溶性薬物の体重当たりの投与量が成人より多めに設定されているものが多いです。
新生児期は血中タンパク量も少ないので、遊離型の薬物比率が多く、効果が強く発現しやすい。
ビリルビンなどのアルブミン結合は、早産児では乳幼児に比べて弱い。
代謝
新生児期の薬物代謝能は極めて低いため、薬物の半減期は延長し、長く体内に貯留します。
新生児期では、主な薬物代謝経路が成人と異なる場合があります。
例えば、気管支喘息治療薬テオフィリンの代謝は、新生児期には一部N-メチル化によりカフェインへと代謝されることから、中枢興奮作用(てんかんなど)の増強に注意します。
胎児期には、成人で主な薬物代謝酵素であるCYP3A4、CYP2C9、CYP2E1、CYP2D6はほとんど存在しないか、わずかに発現しているだけで、出生後に活性が上昇します。
胎児の肝臓には、CYP3A7が主となっています。
このCYP3A7は出産後速やかに減少し、CYP3A4が上昇してきます。
CYP1A2活性は、生後すぐには上昇せず、生後3か月程度で上昇を始めます。
申請時におけるグルクロン酸抱合能は、一般的に低いことから、抗菌薬のクロラムフェニコールによる灰白症候群が起こることがあります。
クロラムフェニコールは、肝臓でグルクロン酸抱合を受けて排泄されますが、新生児期はグルクロン酸抱合能が不十分なため、体内で蓄積されます。
そのため、急性循環不全が起こり、皮膚が灰白色を呈し、死に至ることがある症状です。
排泄
出生後、腎血流量は上昇し、糸球体濾過率も生後急速に上昇します。
糸球体濾過率は正期産児では、出生時2~4mL/分ですが、生後2~3日の間に急速に増加し、8~20mL/分にまで急増します。
一方、早産児では出生時1mL/分前後で、出生2~3日で2~3mL/分に増える程度です。
多くの薬物の尿中への排泄は、正期産児では生後6ヶ月から1歳までに成人の機能に近づきます。
妊婦
妊婦への薬物治療に際しては、母体の生理的変化、胎児への催奇形性、薬物の胎盤移行性などの問題があります。
妊娠週数は、最終月経開始日を0日として、2週0日が排卵・受精日で40週0日(280日目)が分娩予定日となるので、2週目までは受精していないことになります。
受精卵は子宮内で分化し、受精後17日から57日までに脳などの中枢神経、心臓などの循環器、消化器などが形成され、妊娠16週頃には胎盤が完成し、出産までの間に胎児の諸機関はそれぞれの時間に発育・成長します。
母体の薬物動態
妊娠中は血中プロゲステロンなどの増加により、消化管運動が低下し、胃酸分泌の低下が起こります。
黄体ホルモンであるプロゲステロンは、平滑筋収縮を減少する作用を有し、子宮収縮を抑制しますが、同時に消化管の運動も抑制します。
また、血漿容積が増大し、細胞間液が貯留するため、薬物血中濃度は低下します。
血漿容積の増大や血清アルブミンの低下などによって、タンパク結合率も低下します。
血漿タンパクは妊娠3ヶ月で妊娠前の85%にまで減少し、その後も徐々に減少しますが、出産後6~12周で回復します。
妊娠末期になると、脂肪酸などが増加し、アルブミンと競合することにより、遊離型の薬物がさらに増加します。
母体の薬物代謝の変化は、薬物によって異なり、代謝が促進されるものと抑制されるものがあります。
カフェインは妊娠による代謝低下がありますが、妊娠中の肝血流量は増加します。
血症容量が増大し、心拍出が増大するため、腎血漿流量は増加し、糸球体濾過量も増加します。
そのため、未変化体のまま腎臓から排泄される薬物では、体内からの消失が早くなります。
妊娠中にけいれんを起こすと、胎児の低酸素状態や流産・早産を引き起こす危険性があります。
抗てんかん薬のバルプロ酸ナトリウムには、催奇形性を引き起こす危険性があります。
血中濃度モニタリングを行って、慎重に投与する必要があります。
胎児の薬物動態
胎児の薬物代謝および排泄は、一般的に遅くなります。
胎児期には、比較的初期の段階から薬物代謝酵素の発現が認められますが、成人の代謝酵素と異なります。
また、胎児の血液脳関門は未発達なので、多くの薬は脳内へ移行するので注意が必要です。
詳細は上記、新生児の項に記載しています。
妊娠期間と薬物の影響
受精から18日以前の受精卵は、薬物の影響が強いと着床できず流産する可能性が高いです。
ワクチンなどにも注意が必要です。
受精後19日から57日までの期間を胎芽期といい、器官形成期で環境変化によって奇形が起こりやすい。
中枢神経や心臓、消化器、四肢などは受精19~37日に発生・分化します。
妊娠9週からは胎児期に入り、口蓋などで発生障害が起こり得ます。
12週までは催奇形性期で、可能な限り薬物療法を行いません。
妊娠16週頃には胎盤が完成し、母体血中の薬物は胎盤を介して胎児に移行します。
妊娠5か月を過ぎると、薬物による胎児の機能や発育への影響、胎児環境への影響があります。
薬物の胎児移行性
一般に胎児血は母体血に比べて酸性で、塩基性薬物では胎児血中濃度が母体血中濃度より高くなることがあります。
分子量が600以下の薬物や脂溶性が高い薬物は、特に移行しやすくなります。
また、母体の血漿アルブミンが低下するので、遊離型薬物が増加し、胎児に移行しやすくなります。
抗血栓薬のヘパリンナトリウムや、糖尿病治療薬のインスリンは、胎盤通貨制はほとんどありません。
逆に、薬物の胎児移行性を利用して、母体に投与した薬物で胎児治療を行うこともあります。
妊婦に投与禁忌になっている薬剤の一部を下記に示します。
| 一般名 | 措置 | 理由の一部抜粋 |
|---|---|---|
| トリメタジオン | 投与禁忌 | 催奇形性 |
| ノルエチステロン | 投与禁忌 | 催奇形性 |
| ワルファリンカリウム | 投与禁忌 | 催奇形性、出血による胎児死亡 |
| アンジオテンシン変換酵素阻害薬 | 投与禁忌 | 催奇形性、羊水過少症 |
| グリセオフルビン | 投与禁忌 | 催奇形性、流産 |
| ハロペリドール | 投与禁忌 | 催奇形性の疑い |
| シクロホスファミド | 投与しないことが望ましい | 催奇形性の疑い |
| 酢酸フレカイニド | 投与禁忌 | 動物催奇形性 |
| ニフェジピン | 投与禁忌 | 動物催奇形性 |
| メトトレキサート | 投与禁忌 | 動物催奇形性 |
| アセタゾラミド | 投与しないことが望ましい | 動物催奇形性 |
| リファンピシン | 投与しないことが望ましい | 動物催奇形性 |
| ナドロール | 投与禁忌 | 動物胎児死亡 |
| 塩酸チクロピジン | 投与しないことが望ましい | 動物母体出血傾向 |
| インドメタシン | 投与禁忌 | 胎児動脈管収縮、羊水過少症 |
| スルホニル尿素系 | 投与禁忌 | 新生児低血糖 |
| アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 | 投与禁忌 | 新生児低血圧、羊水過少症 |
| アスピリン・ダイアルミネート配合 | 妊娠末期禁忌 | 新生児出血異常 |
| 塩酸クロルプロマジン | 投与しないことが望ましい | 新生児振戦 |
| 塩酸クロミプラミン | 投与しないことが望ましい | 新生児呼吸困難、チアノーゼ |
| 炭酸リチウム | 投与禁忌 | 心臓奇形頻度の増加 |
| デカン酸ナンドロロン | 投与禁忌 | 女性胎児男性化のおそれ |
妊婦への注意点
妊婦は、特に薬物服用による胎児への影響を強く心配されます。
奇形は、薬物服用以外の原因不明により起こることがあることを理解してもらう必要もあります。
しかし、安易に薬物摂取をしないように注意することも必要です。
先天奇形は新生児の約3~5%にみられ、そのうち約20%は遺伝子病、5%は染色体異常症、5~10%は外因性のものとされますが、残り65~70%は原因不明といわれています。
薬物による奇形として一般的に知られているものには、サリドマイド、性ステロイドホルモン、アルコール、有機水銀による先天性水俣病などがあります。
- サリドマイドは、睡眠薬やつわりの薬として1958年から1962年に日本で発売され、妊婦が服用し、胎児にアザラシ肢症や上腕無形成などを引き起こしました。
- 合成エストロゲンのリン酸ジエチルスチルベストロールを妊娠初期に投与された母親から生まれた女児に、膣腺がんや子宮頚部腺がんの発生が報告されています。
手足の長骨がない、または極度に短いため、手足が直接胴体についているように見えるため、アザラシのように見えることから名付けられた先天性奇形。
内臓の配置異常を併発している場合もある。
水俣病とは、化学工場から排出されたメチル水銀化合物に汚染された魚介類を摂取したために発生した中毒性の神経疾患。
熊本県水俣湾周辺を中心として発生したため、水俣病とよばれる。
全体的な脳実質の萎縮を生じ、特に運動・触覚・視覚・聴覚・平衡感覚に障害が起こる。
症状は手足のしびれ、振戦、脱力、耳鳴り、視野狭窄、難聴、構音障害、嗅覚・味覚障害などがある。
授乳婦
母乳は最良の栄養源で、牛乳などの異種タンパクを含まないためアレルギーがなく、特に出産直後の初乳には免疫物質が多く含まれていて、乳児を感染から予防します。
また、母指の精神的安定など、多くの利点があります。
しかし、乳汁中へ移行する薬物もあるため、授乳時には注意が必要です。
乳汁中への薬物移行
分子量が200以下の薬物は、容易に乳汁中へ移行します。
特に脂溶性の薬物は、乳汁中に多くの脂質が含まれているので、乳汁中濃度が高くなりやすいです。
乳汁のpHは、血漿のpHより低いので、弱塩基性の薬物が移行しやすくなります。
母親が腎機能障害などがあると、母体に薬物が蓄積し、乳汁中濃度も高くなります。
出産後初期の乳汁は、免疫物質を多く含み、タンパク質含有量が多い初乳が分泌されますが、その後は脂肪が多い成乳へと変化していきます。
また、授乳中にも成分変化があるといわれていて、授乳開始時よりも終了時の方が母乳に含まれる脂肪量が多いといわれています。
よって、母体血中濃度と母乳中濃度を比較しながら、薬物移行を検討する必要があります。
乳汁1000mLにどのくらい移行するかを概算し、乳汁中の薬物量が乳児への投与量と考えます。
【引用・参考文献】
折井孝男監修:「説明力UP!臨床で役立つ薬の知識」、学習研究社、2007.3
浜田康次監修:「スラスラわかる薬のメカニズム」、医学芸術社、ナーシングカレッジ2006年10月臨時増刊号、第10巻第12号通巻148号
古川裕之編著:「ナースに必要な薬の基本 キー・ドラッグ」、学習研究社、2007.12

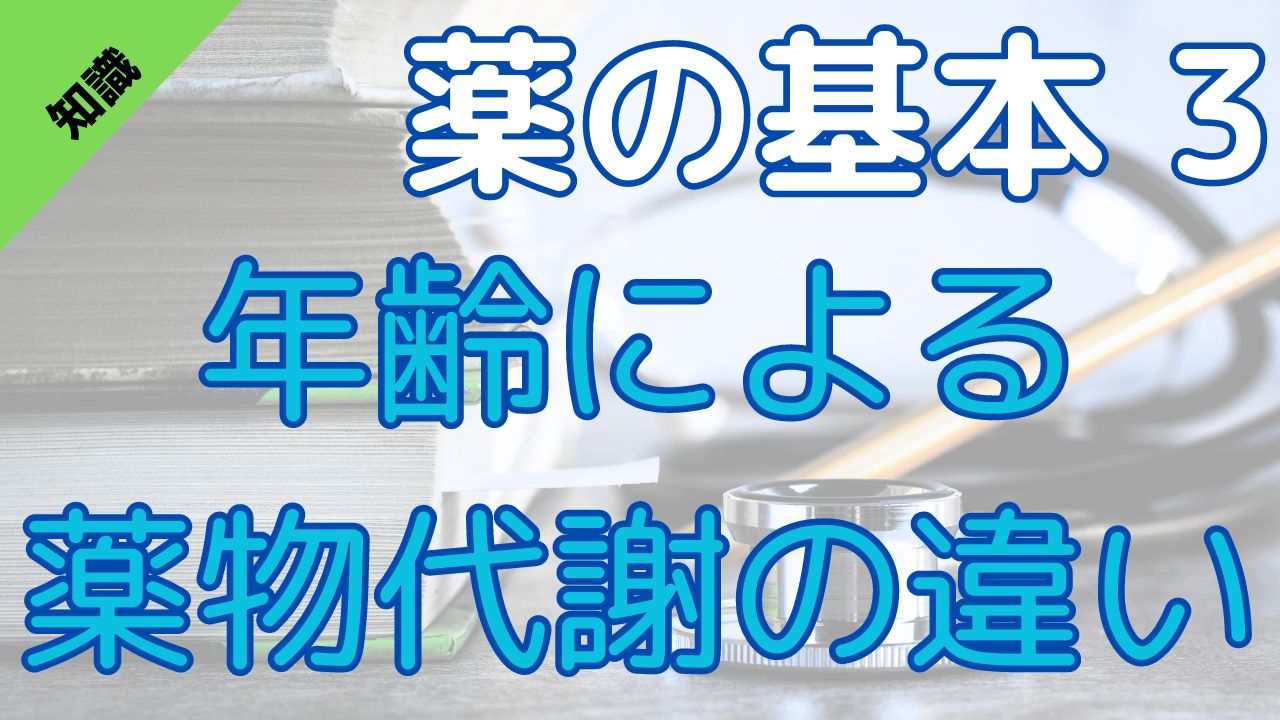


コメント