誰しも常に健康でいられません。
突然働けなくなったり、働き方を変えないと、などの場面が出てくるでしょう。
そのような時に一番困るのが、「お金」です。
その場を凌ぐための貯えがあれば、安心して先のことを考えられますが、
家族を養わなければならなかったり、余裕のある生活を送れていなかったりする場合に限って、
体調を崩してしまうことは少なくありません。
まずは職場でどのような休職制度があるか、その間の給与取得の割合を調べることが必要です。
これは会社によってそれぞれの福利厚生がありますので、人事課で簡単に確認することができます。
病気であれば病気休暇、介護が必要な休暇は介護休暇、休職は診断書の有無で給与支払いがあります。
どのくらいの割合で給与を得られるのか、支払い期間について確認しましょう。
他にも国の制度で使える公費があります。
「傷病手当金」と「失業保険」です。
傷病手当金は、不測の事態で仕事を休まなければならなくなった場合に利用可能です。
失業保険は、自己退職でも受給可能ですが、何らかの理由で仕事を辞めなければならなくなったときの救済処置になります。
今回私も使用するにあたり調べることがあったので、使える公費についてまとめておきます。
働けない時に使える公費

不測の事態に働くことができなくなった時、一番に考えるのはお金ではありませんか?
治療費の支払いに加えて、その後の療養に必要な生活費、固定費の支払いに思いを巡らします。
緊急時に備えてたくさんの貯えをされている方というのは多くありません。
また、その日を過ごすことにも困難である方もいるでしょう。
そんな時のために、どのような補償を得られるのかは知っておく必要があります。
具体的には次の3つです。
- 傷病手当金
- 失業保険
- 民間保険補償
傷病手当金
病気やケガで急に仕事を休んだときに、生活を保障するためにある制度です。
会社から十分な報酬が受けられない場合に支給されるので、一部支給条件があります。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
保険診療以外の自費診療であっても、就業不可の証明ができれば支給対象となります。
その間の自宅療養期間も対象となります。
ただし、労災保険給付の対象であったり、美容整形など病気とみなされないものは対象外となります。
仕事に就くことができないこと
この状態の判断は、申請後に療養担当者の意見などを基に、仕事内容も加味して考慮されます。
連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
仕事を休んだ日を1日目として、連続3日間(待機期間)休んで4日目以降から支給開始されます。
4日目に一度出勤したとしても、その後休業することになっても、待期期間が成立していれば4日目以降は支給対象となります。
その間、給与の支払いがあったかどうかは関係なく、休んだ期間で支給対象とみなされます。
休業した期間について給与の支払いがないこと
基本的な考え方は、生活保障制度のため給与の支払いがあると支給されません。
ですが、傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
支給される期間は、通算して1年6ヶ月となります。
令和2年7月1日以前に支給開始がされている場合は、開始日を1日目として最長1年6ヶ月となります。
1日あたりの金額 =
(支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準月額を平均した額)÷ 30日 × ⅔
全国健康保険協会HP
病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
引用・一部改訂
失業保険
自己都合の退職時に支給を検討される方がほとんどかと思いますが、雇用保険の補償制度のため、病気やケガで退職を余儀なくされた場合にも利用できます。
ただし、療養が必要ですぐに就職できない状態にあるときは、支給対象となりません。
- ハローワークに来所し、求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、就業につくことができない「失業の状態」にあること
- 離職の日から以前2年間に、雇用保険加入期間が通算12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合は、離職の日から以前1年間に、雇用保険加入期間が通算6ヶ月以上でも可能。
失業保険の受給期間
原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日では1年と30日、360日では1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児などの理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となります。
また、所定給付日数330日、360日の方の延長期間は異なり、それぞれ最大限3年と30日、3年と60日となります。
所定給付日数とは、雇用保険に加入していた人が、離職して失業中に受けられる基本手当(失業等給付)の受給上限日数を定めたものです。
自己都合での退職の場合:離職日以前から2年の間で、被保険者期間が通算して12カ月以上
倒産や解雇等の場合(特定受給資格者・特定理由離職者):離職日以前から1年の間に、被保険者期間が通算して6カ月以上
定年や自己都合により退職した人は「一般の受給資格者」、勤務先の倒産や解雇、賃金の大幅な減少や賃金の未払い、会社から退職を勧められるなど、会社都合の理由で退職した方は「特定受給資格者」となります。また、6か月や1年など有期雇用契約で働いていて、本人が希望しても契約が更新されなかった人や、病気やケガ、出産や育児、家族の看護など、正当な理由があって退職した人は「特定理由離職者」となります。
支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められています。
| 30歳未満 | 7,065円 |
| 30歳以上45歳未満 | 7,845円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,635円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,420円 |
ハローワークインターネットサービスhttps://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
引用・一部改訂
民間保険補償
各保険会社が販売している商品になります。
様々な商品がありますが、仕事ができなくなった補償としては、生活補償保険があります。
しかし、支給条件は「寝たきり」の状態になった場合など、今後も働くことが困難な状況下での支給となり、万が一の補償となります。
一般的に使用できる補償は医療保険で、入院・手術・通院に対しての商品があります。
様々な保険がありますので、ほけんの窓口などを利用して検討しましょう。
給付金のサポートをしてくれるサービス(任意)
給付金の手続きを進めるのはなかなか労力を伴います。
まず何が利用できるか、どの程度の期間・支給を確保できるのか、その後の生活設計を立てる、など、仕事を探すにしてもまず情報を仕入れることから始めなければなりません。
このような手間を省くために、退職から支給の手続きまでを代行してくれるものもあります。
下記リンクは、ご参考程度に掲載しておきます。
利用される場合は、自分に必要なものかどうかを見極めて検討しましょう。

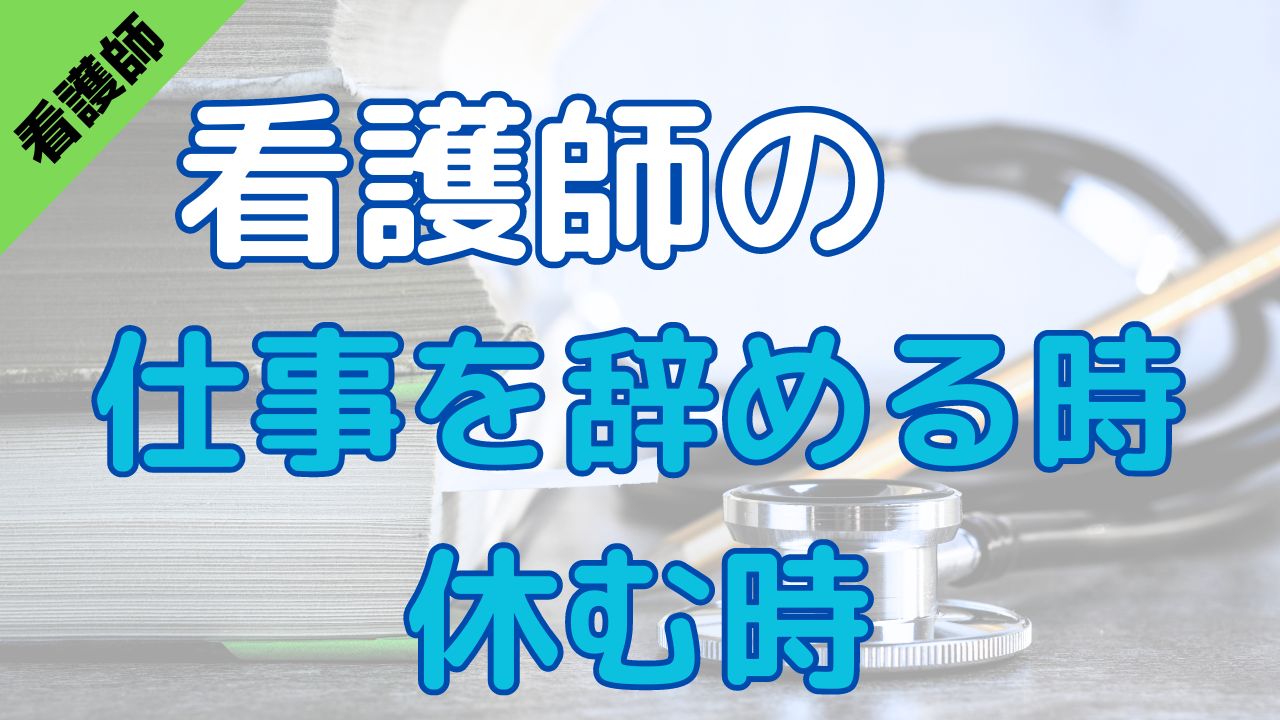


コメント