抗菌薬選択の基本
- どこの臓器に感染しているか
- どんな菌が感染しているか
- その感染源に対してベストな抗菌薬は何か
上記を基本理念として治療を開始します。
実際には、どの臓器に感染しているかを判断して、感染を起こす頻度の高い菌があります。
その原因菌として推定されるものに対して、多くの菌に対応できる抗菌薬を選択し、
とりあえず先に治療を開始します。
グラム染色とは、スライドガラスに検体を塗って、専用の試薬をかけ顕微鏡で見ると、
青(紫)もしくは赤に染まった菌をみることができます。15分くらいで判別できる検査です。
どちらの色に染まるかで、グラム陰性/陽性の判断ができ、より適切な抗菌薬を選択できます。
ちなみに青(紫)はグラム陽性、赤はグラム陰性となります。
詳細な検査は培養検査となります。
抗菌薬投与の原則
- 十分な量の抗菌薬を投与すること
- 必要な期間だけ投与し、長期間投与にならないようにすること
最初から最大量を使用する必要があります。
「最小発育阻止濃度(MIC)」とよばれる抗菌薬の血中濃度で、病原菌は死滅します。
しかし耐性菌ができる可能性があり、「耐性菌抑制濃度(MPC)」とよばれる濃度以上が必要です。
よって、できるだけMPC以上の血中濃度を保つことが重要となります。
抗菌薬の効果的な使い方
- 1回に投与する量を増やす方法(濃度依存性)
- 1日に投与する抗菌薬の総量を等間隔で複数回に分ける方法(時間依存性)
- 1日に投与する総量を増やす方法(時間依存性)
| 抗菌効果 | 効果的な投与方法 | 抗菌薬の分類 |
|---|---|---|
| 濃度依存性 | 1回に投与する量を増やす | キノロン系 アミノグリコシド系 |
| 時間依存性 | 1日に3-4回に分けて投与する | ペニシリン系 セフェム系 カルバペネム系 リンコマイシン系 |
| 1日に投与する量を増やす | マクロライド系 テトラサイクリン系 グリコペプチド系 |
術後の抗菌薬使用
手術時の抗菌薬投与には予防と治療の2つの側面があります。
予防投与:感染が起こる前に術後感染を防ぐことを目的とし、感染しやすい菌に対する抗菌薬を使用
治療投与:腹膜炎や膿瘍を治療するために原因菌に対しての抗菌薬を使用
原則として、清潔手術では抗菌薬の投与は不要であり、準清潔手術では予防投与を行います。
不潔/感染手術では当初より治療投与を行います。
しかし、汚染度の少ない清潔手術であっても、感染が起きると生命の危機となるような手術(心血管系手術、心臓ペースメーカー移植術、人工関節形成術、脳神経外科手術など)では予防投与を行います。
手術時の予防投与は、
①予想される菌に効果がある
②手術部位への移行が良い
③副作用が発現しにくい
④値段が安い
などを考慮して選択されます。
患者の皮膚や粘膜などの常在菌も、手術によって切開されると感染の原因となり得ます。
手術部位ごとに存在する菌は異なるため、それぞれに合った抗菌薬を選択しなければなりません。
PK-PD(PharmacoKinetics-PharmacoDynamics)理念
薬物動態(PK:薬がどれだけ体内に存在しているか)と
薬力学(PD:薬がどれだけその部位で作用しているか)の両方を合わせて考えていきます。
これが、PK/PD理論の概念となります。
抗菌薬の効果は、血中濃度が高くなるとその作用も強くなります。
この時の抗菌薬の作用を測る指標として、MIC(最小発育阻止濃度)があります。
MIC(最小発育阻止濃度)とは、「細菌の増殖を抑制するために必要な最小の薬物濃度」です。
そのため、MICの値よりも抗菌薬の濃度が低ければ菌が増殖してしまいます。
よってMICの値より高い濃度を保つ必要があります。
この時、薬物動態(PK)では「Cmax(最高血中濃度)」、「AUC(血中濃度-時間曲線下面積)」
または「t(作用時間)」の三つの要素を考える必要があります。
Cmax/MIC:Cmax(最高血中濃度)に対するMICの割合
AUC/MIC:AUCに対するMICの割合
Time above MIC:MICより高い血中濃度で推移した時間
抗菌薬の分類
抗菌薬にはたくさんの種類がありますが、特徴的な構造からいくつかの系統に分類できます。
| 大きな分類 | 抗菌薬の分類 | 効果的な投与法 |
|---|---|---|
| β-ラクタム系 | ペニシリン系 | 投与回数を増やす 点滴では点滴時間を長くすることも有効 |
| セフェム系 | ||
| カルバペネム系 | ||
| アミノグリコシド系 | 1回投与量を増やす 点滴では点滴時間を短くすることも有効 | |
| キノロン系 | 1日の総投与量および1回の投与量を増やす | |
| マクロライド系 | 1日の総投与量を増やす 可能であれば1回の投与量を増やす | |
| テトラサイクリン系 | 1日の総投与量を増やす | |
| グリコペプチド系 | 1日の総投与量を増やす 投与間隔などは血中濃度を参考に調節する |
このなかで、ペニシリン系、セフェム系、カルバペネム系は共通の構造をもっていて、
この3種類をまとめてβ-ラクタム系という分類をすることもありますが、それぞれ特徴は異なります。
ペニシリン系抗菌薬
ペニシリンは、治療薬として一番初めに使われた抗菌薬です。
「JIN-仁-」という大沢たかおのドラマをご存知ですか?
脳外科医の大沢たかおが江戸時代にタイムスリップして、江戸の人たちを医学で救っていきます。
その過程でペニシリンを作ってしまう場面が描かれています。
ペニシリン系抗菌薬は、抗菌域が広い種類の薬剤は少なく、
原因菌がわからない状況で使用できるタイプのものではありません。
しかし、特定の菌に対してはとても優れた効果を発揮します。
このように抗菌薬の有効性を示す抗菌スペクトルとよばれる指標があります。
その指標に沿って適切な抗菌薬を選択して使用します。
ペニシリン系抗菌薬のアナフィラキシー反応は、β-ラクタム系抗菌薬の中で最も強く出ます。
その他、比較的多い副作用として、下痢があります。
| 剤型 | 分類 | 代表的商品名®(一般名:略号) |
|---|---|---|
| 注射薬 | 天然ペニシリン | ペニシリンG (ベンジルペニシリン:PCG) |
| 広域ペニシリン | ビクシリン (アンピシリン:ABPC) | |
| 広域ペニシリン (β-ラクタマーゼ阻害薬配合) | ユナシン-S (スルバクタム・アンピシリン:SBT/ABPC) | |
| 複合ペニシリン (耐性ブドウ球菌用ペニシリン配合) | ビクシリンS (アンピシリン・クロキサシリン:ABPC/MCIPC) | |
| 抗緑膿菌ペニシリン | ペントシリン (ピペラシリン:PIPC) | |
| 抗緑膿菌ペニシリン (β-ラクタマーゼ阻害薬配合) | ゾシン (タゾバクタム・ピペラシリン:TAZ/PIPC) | |
| 内服薬 | 天然ペニシリン (グラム陽性菌用ペニシリン) | バイシリンG (ベンジルペニシリンベンザチン:DBECPCG) |
| 広域ペニシリン | サワシリン (アモキシシリン:AMPC) | |
| 広域ペニシリン (β-ラクタマーゼ阻害薬配合) | クラバモックス (クラブラン酸・アモキシシリン:CVA/AMPC) |
セフェム系抗菌薬
セフェム系抗菌薬は、第1選択薬として使用される頻度が高く、比較的安全性も高い抗菌薬です。
セフェム系抗菌薬は、第1~4世代に分けられています。
一般に世代が大きくなるほど効果のある菌の種類が増えますが、抗菌効果は比例しません。
薬剤ごとに使い方の特徴も異なります。
副作用の頻度は低く、発現した場合も軽度で済みます。
利尿薬との併用で急性腎不全のリスクが高まります。
ペニシリンアレルギーがある場合は、セフェム系にも5%程度アレルギーを示すことがあります。
| 剤型 | 世代 | 代表的商品名®(一般名:略号) |
|---|---|---|
| 注射薬 | 第1世代 | セファメジンα(セファゾリン:CEZ) |
| 第2世代 | パンスポリン(セフォチアム:CTM) フルマリン(フロモキセフ:FMOX) | |
| 第3世代 | ロセフィン(セフトリアキソン:CTRX) モダシン(セフタジジム:CAZ) スルペラゾン(スルバクタム・セフォペラゾン:SBT/CPZ) | |
| 第4世代 | プロアクト(セフピロム:CPR) マキシピーム(セフェピム:CFPM) | |
| 内服薬 | 第1世代 | ケフラール(セファクロル:CCL) |
| 第2世代 | パンスポリンT(セフォチアム:CTM) | |
| 第3世代 | セフゾン(セフジニル:CFDN) | |
| 第4世代 | フロモックス(セフカペン・ピポキシル:CFPN-PI) |
カルバペネム系抗菌薬
カルバペネム系抗菌薬は、非常に多くの菌に対して効果があり、短時間で強い殺菌作用を持ちます。
原因菌の判明前の初期治療や、抗菌薬療法の切り札的な存在として使用される場合があります。
カルバペネム系抗菌薬は、ペニシリン系やセフェム系と異なり、抗菌スペクトルが似通っていて、
薬剤ごとの組織移行性が大きく異なるということはありませんが、薬剤ごとの特徴は異なります。
副作用で注意するものとして、けいれんなどの中枢神経系の副作用があります。
その他、下痢、発疹などがありますが、重篤になるものは少ないとされています。
また注意事項として、抗てんかん薬のバルプロ酸ナトリウムと併用すると、
バルプロ酸ナトリウムの血中濃度が低下して、てんかん発作を起こす危険性があり、併用禁忌です。
| 剤型 | 分類 | 代表的商品名®(一般名:略号) |
|---|---|---|
| 注射薬 | カルバペネム系 | チエナム(イミペネム・シラスタチン:IPM/CS) |
| カルベニン(パニペネム・ベタミプロン:PAPM/BP) | ||
| メロペン(メロペネム:MEPM) | ||
| オメガシン(ビアペネム:BIPM) | ||
| フィニバックス(ドリペネム:DRPM) |
アミノグリコシド系抗菌薬
アミノグリコシド系抗菌薬は、単独で特定の感染症に高い効果を持つ薬剤があります。
また、他の抗菌薬と一緒に使用することで相乗効果が得られる薬剤もあります。
アミノグリコシド系抗菌薬は、対象となる感染症によってⅠ~Ⅴ群に分けられます。
Ⅰ群は結核、Ⅳ群は淋菌感染症、Ⅴ群はMRSA感染症と、適応となる感染症が決まっています。
また、Ⅱ群、Ⅲ群は多くの感染症に使用される可能性がありますが、
Ⅲ群はⅡ群の進化版のような特徴を持つため、ほとんどがⅢ群の抗菌薬を使用されます。
Ⅲ群の抗菌薬は、β-ラクタム系抗菌薬と一緒に使うと、相乗効果が得られます。
アミノグリコシド系抗菌薬は、比較的高頻度に聴器毒性や腎毒性などの進行な副作用が発現します。
通常、腎障害が起こった場合でも投与中止で回復しますが、
聴器毒性は、内耳細胞の一部が破壊される場合もあり、聴力回復が望めない場合もあります。
| 剤型 | 分類 | 代表的商品名®(一般名:略号) |
|---|---|---|
| 注射薬 | Ⅰ群 抗結核菌作用を主な特徴とするもの | 硫酸ストレプトマイシン (ストレプトマイシン硫酸塩:SM) 硫酸カナマイシン (カナマイシン硫酸塩:KM) |
| Ⅱ群 主にグラム陰性菌に抗菌力をもつもの (緑膿菌には無効) | ビスタマイシン (リボスタマイシン硫酸塩:RSM) | |
| Ⅲ群 緑膿菌を含むグラム陰性菌に抗菌力をもつもの | ゲンタシン(ゲンタマイシン硫酸塩:GM) エクサシン(イセパマイシン硫酸塩:ISP) 硫酸アミカシン(アミカシン硫酸塩:AMK) トブラシン(トブラマイシン:TOB) | |
| Ⅳ群 淋菌のみに適応をもつもの | トロビシン (スペクチノマイシン塩酸塩:SPCM) | |
| Ⅴ群 MRSAのみに適応をもつもの | ハベカシン (アルベカシン硫酸塩:ABK) | |
| 内服薬 | 消化管殺菌用 | カナマイシン カプセル・シロップ・ドライシロップ (カナマイシン硫酸塩:KM) |
キノロン系抗菌薬
キノロン系抗菌薬は、ペニシリン系抗菌薬やセフェム系抗菌薬の内服薬で
効果が期待できない場合に有用な抗菌薬です。
しかし、多くの菌に対する効果と副作用の少なさから、
感染症の原因菌を特定せずに安易に使用されていることが多いのが問題です。
キノロン系抗菌薬は第1世代のキノロン系抗菌薬に始まり、
現在はニューキノロン薬という分類をされます。
主に尿路感染症に使用されてきた第2世代前期、全身性の感染症に使用されてきた第2世代後期、
グラム陽性菌、グラム陰性菌、否定形菌に抗菌活性を示す第3世代、
嫌気性菌を含む非常に多くの菌に抗菌活性を示す第4世代に分類されます。
ニューキノロン系抗菌薬は、第2世代の2剤を除きすべて内服薬ですが、
消化管からの吸収が良く高い効果を示します。
非ステロイド性消炎鎮痛薬との併用により、けいれん発作が誘発されるので注意が必要です。
他には中枢神経系症状や光線過敏症、心電図上のQT延長、高齢者でのアキレス腱断裂などがあります。
また、小児や妊婦への投与は安全性が確認されていないため、
バクシダール®(ノルフロキサシン)、オゼックス®(トスフロキサシン)以外の薬剤は禁忌です。
| 剤型 | 分類 | 世代 | 代表的商品名®(一般名:略号) |
|---|---|---|---|
| 内服薬 | キノロン | 第1世代 | ウイントマイロン(ナリジクス酸:NA) |
| ニューキノロン | 第2世代 尿路用 | バクシダール(ノルフロキサシン:NFLX) フルマーク(エノキサシン:ENX) | |
| 第2世代 全身用 | タリビット(オフロキサシン:OFLX) シプロキサン(シプロフロキサシン:CPFX) スオード(プルリフロキサシン:PUFX) | ||
| 第3世代 | クラビット(レボフロキサシン:LVFX) オゼックス(トスフロキサシン:TFLX) | ||
| 第4世代 | アベロックス(モキシフロキサシン:MFLX) グレースビット(シタフロキサシン:STFX) ジェニナック(ガレノキサシン:GRNX) | ||
| 注射薬 | ニューキノロン | 第2世代 全身用 | シプロキサン(シプロフロキサシン:CPFX) パシル(パズフロキサシン:PZFX) |
マクロライド系抗菌薬
マクロライド系抗菌薬は、適応菌種が市中肺炎をはじめとした呼吸器感染症の原因菌をよくカバーしていることや、副作用の少なさなどから臨床では広く使用されています。
しかし第1選択薬ということになれば適応症が限られていることや、
マクロライド耐性菌が増加している現状から、適正使用が求められています。
マクロライド系抗菌薬は14員環、15員環、16員環と構造による特徴で分類され、
抗菌活性の高さに差はあっても、抗菌スペクトルでは薬剤間での差はほとんどありません。
組織移行性も優れていて、血中濃度よりも組織ない濃度の方が高くなることが特徴です。
副作用は稀にQT延長などの報告がありますが、ほとんどが一過性の食欲不振、悪心・嘔吐などの
消化器症状であり、安全性の高い薬剤であるといえます。
多剤との併用は、ワーファリン®と併用する場合、ワーファリンの代謝が阻害され、
出血傾向やプロトロンビン時間の延長などが知られています。
| 剤型 | 分類 | 代表的商品名®(一般名:略号) |
|---|---|---|
| 内服薬 | 14員環 マクロライド | エリスロシン(エリスロマイシン:EM) |
| 14員環 ニューマクロライド | クラリス(クラリスロマイシン:CAM) ルリッド(ロキシスロマイシン:RXM) | |
| 15員環 ニューマクロライド | ジスロマック(アジスロマイシン:AZM) | |
| 16員環 マクロライド | ジョサマイシン(ジョサマイシン:JM) リカマイシン(ロキタマイシン:RKM) | |
| ケトライド系 | ケテック(テリスロマイシン:TEL) | |
| 注射薬 | 14員環 マクロライド | エリスロシン(エリスロマイシン:EM) |
テトラサイクリン系抗菌薬
テトラサイクリン系抗菌薬が第1選択薬として使用されるのは、
ライム病、ブルセラ病などの人畜共通感染症や、他の抗菌薬が無効な場合です。
内服薬でも注射薬なみの効果を得ることができます。
しかし吸収を低下させるものとして、牛乳、鉄剤、カルシウム、マグネシウムなどがあるので、
カルシウムなどを含む薬剤と併用するときには1~2時間時間をずらす必要があります。
テトラサイクリン系抗菌薬に共通の副作用は、悪心・嘔吐などの消化器症状があります。
また皮膚・口腔内の色素沈着、頭蓋内圧亢進による視野障害・頭痛や聴器障害にも注意が必要です。
他にも歯のエナメル合成を阻害して、元に戻らない色調変化やエナメル質の形成不全を生じるため、
8歳以下の小児には投与できません。
妊婦にも胎児の骨形成不全を生じるため使用できません。
| 剤型 | 世代 | 代表的商品名®(一般名:略語) |
|---|---|---|
| 注射薬 | 第2世代 | ミノマイシン(ミノサイクリン:MINO) |
| 内服薬 | 第1世代 | アクロマイシンV(テトラサイクリン:TC) |
| 第2世代 | ビブラマイシン(ドキシサイクリン:DOXY) | |
| ミノマイシン(ミノサイクリン:MINO) |
グリコペプチド系抗菌薬
グリコペプチド系抗菌薬には、抗MRSA薬として使用されている抗菌薬です。
バンコマイシン®点滴静注用はもっとも代表的な抗MRSA薬として世界中で使用されているため、
有効性や副作用などの情報が多くあります。
注射用タゴシッド®はアメリカでは使用されていません。
バンコマイシン®酸は抗MRSA薬ではなく、クロストリジウム・ディフィシル腸炎に使用されます。
抗MRSA薬の使用時に注意するのは、MRSA感染症なのか保菌状態なのかを適切に判断することです。
通常、無菌である部位(血液や髄液など)の検体からMRSAが検出されれば感染と判断できますが、
喀痰から検出された場合には、感染か保菌か判断が難しい場合があります。
保菌であると抗MRSA薬を投与する必要がないので、適切な判断が重要となります。
| 剤型 | 代表的商品名®(一般名:略号) |
|---|---|
| 注射薬 | バンコマイシン(バンコマイシン塩酸塩:VCM) |
| タゴシッド(テイコプラニン:TEIC) | |
| 内服薬 | バンコマイシン酸(バンコマイシン塩酸塩:VCM) |
【引用・参考資料】
監修:三鴨廣重、「ナースのための抗菌薬 はじめの一歩」、南江堂、2011.8


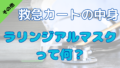

コメント