リンパ浮腫とはなんだろう。
普段は耳慣れない言葉ですが、近年は美容やマッサージなどの場面で、リンパマッサージという言葉を聞くことがあると思います。
リンパ液は、血液と同じように循環しながら老廃物を除去する役割を果たしています。
何らかの影響でこのリンパ液の流れが悪くなった時、そこに留まるリンパ液が増えてくることで、浮腫みが出た状態をリンパ浮腫とよんでいます。
「何らかの影響で」という原因の一つにがんという病気があるのです。
がんの直接的な影響も考えられますが、手術によってリンパ節を取ってしまった場合も起こり得ます。
リンパ浮腫は出現してしまうとなかなか治らないものです。
予防と悪化防止に努めるためには、正しい知識と正しい方法を知ることが必要なのです。
ここではその基本となる知識をつけられるように、まとめていこうと思います。
身体の水分には何が含まれているか

身体の水分は血液だけではありません。
細胞の中にある体液:細胞内液
細胞の外にある体液:細胞外液
細胞外液:血漿、細胞間液、リンパ液、脳脊髄液、消化液、関節液
※血漿:血液は赤血球などの血球と、その他液体成分の血漿に分かれます
年齢によって差がありますが、身体の約60%がこれらの水分でできています。
これらが常に循環を繰り返すことで、身体の細胞に必要なものが運搬されていきます。
リンパ液とは
組織に分布した組織間液を回収してリンパ液になります。
同時にタンパク質や白血球、ウイルス・細菌なども同時に取り込まれます。
リンパ液は無色または淡い黄色をした透明な液体ですが、リンパ節を通過すると細胞成分を多く含むようになり、お腹の中で腸からのリンパ管と合流すると、小腸で吸収した脂肪分が含まれ白く濁ります。
リンパ節は、運び込まれたリンパ液に混入している細胞やがん細胞などを血液に入ってしまう前にチェックし、免疫系を活性化して全身に広がらないようにする機能を持っています。
静脈とリンパ管の違い
静脈とリンパ管は、水分や身体の各所で生じた老廃物などを回収して運搬するという役割を果たしているという面ではよく似ています。
よって異常があると心臓に水分が戻りにくくなり、腕や足がむくみますし、重力に逆らって流れるために逆流防止弁が備わっています。
反対に、静脈は筋肉を使うことで血流を流すのに対して、リンパ管は自ら縮んだり、膨らんだりすることでリンパ液を運びます。
また血小板や血液凝固因子は運び込まれないため、リンパ液は固まりません。
リンパ管は直接心臓とつながることはなく、静脈と合流することで血液循環に戻ることができます。
リンパ浮腫とはどういう状態なのか

リンパ浮腫とは、がんの治療やがんそのものの影響などで、リンパ管やリンパ節が傷つけられて、運べなくなったリンパ液が腕や脚に溜まってむくむ病気です。
他にも、生まれつきリンパ管の発育が悪くても、むくむことがあります。
傷ついたリンパ管を正常に戻すことはできないため、いったんリンパ浮腫になると元の状態に戻すことは困難です。
しかし、発症しても早期から対処することで症状の悪化を防ぐことはできます。
ここで正しい知識を身に付けておきましょう。
浮腫を引き起こす原因になる病気
浮腫は静脈とリンパ管に異常が起こった場合に、体内の水分量が多くなってしまうことで生じます。
・毛細血管からの血漿が漏れ出す
・毛細血管からの再吸収が低下する
・リンパ管の組織間液の吸収量が低下する
・リンパ液の運搬量が低下する
などの理由で体内に水分が溜まってしまう状態が出現します。
下記は代表的なむくみの原因となるものです。
病態によってそれぞれ「○○性浮腫」とよばれます。
| 全身に起こる浮腫の種類 | 病名 |
|---|---|
| 心性浮腫 | 心筋梗塞、心臓弁膜症、心筋症、心不全 |
| 肝性浮腫 | 肝硬変、急性肝炎 |
| 腎性浮腫 | 腎不全、腎炎、ネフローゼ症候群 |
| 内分泌性浮腫 | 甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、クッシング症候群 |
| 栄養障害性浮腫 | タンパク漏出性胃腸症 |
| 薬剤性浮腫 | 抗がん剤、避妊薬など |
| その他 | 特発性浮腫 |
| 部分的に起こる浮腫の種類 | 病名 |
|---|---|
| 静脈性浮腫 | 静脈瘤、深部静脈血栓症 |
| リンパ浮腫 | 原発性(一次性)リンパ浮腫、続発性(二次性)リンパ浮腫 |
| 炎症性浮腫 | 蜂窩織炎など |
| その他 | がんの進行、リウマチ、膠原病、妊娠性浮腫、脂肪性浮腫、廃用症候群 |
リンパ浮腫の特徴
上の表の通り、病気以外の原因でリンパ管だけの異常による局所的な浮腫がリンパ浮腫です。
リンパ管の異常がある部分は、発症の早期では水分が中心で移動しやすい特徴がありますが、徐々に水分以外のタンパク質や繊維組織、脂肪組織も増加していくため、慢性化すると朝になってもむくみが改善しなくなります。
また、身体に侵入した細菌をリンパ節で殺菌するはずの白血球が、リンパ節まで運搬されにくくなるため、細菌感染に対抗できず蜂窩織炎を発症しやすくなります。
このように浮腫が進行してしまうと、外見上にも着用する服にも影響が出たり、握りにくい・座りにくいなど日常生活にも支障を及ぼします。
いかに合併症を予防し、毎日のセルフケアを行うかが重要になります。
また、続発性リンパ浮腫は治療後3年以内に発症することが多いといわれています。
リンパ浮腫に伴う合併症

リンパ浮腫を起こして最も問題となるのは合併症です。
最も重症な場合は、血液に菌が混入し全身の臓器に影響を及ぼす敗血症で、生命の危険もあります。
浮腫を起こした部分の炎症は、半数近くの患者さんが経験します。
リンパ液が循環しにくくなることで、細菌感染に弱くなるので、皮膚や内部の炎症を起こします。
炎症を起こすと、毛細血管から血漿が漏れ出しやすくなり、組織間液が増加するため浮腫が悪化します。
そのため改善には時間がかかり、炎症を繰り返すことになるため、早期の対応が重要なのです。
病名としては、蜂窩織炎、丹毒、リンパ管炎、急性皮膚炎、リンパ漏、リンパ小疱、象皮症、皮膚潰瘍、多毛症があります。
リンパ浮腫の重症度
| 病期分類 | 症状 | 保険診療 | |
|---|---|---|---|
| 0期 | リンパ管に損傷はあるが、まだ臨床的にリンパ浮腫を発症していない | 保険適用外 | |
| 軽度 | Ⅰ期 | 夕方になるとむくむ程度のリンパ浮腫 患肢を挙上することで浮腫は改善する 柔らかさを保っており、圧迫痕が残ることもある | 重症例以外 |
| 中等度 | Ⅱ期 | 患肢の挙上や安静だけでは浮腫が改善しなくなり、圧迫痕がはっきりする | 重症例以外 |
| 重症 | Ⅱ期後期 | 過度の脂肪蓄積や組織の繊維化がみられ、圧迫痕がみられなくなる | 重症例 |
| 重症 | Ⅲ期 | 皮膚の合併症を伴ったリンパ浮腫 リンパ小疱・リンパ漏・象皮症など | 重症例 |
リンパ浮腫の原因となる病態
がんの手術や放射線治療、抗がん剤治療が原因になることがあります。
それぞれの病態を説明していきます。
手術による影響
がんの手術では、進行の程度によって周囲のリンパ節を切除することがあります。(リンパ節郭清)
特に大きなリンパ節が切除の範囲に入ると、リンパ浮腫を発症しやすくなります。
具体的には、腋窩リンパ節、骨盤内リンパ節、鼠径リンパ節となり、他のリンパ節でも郭清範囲が広くなるごとにリンパ浮腫の発生率も高まります。
大きなリンパ節を郭清する可能性があるのは、乳がん、婦人科がん(子宮・卵巣など)、泌尿器科がん(前立腺など)、消化器がん(直腸など)で、リンパ浮腫の発症は高まります。
放射線治療による影響
放射線治療がリンパ管自体に影響することは少ないです。
多くのがん治療は、手術と併用して他の治療を行うことが多いため、リンパ節郭清を行ったかどうかで発症率は異なります。
放射線治療には、早期障害と晩期障害があります。
早期障害は、リンパ管を含んだ皮下組織の再生や炎症に対する反応に遅れがみられますが、一過性の症状であることが多いです。
晩期症状は、時間経過によって皮膚や皮下組織が線維化することで硬くなり、リンパ管を圧迫するため、リンパ管が押しつぶされることによって流れが悪くなり、リンパ浮腫を発症しやすくなり、また改善しにくくなります。
抗がん剤治療による影響
抗がん剤自体の副作用で浮腫が起こることがあり、リンパ節郭清を行っていると、相乗効果としてリンパ浮腫を発症する可能性が高まります。
抗がん剤はそれぞれの薬剤によって副作用が異なりますので、全てに影響があるとはいえません。
一般的には、抗がん剤を使用すると血管に障害が起こる率が高くなり、血流が悪くなることで浮腫を起こす可能性が高まります。
その結果、リンパ液の循環も悪くなってリンパ浮腫を発症される要因になり得ます。
リンパ浮腫の原因になりやすい抗がん剤は、乳がん・子宮がんなどによく使われるパクリタキセル、ドセタキセルといったタキサン系の抗がん剤です。
特にドセタキセルは、浮腫、爪の障害が特徴的な副作用として挙げられます。
この薬剤は、毛細血管から血漿の漏れ出しを増やし、組織間液を過剰に増加させてリンパ浮腫を発症させやすくし、リンパ浮腫の発症率が約2倍になるといわれています。
リンパ浮腫の治療

むくんでるかも・・・と感じた時が、リンパ浮腫に対しての行動を起こす時です。
悪化してから治療を開始しても改善が難しい場合がありますので、できるだけ早期に対処する必要があります。
ではどのような治療を行っていけばよいのか、自分で気を付けておくことは何かを説明していきます。
リンパ浮腫の治療方法
複合的治療といい、がんの治療と同様に複数の治療方法を組み合わせて考えていくのが基本です。
- 圧迫療法:弾性着衣または弾性包帯による圧迫
- 用手的リンパドレナージ:資格を持った専門医療スタッフによるドレナージ
- 運動療法:圧迫下での適切な運動
- スキンケア:普段から自分で行う
- 体調管理などのセルフケア指導
これらをそれぞれの患者さんに合わせて治療を選択していきます。
他にも、手術をして改善を図ることを選択肢として考えられるようになっていますが、完全に治すことはできないため、上記の複合的治療を負担なく行えるために検討されます。
手術の内容は、リンパ管と小さな静脈をつなぐリンパ管細静脈吻合術、リンパ節を移植する血管柄付きリンパ節移植術、浮腫がある個所の脂肪を吸引する脂肪吸引術があります。
薬物療法も、治療を目的として効果が認められている薬はありません。
炎症を抑えたり、利尿を図り水分を減少させたり、症状の改善を目的に使用されることがあります。
治療の保険診療
複合的治療は保険適応となります。
医療者からの指導やドレナージなどの手技は診療として扱われますが、圧迫のための着衣には療養費がかかります。
これらも安いものではないため、一部支給制度が作られています。
療養費には、洗い替えを含めて1回あたり2着まで申請できます。
申請の際は、勤務先・市区町村などの保険者に連絡し、療養費支給申請書、弾性着衣等装着指示書、購入時の領収書を提出します。
支給額の上限を下記に記します。
【弾性着衣】
スリーブ 16,000円/1着
ストッキング 28,000円/1着(片足の場合は25,000円/1着)
グローブ 15,000円/1着
【弾性包帯】
腕 7,000円/1組
脚 14,000円/1組
(支給額の上限を超えた金額)+(支給金額の上限と保険の負担割合から計算した金額)
=負担支払い額
圧迫療法
圧迫療法は、毛細血管からの水分の漏れ出しを抑え、組織間液の回収を促すことで浮腫を改善させます。
ただし、動脈血の流れが悪い場合、深部静脈血栓症がある場合、重症心不全などを併発している場合は、圧迫を行わず、原因が改善されてから圧迫療法を行います。
また、麻痺や知覚障害がある場合も注意して行う必要があります。
正しい着脱法・使用法ができないと、かえって浮腫の悪化を招くため、正しく使用できない人には用いるべきではありません。
圧迫療法には、弾性包帯と弾性着衣を状態に応じて使い分けます。
弾性包帯は多層包帯法といって、複数の包帯を使用して圧を調整するため、自分で行うことは難しいです。その点、弾性着衣は正しい着脱方法を身に付けるだけで、簡単に自宅で行える利点があります。
それぞれ状態によって適切な使用目的がありますので、専門の医療者と相談しながら、自宅で継続しやすい方法を選択します。
用手的リンパドレナージ
手のひら全体を使って強い圧を加え過ぎないように注意しながら皮膚を動かすことで、むくんでいる腕や脚に溜まっている組織間液をリンパ管へ送り込み、正常に機能しているリンパ管へ誘導する治療です。
リラクゼーションや美容を目的としたマッサージやリンパマッサージとは異なり、専門の医療者が行うドレナージのみがリンパ浮腫に有効な治療です。
ご自身で行うリンパドレナージも、Webサイトで見かけるようなものではなく、専門の医療者に方法を教えてもらう必要があります。
運動療法
圧迫療法を行った状態で行う運動を運動療法とよびます。
筋力トレーニングや有酸素運動、腹式呼吸とストレッチを組み合わせて行います。
筋力トレーニングは、ペットボトルなどを持ち腕を伸ばす運動や、両ひざを軽く曲げるスクワットなどが自宅で行いやすいトレーニングになります。
有酸素運動はウォーキング、水泳、サイクリング、軽いエアロビクスなどが勧められています。
スキンケア
リンパ浮腫が生じている部分は、正常な皮膚に比べて感染症にかかりやすく、炎症も悪化しやすい状態にあります。
感染症をさけるためには、皮膚を清潔に保ち、保湿を与えて、外傷から保護することが必要です。
①清潔を保つ
患肢を洗う時は、石鹸やボディーソープの泡を皮膚に乗せて、手で転がすように優しく洗います。
洗った後も擦らないように、押さえるようにして水分を拭き取ります。石鹸や水分が残っていると、細菌が繁殖しやすいので、丁寧に行うようにしましょう。
②保湿をする
正常な皮膚では、免疫機能と水分が体外に蒸発しないように防御するバリア機能が備わっています。リンパ浮腫を発症すると、皮膚が張って薄くなり、さらに感染の働きが不安定になることで乾燥することが多くなります。よって傷つきやすい状況となっているため、しっかりと保湿を行う必要があります。保湿剤は添加物やアルコール成分が含まれない、刺激の少ないものを選ぶ必要がありますので、慣れるまでは医療者の指導のもとで使用するようにしましょう。
③保護する
日常生活でどんなに気を付けていても、傷をつくってしまうことはあります。
虫刺され、けが、日焼け、ムダ毛の処理、爪の切り方などに気を遣ってください。
できるだけ傷をつくらないようにするのは必要ですが、傷ついた場合でも感染しないように、清潔と保湿を心掛けましょう。少しでも悪化する兆候があれば、すぐに受診することをお勧めします。
日常生活での注意点
- 肥満を避ける
- 傷や炎症を避ける
- 持続的な血圧測定は避ける(一般的な測定程度は問題ない)
- 採血ではリンパ浮腫の発症に関連性はないが、抗がん剤や持続点滴を行うのは避ける
- 重いものを持たない指導もあったが、持続的に圧迫する状況でなければ問題ない
- 飛行機の搭乗もリンパ浮腫発症要因とされてきたが、近年関連性はないことが示された
リンパ浮腫の合併症を起こしてしまった場合の対処

どれだけ気を付けて生活していても、リンパ浮腫を発症してしまった状態では、皮膚のバリア機能が落ちてしまう、リンパ液の循環が悪いため免疫機能の低下を起こしており、合併症を引き起こしてしまう可能性があります。
その際にどのような対処をすれば良いのかも知っておくのは良いことでしょう。
蜂窩織炎、丹毒、リンパ管炎
蜂窩織炎とは、小さな傷などから細菌が侵入することで起こる患肢の炎症です。
丹毒は、蜂窩織炎よりも皮膚の表面に近い炎症のことを指します。
リンパ管炎は、リンパ管に沿って炎症が広がっていきます。
それぞれ炎症を起こすと、発赤・腫脹が感染部位周囲に急速に拡がり、熱感・圧痛・自発痛・高熱・倦怠感などの自覚症状が出てきます。
炎症の治療が終了するまでリンパ浮腫の治療は行えません。
抗生物質の投与、冷却、安静といった治療を行うために、状態によっては入院加療が必要です。
リンパ漏
リンパ漏とは、皮膚表面からリンパ液が漏れ出している状態です。
普段は透明またはさらっとした薄い黄色の液体ですが、細菌感染を起こすと、悪臭を伴う粘り気のある黄色になることがあります。
治療は創部を清潔に保ち、保護材やガーゼで浸出液を吸収される必要があります。
治療中もリンパ浮腫に対する治療は並行しますが、悪化すると皮膚潰瘍ができたり、蜂窩織炎の原因にもなるため、早期からの治療が必要となります。
皮膚潰瘍
皮膚潰瘍とは、皮膚の一部に生じる深く広い傷のことです。
リンパ浮腫の部位に皮膚潰瘍ができる原因の多くは外傷です。
傷から漏れ出る浸出液で傷の治りが遅くなり、細菌感染を起こすと浮腫が悪化し、更に浸出液が出てくる悪循環に陥ります。
治療はリンパ浮腫を改善させることを優先します。
潰瘍部分は清潔を保つためにお湯で流す程度にし、潰瘍周辺は泡石鹸で優しく洗います。
そして適切な保護材を用いて、乾燥や過剰な湿潤を避けます。
象皮症
象皮症とは、患肢の皮膚の線維化が進み、皮膚に隆起や変形、イボやかさぶたなどができた状態です。
長期化したリンパ浮腫に、何らかの要因が影響して発症すると考えられています。
象皮症では皮膚が厚くなりますが、乾燥してもろくなっています。
清潔を保ち、尿素系軟膏などの皮膚を柔らかくする軟膏を塗り、角化を改善させます。
併せてリンパ浮腫の治療も行うことで改善が期待できます。
引用・参照
一般社団法人日本がんサポーティブケア学会編集、「JASCCがん支持医療ガイドシリーズ Q&Aで学ぶリンパ浮腫の診療」、医歯薬出版株式会社、2019

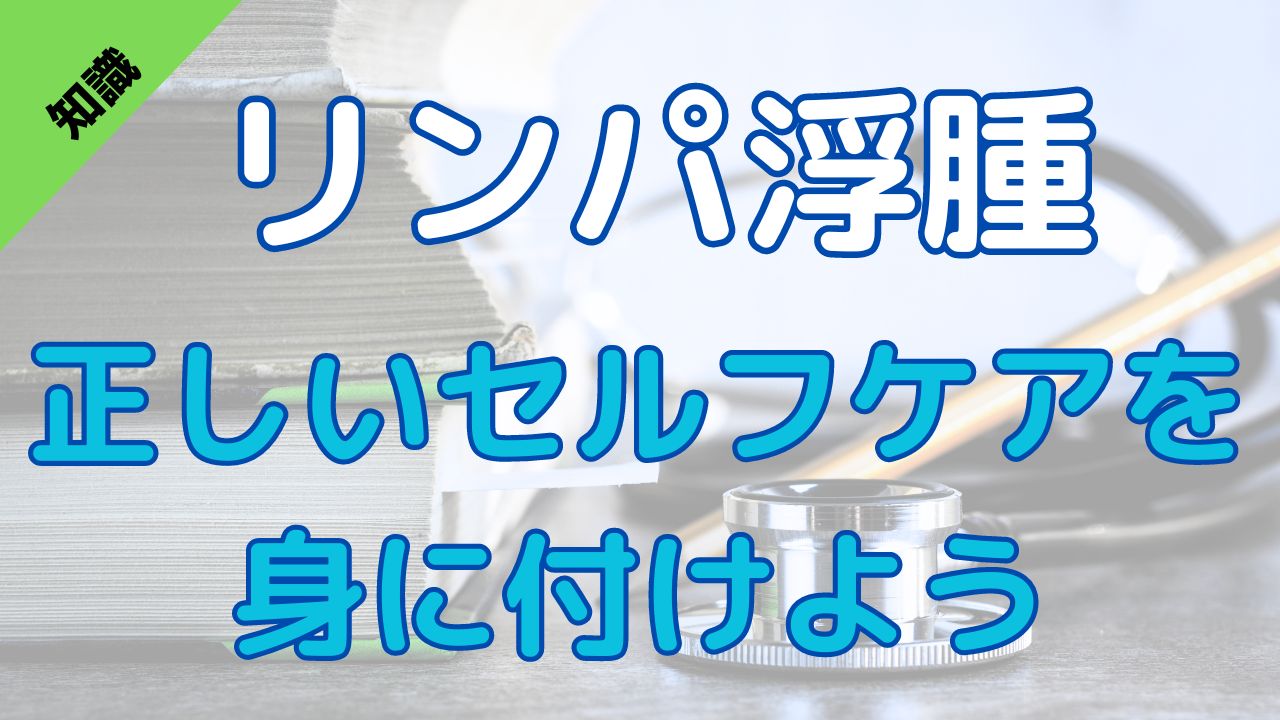


コメント