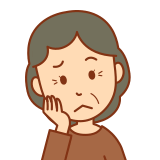
わたしががんだなんて…
これからどうしたらいいのか
何をしないといけないのか
まったく分からないわ…
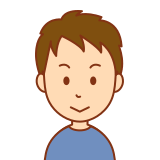
そう思われるのは当然です。
だれもが思いもしないことですから。
おつらいですよね。
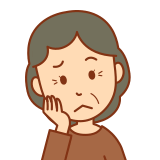
今まで何もなかったの。
思い返せば少し食欲ないなぁって思ってたけど、
忙しかったし、疲れてたのかなぁって思ってて…
もっと早く病院にくれば良かったのかしら…
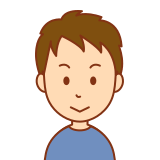
皆さん多少のことでは病院に行こうとは思わないですよ。
これからどうしていくか、一緒に考えていきましょう。
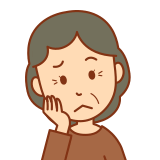
そうですよね。
自分で考えてても良いことないから、
考えてもらえると助かります。
告知をされるとき。
上記のようなケースが多いかと思います。
一般的なケースを取り上げているので、返答は曖昧にしていますが、
医師からの話を一緒に聞いている場合は、もっと具体的な返答をしていきます。
受け止めて、理解しようとして、一緒に考える。
わたしは、このような対応を心掛けています。
皆さんはどのような対応を心掛けていらっしゃいますか?
どうしたらいいか分からない、どうすれば良い言葉かけができたのだろう…
そんな方々へ、関わり方のヒントにして頂ければ幸いです。
患者さんの反応は表面だけでは分からない
「大丈夫」という人
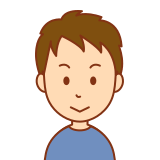
たくさんのお話があったと思いますが、
先生のお話で難しいところなかったですか?
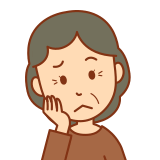
大丈夫…ですよ。
考えてても仕方ないし、先生のおっしゃる通りにしないと。
“「大丈夫」と言いながら、フラフラでいかにも転びそうな人”、
どこにでもいらっしゃる事例かと思います。
このような事例は、普段の看護の現場でも良くある事ですが、
告知時の「大丈夫」には、少し趣きが異なります。
多くの場合、がん告知時には、
一見するとどこが悪いのか分からない元気な方が多いです。
そうなると、上述のような事例には当てはまらないので、
患者さんから「大丈夫」と言われると、
こちらも「大丈夫なら良かった」と思ってしまうのです。
一度立ち止まって、「本当に大丈夫なのだろうか」と、
現状を疑ってみることが必要です。
内面の気持ちを知る
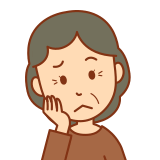
色々言われたけど、何から考えたらいいのかわからないわ。
帰って普通の生活をしてていいのかしら。
こどもたちに何て言えばいいのか。
言われたことも難しいし、そのまま伝えられるかしら。
わたしはこれからどうなっていくのかしら。
表出している言葉や態度とは別に、
告知された患者さんは、たくさんのことを考えています。
わたしたちは、外見では分からない内面の表情を観察する必要があります。
観察できると、不安で緊張のあまり状況を全く理解できていなかったり、
診断のショックで思考停止してしまっていたりする事に気付くことができるはずです。
まずはそんな気持ちに気付く事が第1歩です。
声掛けをする
内面の変化に気づくことができれば、自然に声をかけたいと思うはずですよね。
ですが、そんな時にどう声かけたらいいか分からないという方は多いのではないでしょうか。
声かけに正解はありませんが、単純に「大丈夫ですか?」というだけの声掛けはタブーです。
大丈夫なはずないでしょう、何しにきたん!?と敵意を向けられる事にもなり兼ねません。
だからこそ、どのような声掛けがいいのか、と悩むのだと思います。
声掛けの例
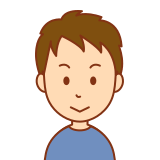
先生のお話、一緒に伺いました。
たくさんの内容があったのですが、難しいところはなかったですか?
わたしが聞いている中では、○○というところが分かりにくかったのではないでしょうか。
何を考えればいいのかと思われるかもしれません。
すぐに答えの出ることではないと思いますが、
わたしたちも一緒に考えますので、お気持ちお聞かせ願えますか?
私の場合は、
①医師からの話の内容を理解できたかを確認すること
②看護師として力になりたい事を伝えること
から始めています。
大抵は「診察で聞けたから大丈夫」となるのですが、
医師の説明の仕方や言葉の使い方によっては、多少の疑問点が残ったりします。
疑問に残るだろうことを予測する
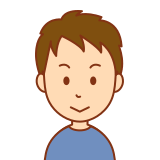
先生、○○って説明してたけど、
ちょっと難しかったんじゃないかな。
患者さんは頷いていたけど無反応だったし、
あとで聞いてみよう。
医療者側からすると簡単な内容だったとしても、
一般の方にとっては難しいことだらけです。
この大前提があることを、頭に置いておかなければなりません。
自分が聞いていて、難しいのではないか、と感じた部分には、
患者さんがどのような態度・表情で話を聞いているかを観察します。
その部分から声掛けを始めると、患者さんも話しやすかったりします。
予測したことを伝える
予測し、観察ができたとしても、伝えなければ確認できません。
こちらから分かりにくいと予測した部分の話や、疑問がありそうな部分を提示すると、
「そういうことだったんですね」と返答があったり、
充分な理解が得られていなかったことは少なくありません。
分かっているようで分からなかったというのが、告知時の心理状態でもあります。
観察したことを素直に確認してみましょう。
きっかけさえ作れば患者さんは話してくれます。
話出すと色々な問題点が明確になると思います。
患者さんの気持ちを真摯に受け止めましょう
「看護師は否定する癖がある」ということを認識する
誰しも、聞いてもらえていないと感じれば、話すのをやめてしまうでしょう。
では、どのような時に「聞いてもらえていない」と感じるのでしょう。
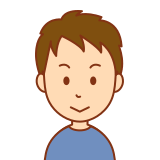
①なすえさん、お薬飲めてなかったので、こちらから渡すようにしますね。
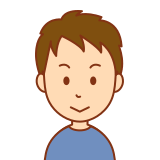
②なすえさん、トイレまで行くときはついていきますから呼んでくださいね。
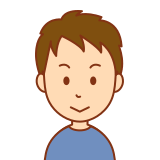
③なすえさん、点滴しているので着替えは手伝います。
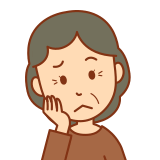
わたしそんなにできてないのかしら…
迷惑かけて申し訳ないわ…
看護師さんの負担にならないようにしないと。
例えば、上記の例は日常でよく使用している声掛けになります。
当然のように使っている言葉掛けですが、患者さん側に立って考えてみましょう。
普段は自立して生活している方が、入院した途端に、過保護にされます。
自尊心を低下させられるし、迷惑をかけると気を遣われる要因になると思いませんか?
上記の例は何が問題になるのかというと、
こちらの要望ばかりで、患者さんが納得できる理由がないので、
「否定」「迷惑」と捉えられる可能性があるのです。
そのなかでも特に注意すべきことは、否定要素のある返答をすると話さなくなります。
当然のように思いますが、
基本的に看護師さんは真面目な方が多いです。
正しい知識を与えたいがために、知らない間に自分が思う以上に否定文を使用しています。
自分が否定的と捉えられる言葉を使用していないか、一度振り返ることが大切です。
良い声掛けの例
①お薬多いと大変ですよね。大事なお薬もたくさんありますので、治療中は間違いのないようにこちらでも確認させていただきたいので、持ってくるようにさせてください。
②歩くの大変そうに見えますが大丈夫ですか?入院環境に慣れるまで一緒に付き添いますので、ナースコールを押してもらってもよろしいですか?治療しにきて怪我でもしたら大変です。
③点滴していると服を通さないといけないので、お一人では引っかかったりして危ないです。こちらでお手伝いさせていただいてよろしいですか?
このように、一度相手の行動を承認し、次に提案し、了承を得るというステップで、
お互いに快く協力を得られるでしょう。
もちろんケースバイケースですので、全てが上手くいくわけではありませんのでご了承ください。
話をした患者さんの気持ち
告知時は、ただでさえ逃げ出したくなるような、つらい状況下にあります。頼れると思い話した人に、否定されたと思ってしまう状況ほど、つらいことはありません。
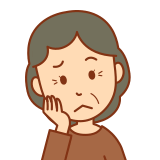
この人なら話聞いてくれると思ったのに…
やっぱり看護師さんは忙しいんだわ。
あんまり私の話に付き合ってもらうのも悪いわよね。
自分で処理できるようにしっかりしないと。
せっかく心を開こうと話し始めてたら、話す気をなくしてしまう…
こんなもったいないことはありません。
患者さんも看護師さんも大きなチャンスを逃してしまっているのです。
「話せる」「聴ける」ということは、お互いの心を通じ合わせる行為です。
これからの入院生活・治療生活に大きなプラスの要因になるはずです。
たとえ患者さんが話された内容が間違っていたとしても、
「それは違います」と返答するのではなく、
「そう考えてしまいますよね。でもこの方が良いと思いますよ」と表現を変えるだけで、
劇的に伝わり方が変わります。
一度意識して声掛けを変えてみましょう。
そのままの感情を受け止める
まずは、患者さんのつらさを受け止める姿勢が重要です。
患者さんが表出する全ての感情を、そのまま受け止めてください。
相槌を打って、そばで聴いているだけで構いません。
他者に話せたという事実が、患者さんの心を救っています。
そこに看護師側の解釈は不要です。
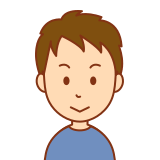
肩が凝って痛いのは病気のせいだとおっしゃってますが、
必ずしもそうとは限りません。
今回の場所的には肩に負担がかかるような場所にはないのです。
という言い方はNGです。
「そう思われるのですね」「そんなことを考えておられたのですね」など、
患者さんの今を理解できるように努めましょう。
そして、そのことを思い詰めないように思考を切り替えるきっかけを提供します。
そうすることで、聴いてもらえた満足感と、異なる考えを持つ余裕ができてきます。
「聴く」ことは「心配している」ことを伝えること
「話を聴きたい」という姿勢を示し、話を聴くことは、
「私はあなたのことを心配しています」という無言のメッセージを届けているのです。
看護師さんからすると、「話を聞いているだけで何もできていない」と感じるかもしれません。
ですが、それは普段から何らかの世話をしている、という状況下から感じる感情と思います。
聴く態度を示すことも、重要な看護ケアであることを知りましょう。
考え方を自分に置き換えてみましょう。
つらいときに色々と情報を与えられたとしたら、
「なんか今日は疲れたな」という感情しか残らないと思いませんか?
「聴く」ことで、患者さんの本当の気持ちを聞けた・引き出せた、という看護ができています。
これは誰にでもできることではありません。
患者さんのことを本当に心配して、何ができるか探した結果、
導き知り得た、患者さんの本当の気持ちなのです。
あなたにしか知り得なかった情報だと思いますよ。
聴いた情報を共有する
せっかく知り得た情報を、自分だけが抱えていては、
次からの患者さんの支援につながりません。
患者さんの治療はここからが始まりです。
今があって、ここを乗り越えて、次があります。
だから重要な情報として、医療者間で共有する必要があります。
これがACP(アドバンス・ケア・プランニング)につながる看護ケアとなり得ます。
最初から多くの情報を伝えないようにしましょう
上述のように声掛けや態度も重要ですが、具体的に観察をし、
アセスメントするには状況把握が必要です。
一般的な反応や陥る状況を知っておくことで、対応できる範囲が広がります。
患者さんは色んな反応をする
告知時というのは、通常とは異なる心理状態であることはわかると思います。
ですが、反応は人それぞれで、
落ち着いた反応をする人、明らかに落ち込んで固まっている人、分かってたと笑う人もいます。
どんな反応をされている人でもショックを受けていることを忘れないでください。
患者さんの心理状態を知る
大きなストレッサーがある状況で、冷静な判断・思考が保てるわけがありません。
実際に、安定して医師の話を聞いていて、
診察後も理解できていることを確認できたとしても、
次に会った時には、前回の内容をすっかり忘れていたり、
思い違いをしていたり、まったく違うことを考えていたりするケースもあります。
通常では考えにくい状態になり得ることを念頭に置かなければなりません。
患者さんの状況を認識する
このような状態ですが、今後も含めて、色んな話を聞かされます。
病院通いに慣れている方なら、多少予測もつくのでしょうが、
ほとんど病院に来ることのない方にとっては、全てが初めてです。
病院に来ていること自体に大きなストレスを感じているはずです。
次にどこに行って検査を受けて、次にどこで話を聞くのか、
そういう順序だけでも手一杯なのです。
当たり前の行動・心理状況であることを、
まず医療者が認識することが重要だと思います。
認識できると、その後の行動も予測でき、
丁寧な説明と配慮を行うことが必要だと、自然に支援することができるでしょう。
必要な情報を整理する
上記のように、患者さんは自分で適切な判断を下せない状況にあります。
現時点で必ず必要な情報はなにか、整理する必要があります。
どれだけ的確に、どれだけ多く持ち帰ってもらうかは、
看護師さんの力量が図られるところでもあり、
その患者さんの次回の状態は、看護ケアの評価の場面であると私は思います。
この時の支援を良いものとするには、どれだけ配慮ができているか、ではないでしょうか。
忙しかったり、自分の精神状態が安定していない場合もありますが、
いつでも配慮ができる看護師で在りたいなと思います。
今回は以上です。
YouTubeで見たい方はこちら↓
気に入っていただけたら、チャンネル登録お願いします!

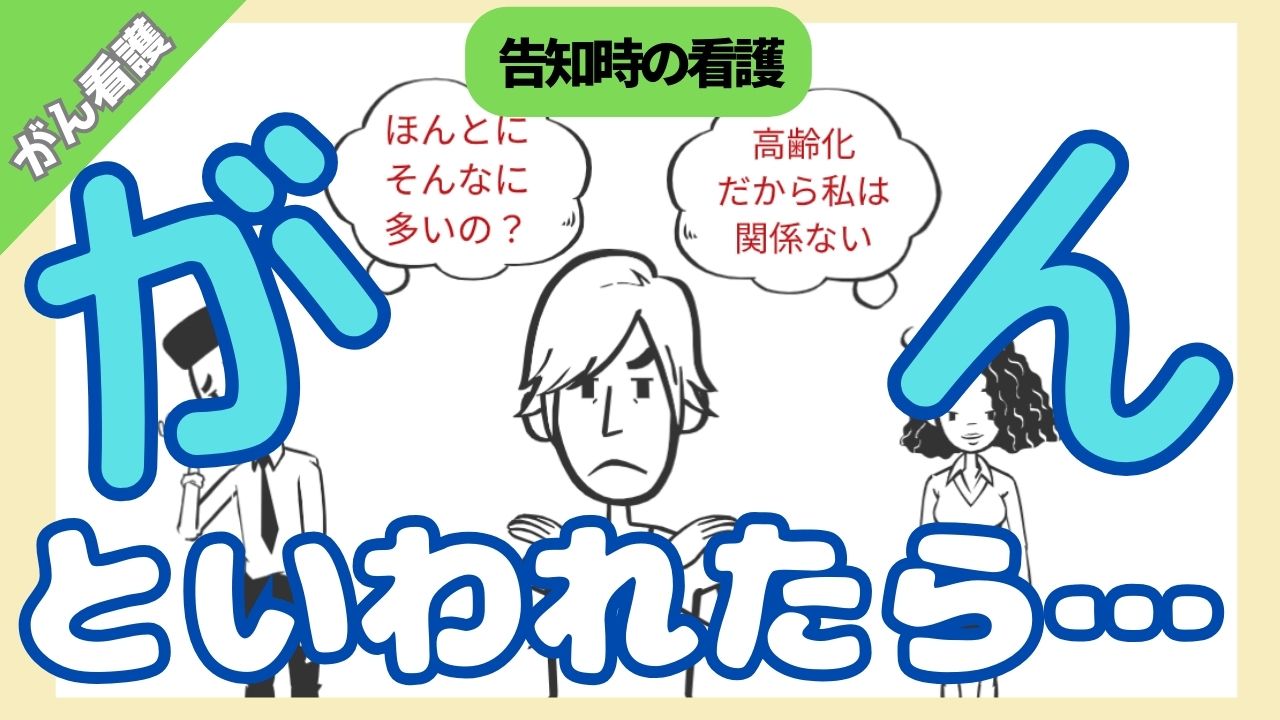


コメント