看護師を経験してから入院をしたことで、多くの学びがありました。
今回のタイトルもその一つです。
「入院時の看護」という項目で、看護学校の授業を受けることはありません。
〇〇病の入院時の症状などと、どのようなことが考えられるかというアセスメント事例として、勉強することがあるくらいだと記憶しています。
入職してからアナムネやクリニカルパスなどの説明・問診を行なっていくので、指導者や本人の性格によって、大きく実施能力が変わってしまうこともあります。
ですので、ほとんどの場合、自分の業務優先に進めてしまっていないでしょうか。
しかもここは、患者サービスに直結する重要な場面であることも実感しました。
これをまとめていきたいと思います。
入院の基本的な流れ(予定入院)

入院の形態としては予定入院と緊急入院があり、今回は予定入院での流れを伝えます。
緊急入院でも大きな流れは一緒なのですが、入院直後から身体に対する治療が最優先される、という大きな違いがあります。
当然のことながら安全性を確保してから、各種手続きを進めていくことになります。
よって初期対応がケースバイケースとなりますので、予定入院を例に、実際の看護現場を見ていきましょう。
入院時に必要なこと
- 総合受付の「入院受付」で手続き
- 入院病棟へ案内
- 入院当日の検査の実施
- 体調確認、問診票や同意書、持参薬などのチェック
- 治療計画書の説明
- せん妄、転倒リスク、栄養状態などのチェック
このような事務手続きが主体となります。
よって多くの場合は、この項目をこなす作業となってしまいます。
ではそれぞれの個別性を持たすためには、どのようなことをすれば良いのかを示していきましょう。
入院手続き
これは事務での仕事になりますが、看護師に繋ぐようにするには、という視点でお伝えします。
①アナムネ(病歴)は、院内統一された様式に沿って、すべての内容が網羅されているか、されていない箇所で事務で聴取できるところは記載し、できないところは看護師が分かるようにマーカーしておく
②病棟での入院生活のルールや配置図などを先に知らせておけるよう、パンフレットに記載するなど工夫する
入院病棟での案内
事務から入院病棟へ案内されます。
そこからは病棟事務が病棟の配置案内などを行い、その後看護師での説明が行われるという流れが一般的です。
配置案内は、トイレ、シャワー室、洗濯機、給湯器、TVカードなどです。
①トイレは、身障者用・オストメイト用も使用可能なことや、便座シートなどの設備も説明する。
②シャワーの使用可能時間と、予約の仕方を伝える。
③洗濯は自己で行えるかレンタル使用か、レンタルなら手続きが済んでいるかも確認する。
④給湯器は施設によって異なる。トースター・レンジなどの備え付けや購買の開店時間も案内しておく。
⑤TVカードは1000円で○分という目安は伝える。
これらを説明しているだけでも、普段どのような生活をされているか、自分で行える範囲はどの程度かを知ることができます。
そこで得られた情報をもとに、個別的な説明を加えていくことが必要なのです。
入院当日の検査の実施
術前や治療前など、採血やレントゲンなどがオーダーされている場合があります。
これらは入院前に情報を得ておくと、スムーズに業務が進みます。
採血がある場合は、点滴が同時に開始されるのか確認しておき、一度で採血と静脈確保ができると、患者への負担が少なくて済みます。
レントゲンなどの外来検査では、病棟へ戻ってくるための経路も説明する必要があるでしょう。
体調確認、問診票や同意書、持参薬などのチェック
バイタルサインの確認は一番に確認する必要があります。
特に近年では新型コロナウイルス感染症が蔓延していますので、入院時に疑いがあると、病棟全ての患者さんへ影響を考えなければなりません。
問診は、病棟案内などの際の会話で聴取することも可能なのですが、上手く話を進めないと、その部分で花咲いてしまって、業務が滞ってしまうことがあります。
できれば一つ一つの項目をこなしていって、聴取する時のために情報を溜めておくと良いでしょう。
持参薬は基本的に薬剤師が確認しますが、看護師に渡されることも多いので、中止薬が内服されていないか、今回の持参はあるかなど、優先事項は聴取しておいた方が良いでしょう。
同意書は外来で手渡しているパターンと、入院後取得されるパターンがあります。
患者さんに聞かないと分からないことも多いので、どのような書類をもらったか、自分の目で確認させてもらう方が確実です。
治療計画書の説明
入院すると、その入院目的と治療内容の概要を文書で説明する必要があります。
その書式は施設によって異なりますが、疾患名、治療内容、入院期間、各種検査や栄養管理の必要性、療養支援内容、各担当者名などが記載されています。
これがクリニカルパスであると、一般的なスケジュールを表にまとめていますので、説明する側もされる側も理解しやすい特徴があります。
入院当日に何をするのか、手術の時間は何時か、術当日の流れ、術後の経過などが、行動レベルで細かく記載されています。
クリニカルパスを充実させると、業務効率が上がるだけでなく、患者満足度も上がります。
せん妄、転倒リスク、栄養状態などのチェック
こちらも診療報酬に関わる部分なので、それぞれ入院時とその後の経過でチェックしていく必要があります。
それぞれ施設に沿ったチェック項目があるので、聴取しなければ分からない項目か、カルテの情報でチェックできるのかを把握しておきましょう。
患者側の不安
入院時での患者側の不安を列挙しておきます。
これを念頭に置いて説明ができると、患者は安心して入院できること、看護師側からも患者の状況を把握しやすく早期対応が行いやすくなるメリットがあります。
- 手術や検査時間は何時からか。未定の場合はどのように対応してもらえるか
- 家族の待機は何時からか。待機場所と当日に対話する時間があるか
- 術後、シャワーやトイレはどのように行うか
- 痛みや苦痛に対してどのように対応してもらえるか
特に伝えやすいのが、「何かあればナースコールを押してください」という言葉です。
基本的に患者さんはコールに気を遣います。
自立している方でトイレ介助などがあれば尚更です。
なぜコールして欲しいのか、看護師がラウンドする時間はいつ頃か、などを伝えておくと、お互いの気遣いが少なく済むのではないでしょうか。
私が普段使っている例を紹介しましょう。
「困った時やご用事があれば、遠慮なくナースコールを押してください。トイレなど気を遣われるかもしれませんが、お見かけする限りお一人では足元に不安を感じます。慣れないトイレを使うことで怪我されては元も子もありません。余計な治療を増やさないためにも遠慮なさらないでください。基本的には日勤・夜勤・早朝と3回は訪室しますが、それ以外でご用命の場合もコールしていただけると助かります」
まとめ
看護師側が行う業務内で、どのようなことに注意する必要があるのか、患者側の不安はどのようなものがあるのか、お分かりいただけたでしょうか。
これらのことを念頭に置くと、患者のニーズに的確に応えられるだけでなく、看護師側としても、スムーズな説明を行え、理解も得られやすい状況が作りやすいと思います。
お互いに初対面の状況からなので、お互いに丁寧な対応を心がけていけば、自然と配慮ある行動がとれ、お互いに気持ちよく安心して、入院生活を送ることができるでしょう。

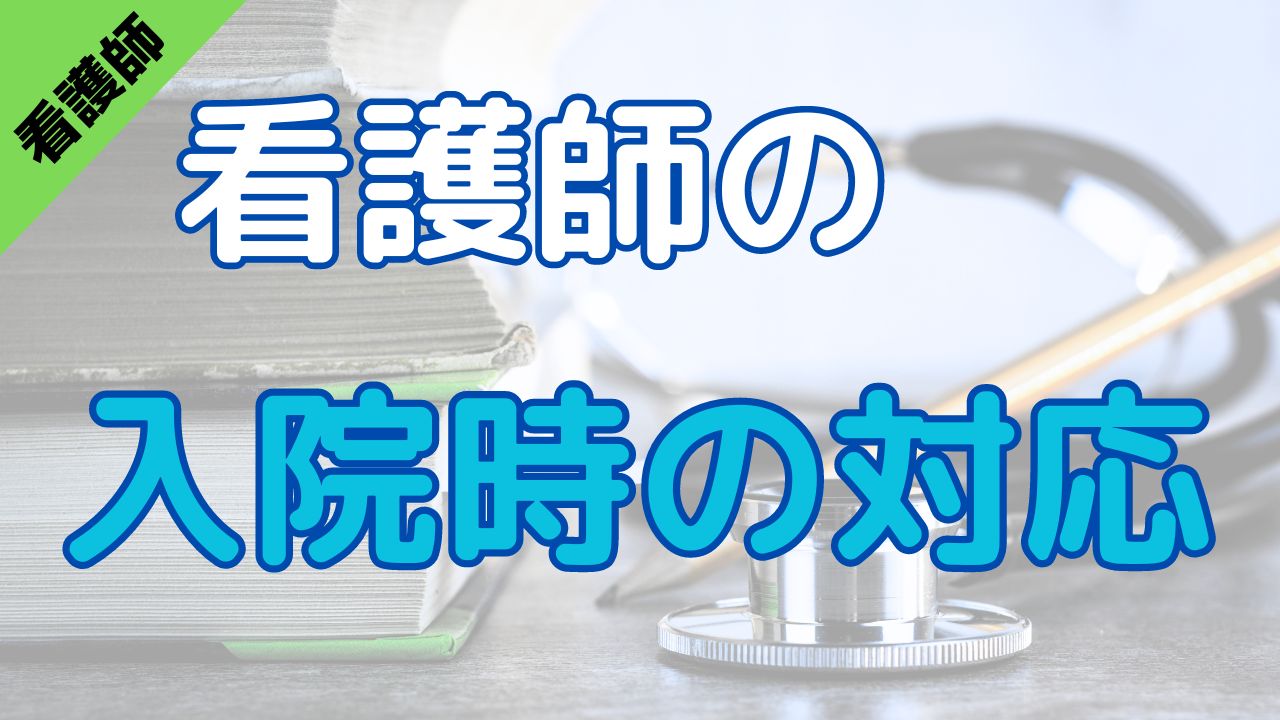


コメント