がんになって一番心配される苦痛症状は痛みです。
痛みは生活の質の低下に直結し、体動困難、意欲の低下を招きます。
その痛みに対しては様々な薬剤が開発され、適切に使用することで、
ほとんどの痛みをコントロールすることができるようになってきています。
多くの薬があるので、段階的にまとめていきましょう。
痛みの評価
まずは適切な評価が必要になってきます。
臨床でよく使用される評価方法は、Numerical Rating Scale(NRS)です。
「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」では、
NRS1~3を軽度、4~6を中等度、7~10を高度と定義されています。
NRSは患者の主観的な評価のため、訴えだけで評価するのではなく、
日常生活への影響なども含めて総合的に評価する必要があります。
特に指標とするのは、睡眠中に痛みで覚醒することがあるかどうかです。
覚醒するほどの痛みがある場合は、中等度~高度の疼痛があると評価できるでしょう。
軽度の痛みに対する対応
「軽度の痛み」としても、痛みの原因・種類を聴取する必要があります。
侵害受容性疼痛であると判断できる場合、第一選択薬は非ステロイド消炎鎮痛薬となります。
がんに使用される非オピオイド鎮痛薬の種類と作用機序
- NSAIDs
- アセトアミノフェン
NSAIDs
抗炎症作用があり、侵害受容性疼痛に効果的です。
①組織の損傷や炎症によって、ブラジキニンなどの発痛物質が遊離される。
②末梢神経の痛み受容体(侵害受容器)に結合して、その刺激が大脳に伝達することで、痛みとして認識される。
③①,②と同時に、損傷部位から発生するシクロオキシゲナーゼ(COX)が発生。
④アラキドン酸からプロスタグランジン(PG)が産生され、発痛物質の作用を増強させたり、炎症を促したりする。
アラキドン酸カスケードは、NSAIDsの作用機序や副作用の理解に重要です。
細胞膜リン脂質から合成されたアラキドン酸は、主に3つの経路で代謝されます。
第一の経路は、COXによりプロスタグランジンやトロンボキサンなどを合成するCOX経路、
第二は、リポキシゲナーゼによりロイコトリエンやリポキサンなどを合成するリポキシゲナーゼ経路、
第三は、チトクロームP450(CYP)によりエポキシエイコサトリエン酸などを合成するCYP経路です。
COXには、COX-1とCOX-2の2つのサブタイプがあります。
COX-1は血小板、消化管、腎臓などに常時発現しており、臓器の恒常性維持に必要です。
COX-2は炎症などで誘導され、血管拡張作用などを有し炎症を促進するPGE2などを合成します。
NSAIDsはCOXを阻害することで各種PGの産生を抑制し、抗炎症作用、鎮痛作用を発現します。
また発熱時には、視床下部にある体温調整中枢でのPGの産生を阻害することで解熱作用を得られます。
一方、神経障害性疼痛はPGを介さない痛みの伝達なので、NSAIDsは効果が薄くなります。
アセトアミノフェンとの使い分けを下記に示します。
| NSAIDs | アセトアミノフェン | |
|---|---|---|
| 作用機序 | 末梢のCOX阻害作用 | 中枢性作用 |
| 消化管障害患者 | 使用を避ける(COX-2選択的阻害薬ではリスクが低くなる) | 使用できる |
| 腎機能障害患者 | 使用を避ける | 使用できる |
| 肝機能障害患者 | 肝機能に注意しながら使用する | 重篤な肝障害患者には使用を避ける |
| アスピリン不耐症・ アスピリン喘息患者 | 使用を避ける(COX-2選択的阻害薬ではリスクが低くなる) | リスクは低い ただし低用量から慎重に開始 |
| 血小板機能障害患者 | 重篤な血液障害がある場合は使用を避ける(COX-2選択的阻害薬ではリスクが低くなる) | 影響は小さいので使用可能 |
COXには、COX-1とCOX-2という2つのアイソザイムがあります。
アイソザイムとは、ほぼ同じ活性を持っているがアミノ酸配列が異なる酵素のことです。
COX-1は恒常的に発現していて、胃粘膜保護や腎血流の増加、血小板凝集といった生理的な役割を担うプロスタグランジンやトロンボキサンを産生しています。
COX-2は炎症組織において発現が誘導されます。
NSAIDsはCOX-2阻害作用の結果、組織損傷部位のプロスタグランジン産生を低下させて鎮痛作用を発揮させます。
同時にCOX-1阻害によってプロスタグランジン、トロンボキサンを抑制することで引き起こされる作用の一部は副作用となります。
アセトアミノフェン
アセトアミノフェンの作用機序は、代謝物が中枢に作用していると考えられていますが、まだ明らかにはなっていないようです。現在考えられている機序は、中枢性COX阻害に加えてカンナビノイド受容体やセロトニンを介した下行性抑制系の賦活化です。痛みのシグナルは末梢神経終末→脊髄→脳へと上行性に伝達されますが、逆に中枢側である脳から脊髄へと下行性に痛みを抑制するシグナルを伝達する経路があります。この経路のことを下行性抑制系と呼びます。アセトアミノフェンはこの下行性抑制系を活性化することで鎮痛効果をもたらすと推定されています。
中枢性の解熱・鎮痛作用がありますが、抗炎症作用は弱いので、投与量が少ないと効果が得られないことが注意点として挙げられます。
NSAIDsと比較して、消化管障害、腎機能障害、血小板機能障害は少ないですが、重篤な肝機能障害がある患者では、アセトアミノフェン特有の中毒性肝障害を起こすため投与を避けます。
1回の服用で150~250mg/Kgを超えると肝細胞壊死が起こり、成分量300~400mg/Kgでは致命的になるといわれていて、一般的な使用量では可能性は低いのですが、アルコール常飲者や低栄養状態ではリスクが高まるので注意が必要です。
NSAIDsとアセトアミノフェンの使い分け
前述の通りNSAIDsでは消化管障害、腎機能障害、血小板機能障害が起こるため使用に制限があるのに対して、アセトアミノフェンは重篤な肝障害以外には使用しやすくなりますが、有効量に達するまで投与量が多くなりがちなので注意が必要です。
また、アスピリン不耐症・アスピリン喘息のリスクがある患者の場合は、NSAIDs使用で血管浮腫、全身性蕁麻疹、気管支喘息、咽頭浮腫、ショックなどの症状を来す場合があるので使用を避けます。
使用しやすいアセトアミノフェンですが、抗炎症作用がほとんどないので、がんに対する疼痛緩和には効果が乏しいことが多いです。
特に炎症が強い骨転移、皮膚転移、がんの軟部組織浸潤などの痛みに対しては、NSAIDsの方が有効であることが多く、アセトアミノフェンはNSAIDsで緩和しきれない痛みに対し、併用して相加効果を期待されます。
【引用・参考】
岡本禎晃、荒井幸子編:「基本的知識と症例から学ぶ がん緩和ケアの薬の使い方」、じほう、2019
日本ペインクリニック学会 (jspc.gr.jp)

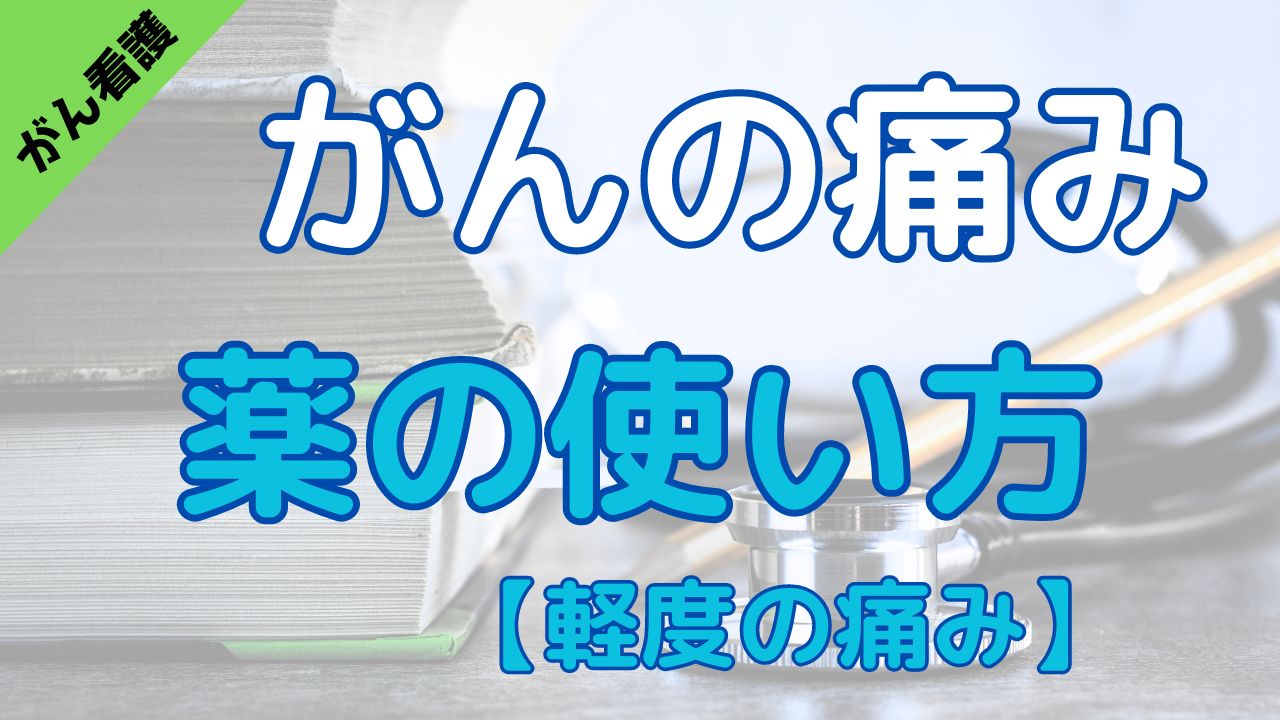


コメント