がんの治療は、手術できることが第一目標です。
よって、手術を繰り返す患者さんも少なくありません。
またどのような手術を行っているのかを知ることで、より深く患者さんの病態を知ることができます。
病態が分かると今後出現する症状の予測ができ、予防や生活上の注意点のアドバイスが可能です。
看護師として患者さんにできることが増えますので、必要な知識の一つです。
術後の身体には様々な付属物がついてきます。
それぞれに不要なものは一切なく、全てのものに目的があります。
その中の一つにドレーンがあります。
特にドレーンは色々な種類があり、観察する項目も押さえなければならないポイントがあります。
これも実際に臨床で見ないと想像できない知識になりますので、
まずは、基本的な知識をみていきましょう。
ドレーンの基礎知識
体内に貯留した血液、膿、浸出液、消化液、分泌液などを体腔外へ誘導し、排泄させるために挿入することをドレナージといいます。
このドレナージを行うために使用する医療材料をドレーンといいます。
ドレーンの種類
様々な形態のドレーンがあります。
ドレーンは目的、形状、原理などによって分類されます。
目的による分類
- インフォメーション(情報)ドレーン
手術によって異常な状態になった場合に、状況を知るサインとするために留置します。
出血、消化液漏出、感染などを知ることができます。 - 予防的ドレーン
手術によって血液、浸出液、消化液などの貯留が予想される場合に、あらかじめ腹腔内や胸腔内などに挿入します。浸出液が貯留することによって感染・臓器障害を引き起こさないよう予防することが目的です。 - 治療的ドレーン
病態によって体内に貯留した血腫・消化液・膿・壊死組織などを排出・洗浄するために留置します。
形状による分類
- フィルム型ドレーン(ペンローズ型)
シリコン製で柔らかく、患者への負担は軽くなります。
毛細管現象を利用するといわれていますが、必ずしもそうではありません。
粘稠性の低い液体をドレナージするもので、開放式で使用されます。
圧迫によって内腔がつぶれたり、粘稠な液体で閉塞する欠点があります。 - チューブ型ドレーン(チューブル型、プリーツ型、単孔型、平型)
粘稠性の高い液体も排出でき、閉鎖式で用いると逆行性感染が少なくなります。
凝血塊や壊死組織も排出するため、胸腔内、腹腔内に用いられます。 - サンプ型ドレーン(2腔型、3腔型)
治療的ドレーンとして使用でき、洗浄用にも利用されます。
排液量の多い時や、血性の高い排液にも適しています。 - スリット型(ブレイク型)ドレーン(ラウンド型、フラット型)
内腔がなく接触面が大きいため、広範囲のドレナージが可能となります。
閉鎖的・能動的ドレナージに使用されることが多いです。
ドレナージ原理による分類
- 開放式ドレーン
ペンローズドレーンなどを用い、滅菌ガーゼで覆います。
ドレナージの効率は良いが、逆行性感染の危険性は高くなります。 - 半閉鎖式ドレーン
開放式ドレーンをパウチで覆います。
排液量が多量の場合は有効です。 - 閉鎖式ドレーン
排液バッグに接続するため、逆行性感染の危険性が少なく排液量を正確に測定できます。
患者が動きにくく、体動時の逸脱に注意が必要となります。
管内が液体で満たされている状態をつくると、自然と液体が流れていく仕組みのこと。
貯留している水位と、管の出口に高低差があると、高い方から低い方へ流れ出ていきます。
細い管の内側を液体が昇っていく現象のこと。
管が細いほど液体が軽くなり、より高くまで昇っていきます。
ドレーン挿入部の陰圧を保つために、液体で空気の逆流を防ぐこと。
滅菌蒸留水が規定量より少ない場合、胸腔に空気が逆流して肺が圧迫されてしまいます。
水封部液面の上下の動きは、呼吸性移動があることでドレーンが有効である証明となります。
ドレーン観察のポイント
実際に見てみないと分からないことは多いのですが、観察ポイントは覚えておいた方が良いでしょう。
臨床に出てすぐに覚えられるところではありますが、ドレーンに限らず、治療によって身体に付属するものの観察は、全て同じようなところに注意を払っておけばよいことを知っておきましょう。
- ドレーンの名称・目的・挿入位置を確認する
各種ドレーンがどこに挿入されているか、分かるように示しておく
仰臥位ではモリソン窩、ダグラス窩に貯まりやすいことを覚えておく - 排液の色・性状・量の観察
淡血性~漿液性、血性、混濁、浮遊物の評価を行う
臭いは、便臭があると下部消化管の損傷・縫合不全、アンモニア臭があると尿管損傷があると考えられる
量は急激な増減がないかを確認する - 効果的に排液されているか確認する
挿入部から確認していき、ねじれや引っ張られたりしていないか、屈曲や体の下敷きになっていないか、排液バッグの位置が問題ないか、順番に確認していく - 固定方法が適切か確認する
固定が剥がれていないか、抜けにくく固定されているか、基本的には2か所以上でループを作って止めてあるか確認する - 皮膚の状態を確認する
水疱・発赤などがないか、浸出液で汚染されていないかなどを確認する - 感染対策ができているかを確認する
挿入部の清潔が保てているか、外部からの汚染の危険性がないかを確認する - 患者指導ができているか確認する
離床や体位変換で引っ張られないように注意できているか、安静時に屈曲予防行動を取れているかなど、説明を理解されているかを確認していく
【参考・引用】
清水順三、曽根光子著:「はじめてのシリーズ はじめてのドレーン管理」、メディカ出版、2010
永井秀雄、中村美鈴編集:「臨床に活かせるドレーン&チューブ管理マニュアル」、学研メディカル秀潤社、2011

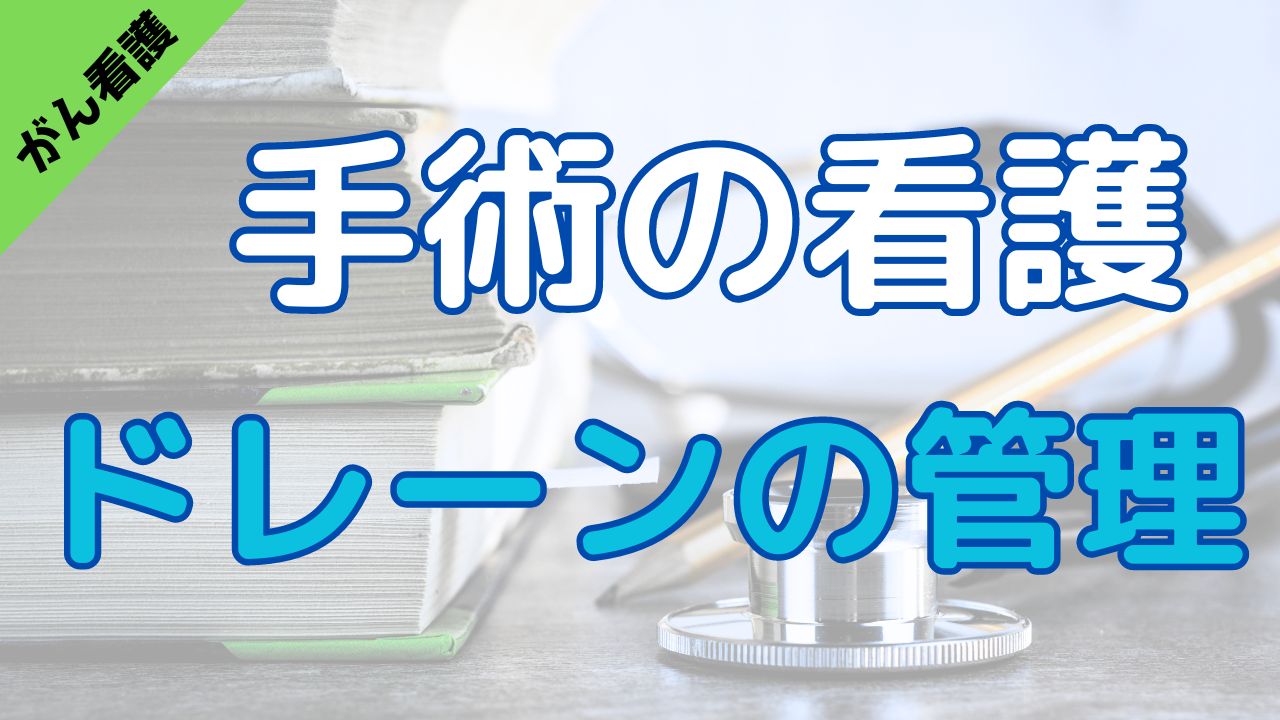


コメント