「がんになると痛みが強い」と考える人は多いでしょう。
がんの痛みは、がんの場所や病状によって大きく異なります。
ですが、痛みの原因を調べることで、適切な薬を選択でき、疼痛緩和が可能となります。
痛みで苦しんでいる人を見ると、「何とかしてあげたい」と思うのではないでしょうか。
そこには痛みをアセスメントできる力が必要になります。
痛みの原因を一番早くアセスメントできるのは、実は看護師なのです。
看護師は患者さんの日常生活に焦点を当てて、ケア・プランを作成しています。
どのような種類の痛みか、どんな時に痛むか、どの程度痛むか。
このような聴取ができるコミュニケーションスキルが大事なのです。
看護師が知識を持つことで、早急に正確な診断の手助けとなります。
そこで、基本的な考え方を見ていきましょう。
痛みの概念
国際疼痛学会は、痛みを「実際の組織損傷、あるいは組織損傷の可能性、またはそのような障害の際に表現される不快な感覚および情動体験」と定義しています。
痛みは主観的なもので、第三者が客観的に評価できないことを認識しておかなければなりません。
よって、痛みの原因と種類を適切な評価方法で、速やかにアプローチすることが必要です。
ここで、看護師のコミュニケーションスキルが問われる場面となります。
痛み刺激の病態生理
【Aδ繊維】
針で刺したような鋭い刺激を伝達(伝達速度が速い) ⇒体制痛、神経障害性疼痛
【C繊維】
どこが痛むのかはっきりしない鈍い刺激を伝達(伝達速度が遅い) ⇒内臓痛
この2種類の一次ニューロンから侵害受容器へ伝達され、脊髄後角へ伝えられます。
すると、痛覚情報伝達物質であるグルタミン酸やサブスタンスPが遊離されます。
これらが脊髄を通り、視床を介して大脳皮質へ伝達されることで痛覚を生じます。
また、脊髄網様体路を通り、脳幹を介して大脳辺縁系へ到達すると、
情動(不快な感情)を引き起こして、痛みを不快で苦痛なものと認識するようになるといわれています。
痛みの3つの分類
痛みの種類を理解すると、どこに問題があるのか見当をつけて観察することができます。
その痛みに適切な薬剤を使用しているか、どの程度コントロールできているかを
アセスメントすることで、患者さんの苦痛を早期に緩和することに役立ちます。
まずは、ここを覚えておきましょう。
痛みは、侵害受容性疼痛(体性痛・内臓痛)と神経障害性疼痛に分けられます。
がんによる痛みの場合、体性痛、神経障害性疼痛、内臓痛の順に多く、
これらの病態が混在していることが多いのです。
また、関連痛も存在します。これは、病巣周囲や離れた場所に起こる痛みのことです。
関連痛は、内臓の刺激を入力する脊髄レベルに刺激が伝わって起こる、
皮膚の感覚異常や痛み、または筋肉の収縮や痛みが起こることで発生します。
他にも、骨転移や脊椎転移がある場合、椎体症候群といわれる関連痛も起こりやすいといわれます。
疼痛部位とその種類を把握するためには、デルマトームやヴィセロトーム、オステオトームといった、神経伝達部位の理解が必要です。
体性痛
体性痛とは、皮膚や骨、関節、筋肉、結合組織といった体性組織への機械的刺激(切る、刺す、破壊する・される、重力がかかる、など)が原因で発生する痛みのことです。
術後早期の創部痛、筋膜や筋骨格の炎症や損傷、けいれんに伴う痛み、
がんの場合には腫瘍の浸潤によるものなどがあり、組織への損傷が原因となります。
多くの場合は、痛みが損傷部位に限定していて、圧痛があります。
また、持続する痛みに加えて、体動や荷重に伴って痛みが増強することや、
短時間で悪化する拍動性の痛み、うずくような痛み、などがあります。
体性痛に対する薬
基本的にはNSAIDsやアセトアミノフェン、オピオイドが選択されます。
必要に応じて鎮痛補助薬を使用しながらコントロールしていきます。
一過性の強い痛みがたびたび出ることがあるので、使用するレスキュー薬を決めておきます。
骨転移痛に対しては、ビスホスホネート製剤やデノスマブを使用していきます。
内臓痛
内臓は、体性刺激とは違い、切る、刺すなどの刺激では痛みを感じません。
①食道、胃、小腸、大腸、胆嚢、胆管、尿路、膀胱などの管腔臓器は、炎症や狭窄・閉塞による内圧が上昇して起こる痛み
②肝臓、腎臓などの実質臓器では、周囲の被膜への炎症による痛み、臓器腫大による伸展の痛み
③膵臓は、周囲の神経叢への炎症や、腫瘍浸潤による痛み
④腸間膜、腹膜、胸膜は、炎症や腫瘍浸潤、伸展が生じた場合の痛み
内臓痛はC繊維を介すること、
また、一次ニューロンから複数の脊髄レベルに分散されるため、関連痛も発現します。
これらのことから、体性痛に比べて痛みの場所が不明瞭になることが多いです。
内臓痛に対する薬
痛みの種類が複数あるため、それぞれの痛みに対して適切な薬物を使用することが求められます。
腫瘍浸潤などで、消化管に狭窄・閉塞を生じる場合は、消化管分泌量の減少や消化管蠕動運動低下を期待して、鎮痛目的でオクトレオチドやブチルスコポラミンなどを使用することもあります。
また、腫瘍により臓器被膜や管腔臓器に炎症が起こり、浮腫が出た場合、コルチコステロイドを使用することもあります。
神経障害性疼痛
体性感覚神経系の病変や疾患によって引き起こされる痛みと定義されます。
痛覚を支配する神経の損傷や、その神経の疾患による痛みです。
がん患者の場合は、腫瘍の増大による末梢神経や脊髄神経、脳、軟髄膜の圧迫、巻き込みなどが起こると、神経障害性疼痛が発現します。
また、腫瘍周囲の体性組織や内臓にも浸潤して、侵害受容性疼痛が混在していることも多いです。
さらに腫瘍が進展・浸潤していくと痛みの病態が変化しやすいため、診断が難しい特徴があります。
他にも、手術療法、化学療法、放射線療法の治療によって生じることもあります。
神経障害性の痛みは、損傷神経の支配領域によってさまざまな部位に生じ、感覚障害や運動障害、自律神経系の異常(発汗異常、皮膚色調の変化)などが起こる場合もありますが、通常は痛覚過敏やしびれ感などの感覚異常が起こります。
起因する事象がなくても、「刺すような」「焼けるような」「槍で突き抜かれるような」「ビーンと電気が走るような」などと表現される痛みがあったり、通常では痛みを感じない刺激で痛みを感じるアロディニアが生じることもあります。
神経障害性疼痛に対する薬
非オピオイド鎮痛薬、オピオイドを基本に使用し、効果が乏しい場合は鎮痛補助薬を検討します。
投与薬剤の例は、第一選択薬がプレガバリン、ガバペンチン、デュロキセチン、アミトリプチン、ノルトリプチリン、第二選択薬は、ノイロトロピン、トラマドール、第三選択薬はフェンタニル・モルヒネ・オキシコドン・ブプレノルフィンなどです。
がんによる痛みの症候群
症候群とは、いくつかの症状が同時に起こる状況をまとめて説明する言葉です。
このような場合には、このような症状が起こり得ます、といったパターンを知ることで、
状況の判断に役立ち、予測した行動がとれるようになります。
骨転移症候群
肺がん、乳がん、前立腺がんの順に発生頻度が高くなります。
骨転移の好発部位としては、脊椎、胸椎、腰仙椎、頚椎の順に発生頻度が高くなります。
| 腫瘍の部位 | 痛みの特徴 | 随伴症状・その他 |
|---|---|---|
| 頚椎 | 後頚部の痛み 頭頂部に放散する痛み 肩や上肢に放散する痛み ピリピリした痛み | 運動による痛みの悪化 上肢の進行性の感覚・運動機能障害 |
| 腰椎 | 腰部正中の痛み 仙腸痛、鼠径部痛 下肢に放散する痛み ピリピリした痛み | 運動や体重のかかる体勢で痛みが悪化 上肢の進行性の感覚・運動機能障害 |
| 仙骨 | 腰部正中の痛み 臀部や下肢に放散する痛み ピリピリした痛み | 肛門周囲や下肢の感覚・運動機能障害 膀胱・直腸障害 |
| 硬膜外脊髄圧迫 | 背部痛 障害脊髄レベルの締め付ける痛み 障害脊髄レベル以下のピリピリした痛み | 進行性対麻痺、感覚障害 膀胱・直腸障害 圧迫が強いと非常に強い痛み |
内臓痛症候群
内臓痛は様々な症状が発現する可能性があるため、症候群としてまとめられています。
主な内臓痛症候群を下記に示します。
| 症候群名 | 原因 | 痛みの特徴 |
|---|---|---|
| 肝拡張 症候群 | 肝被膜の急激な伸展 圧迫による胆管、血管内圧上昇 | 右季肋部痛 側腹部痛 背部痛 右頚部、肩、肩甲背部の関連痛 |
| 正中後腹膜 症候群 | 膵臓がん、後腹膜、 腹腔リンパ節転移 膵・胆管などの脈管閉塞 腹腔神経叢浸潤 | 上腹部・背部の局在不明瞭の鈍痛 仰臥位で憎悪、座位で改善 |
| がん性 腹膜炎 | 腹部・骨盤腫瘍の体腔への 拡がり 腹膜の炎症、腹水 腸間膜の癒着 | 腹部膨満感を伴う痛み 腸閉塞に伴う間欠的疝痛 |
| 悪性会陰部痛 | 大腸・直腸、泌尿器生殖器系 のがんの骨盤底浸潤 深部筋層への浸潤 | うずくような持続痛が座位や立位で増強 テネスムス 膀胱攣縮に伴う頻尿を伴うことがある |
| 尿管閉塞 | 小骨盤、後腹膜内の腫瘍 リンパ節の圧迫や浸潤 | 側腹部の鈍痛 鼠径部・性器に関連痛 腎盂腎炎併発で下腹部・排尿時痛 |
| 卵巣がんに 伴う痛み | 卵巣がんの浸潤、転移 | 中等度以上の下腹部・臀部痛 痛みのみが再発の唯一の兆候のことがある |
| 肺がんに 伴う痛み | 肺がんの浸潤、転移 | 上葉のがんは肩に、下葉のがんは下腹部に関連痛を起こす 副腎転移を起こしやすく、側腹部痛の原因になる |
術後痛症候群
乳がん切除後疼痛症候群
乳房手術、とくに腋窩郭清を伴うと、肋間上腕神経を傷つけてしまうことがあります。
上腕内側や腋窩、前胸部などに、締め付けられるような、灼けるような、ぴりぴりするような持続痛や知覚異常、アロディニア、トリガーポイントがみられることが多くあります。
手術直後~半年までに発症することが多く、慢性痛・難治性に移行する場合もあります。
広範囲頚部切除後疼痛
リンパ節郭清を伴う広範囲の頚部手術で、頚部の神経叢や副神経などの神経障害、筋群除去に伴う骨格筋の不均等で疼痛を発現することが多くあります。
頚部の締めつけ感を伴う持続痛や電撃痛、感覚鈍麻や感覚異常、アロディニア、トリガーポイントを認めることも多いです。
副神経損傷に伴う肩の痛みを認めることがあります。
開胸術後痛
開胸手術、特に肋間を拡げる手術をした場合、肋間神経の牽引や断裂、肋間筋の損傷、開胸部の慢性の炎症があったりして、疼痛が発現します。
切開創の部分や損傷を受けた肋間神経の走行に沿って、電撃痛や締めつけ感、うずくような灼熱感、アロディニア、感覚鈍麻や感覚異常を感じるようになります。
化学療法誘発性末梢神経障害性疼痛
薬剤の種類や投与量によっても大きく異なります。
特に糖尿病や既存の末梢神経障害がある場合は、症状が強く出る傾向にあります。
感覚障害が主な症状ですが、薬剤によっては運動障害、自律神経障害が出ることもあり、薬剤の調整や用量変更が必要になることがあります。
放射線照射後疼痛症候群
放射線照射による末梢神経周囲の微小循環障害や組織の繊維化、脊髄の白質、灰白質の壊死や脱髄の結果として末梢・中枢神経の障害が痛みの原因となります。
この痛みは、治療関連の晩期症状で、月~年単位で発生・進行することがあります。
【引用・参考】
日本緩和医療学会ガイドライン(がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン2020年版)
ガイドライン | 日本緩和医療学会 – Japanese Society for Palliative Medicine (jspm.ne.jp)
日本ペインクリニック学会 (jspc.gr.jp)

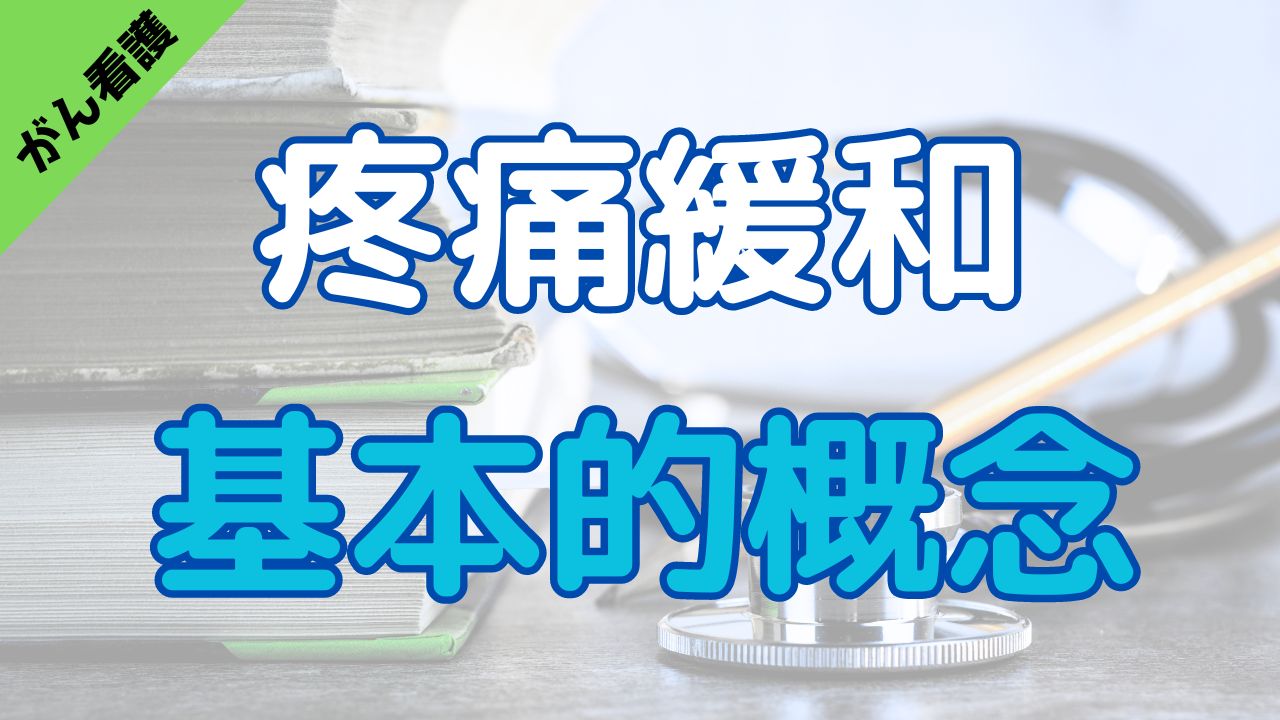


コメント