薬事法では、「口に入るすべてのものは医薬品と食品に分類される」とされています。
医薬品の中にも、処方箋でもらう医療用医薬品と、ドラッグストアで購入できる一般用医薬品があります。
その中で、健康食品というのは薬ではありません。
ですので、何かを補うために積極的に摂取したとしても、効果を保証するものではありません。
ただし、普通の食事よりも効率的に目的のものを摂取でき、使い方によっては、効率の良い補助食品であるともいえます。
ですが前提として、食事からの栄養摂取に優るものもはないことを覚えておいてください。
注意すべきは、病気の治療中であったり、過剰摂取になってしまったりすることで、害を及ぼすことがあるので注意が必要です。
特にがんの治療中に、「がんに効果があると聞いた」と言ってさまざまな健康食品を試される方も多くいらっしゃいます。
たまたまその方にあった対処法であった、という例がなくもないのですが、期待できるほどの効果を得られるかの保証ができません。
また高価なものも多く、私個人の意見としては、試せる程度の金額であれば止めることはありませんが、効果の保証ができないことと、治療に影響するような成分が混入されていないかを薬剤師に調べてもらう必要があることをお伝えしています。
今回はそのような商品を紹介することではないのですが、簡単に手に入る健康食品だからこそ、基礎的な知識を身につけておき、適切なセルフコントロールを身につけて頂きたいので記載していきます。
健康食品とは

健康食品という言葉は、「普通の食品よりも健康に良いとして販売される食品全般」のことをいい、法律上の定義はありません。よって、健康食品とは健康が気になる方が健康の維持・増進のために使用するものといえます。
健康食品には、サプリメント、栄養補助食品、健康補助食品、機能性食品、保健機能食品、特定保健用食品、栄養機能食品、特別用途食品など、さまざまな名称の食品があります。
これらは、国が制度を創設して表示を許可しているもの(特別用途食品、特定保健用食品、栄養機能食品)と、それ以外のものに分類できます。
明確に分けなければならないものは、医薬品との区別です。
身体の構造や機能に影響を与えるような表示をすることは認められていません。
「診断する」「予防する」「治療する」「軽減する」などの表現は許されていないのです。
それぞれの分類をみていきましょう。
厚生労働省 1)健康食品やサプリメントの名称について https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dl/pamph_healthfood_d.pdf
引用・一部改訂
国が制度を創設して、保健機能や栄養機能の表示を許可しているもの
特別用途食品
乳児、妊産婦・授乳婦、病者など、医学・栄養学的な配慮が必要な対象者の発育や、健康の保持・回復に適しているという「特別の用途の表示が許可された食品」のこと。
特別用途食品の表示をするためには、健康増進法(第26条)に基づく消費者庁長官の許可が必要になります。許可基準があるものについてはその適合性を審査し、許可基準がないものについては個別に評価が行なわれます。
特定保険用食品は、その制度が創設された際の分類の関係から、特別用途食品の一つでもあるのです。
特定保健用食品
食品機能を有する食品の成分全般を、広く関与成分の対象として、ある一定の科学的根拠を有することが認められたものについて、消費者庁長官の許可を得て、特定の保険の用途に適する旨を表示した食品のこと。通称「トクホ」と呼ばれているものになります。
現行では、特定保健用食品(疾病リスク低減表示・規格基準型を含む)と、条件付き特定保健用食品があり、有効性及び安全性について、基本的に消費者庁および食品安全委員会の審査に通ることが必要です。
健康が気になる人を対象とした食品で、病気の治療のために使用する薬ではないので、多量に摂取しても予防の効果が高くなったり、病気が治るわけではありません。
過剰摂取で健康被害が出ることも考えられますので、補助的な用途で使用するようにしましょう。
栄養機能食品
身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分の補給・補完を目的に利用する製品。
12種類のビタミン(A、B1、B2、B6、B12、C、E、D、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、5種類のミネラル(鉄、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、銅)の含有量が国の基準を満たしている製品では、定められた栄養機能表示を付ければ、国への届出や審査を受けなくても販売することが出来ます。
どれか一つでも基準を満たせば表示が可能となるため、すべての栄養成分をバランスよく含有しているわけではありません。
許可されている以外のもの(健康食品とよばれるもの)
機能性食品
食品の三次機能(体調調節作用)に着目し、その機能性を示す食品全般が該当します。
一般には、試験管内実験や動物実験から得られた効果で機能性を示した食品が多く、機能性を発現する量に関する考え方が欠如した製品となります。
この中でも、ヒトにおいてその有効性・安全性が製品全体として審査され、国の許可を受けたものだけが特定保健用食品と認定されます。
栄養補助食品
以前まで定義されていたもので、栄養成分を補給し、または特別の保健の用途に使うものとして販売する食品のうち、錠剤、カプセルなど通常の食品形態でないものになります。
現在は、あまり使用される名称ではなく、国が制度化、定義しているものでもありません。
健康補助食品
栄養成分を補給し、または特別の保健の用途に適するもの、その他健康の保持・増進及び健康管理の目的のために摂取される食品として、財団法人日本健康・栄養食品協会が提唱しているものです。
栄養強化食品
栄養表示基準制度が創設されてから廃止されています。
栄養調整食品 など
国が制度化しているものではなく、表示の許可、認証、届出といった規制はありません。
よってどのような食品が該当するのか不明なものになります。
サプリメント
いわゆる健康食品のうち、米国のDietary Supplementのように特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態のものが該当すると考えられていますが、スナック菓子や飲料までサプリメントと呼ばれることもあります。
アメリカの栄養補助食品健康教育法という法律では、「薬と食品の中間のもの」と定義されていて、ビタミン、ミネラル、ハーブ、アミノ酸などの栄養素を1種類以上含んだもので、形状は「錠剤、カプセル、粉末、液体など、通常の食品の形以外のもの」と定義されています。
健康食品と医薬品の違い

錠剤・カプセル状の健康食品は、医薬品と混同されやすいのですが、この二つは全く異なるものです。その違いは、
①製品の品質(有効成分量、有害物質の混入の有無)
②安全性と有効性の科学的根拠(病気の治療・治癒効果の証明)
③利用環境(専門職のサポート体制)
です。
製品の安全性と有効性を確保するには、製品中に一定量の有効成分が含まれ、有害な成分が含まれていないことが重要です。医薬品は全てGMP(Good Manufacturing Practice適正製造規範)に基づき、一定の品質が確保された製品として製造されています。
医薬品は病気の人を対象に、有効性・安全性が検討されていて、医師・薬剤師の管理・指導によって安全かつ効果的に利用出来る環境が整備されていますが、健康食品の選択や利用は、消費者に任せられています。また、厚生労働大臣の承認を受けて国内で正規に流通する医薬品には、それを適正に使用していて重大な健康被害が生じた場合、救済を図る公的な仕組み(医薬品副作用被害救済制度)がありますが、健康食品にはこのような制度はありません。
健康食品は「摂取すれば健康になる」というイメージが強いようですが、安全性や有効性がしっかり検証されている製品もあれば、全く検証されていなかったり、医薬品成分が違法に添加されていなかったりする悪質な製品もあります。
健康食品の問題点

先にも挙げていますが、健康被害が出たり、高額商品があったりと、安易に使用すべきでないものが健康食品です。
そのことを念頭に置き、実際どのような問題があるのかを、ここでまとめておきます。
消費者庁HP 健康食品https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/food_safety_portal/health_food/ 引用・一部改訂
健康食品による健康被害
健康被害の原因には、粗悪製品の利用、過剰摂取、アレルギー体質の人の利用、医薬品との相互作用などが挙げられます。
効果を実感できない人が、食品だからと自己判断で、過剰摂取しやすいことも健康食品に特有の現象です。現在の世の中には、多様な品質の健康食品が消費者の自己判断で利用されており、健康被害の正確な実態はよくわかっていません。
「東京都福祉保健局」の調査によると、健康食品によって身体の不調を感じた人は利用者の4%程度で、下痢や腹痛、発赤や発疹、体のかゆみなどのアレルギーと思われる症状が多いと報告されています。
その他、肝機能や腎機能に障害が起きたという、一部の報告があります。
そのような被害が起きる健康食品の多くは、サプリメントといわれている錠剤・カプセル状の製品です。その理由としては、形状から医薬品と誤解して、病気の治療目的に使われることが考えられます。
また、特定の成分が濃縮されているため、日常食べている食品よりも身体への作用が強くなり、望まない影響が出やすくなる、とも考えられます。
健康被害の症状が重篤になる事例として、医薬品との飲み合わせが特に問題となっています。
特に病気の人は、身体の機能が落ちているため、摂取した成分の有害な作用を受けやすく、そのような人が健康食品と医薬品を併用すると、医薬品が効きにくくなったり、副作用が出やすくなったりする場合があります。使用する場合は必ず、治療を受けている主治医と相談するようにしてください。
根拠のない健康食品の広告などの問題点
健康食品の中には、「有名人が利用している」「稀有な成分が含まれている」「病気が治った」「特許取得」「〇〇賞を受けた」など、魅力的なうたい文句がついているものが多く存在しますが、これらの内容は、製品の安全性や有効性を保証するものではありません。
なお、このような魅力的な効果をうたいながら、その効果などが実証されていない広告は、虚偽表示や誇代表示に該当し、「健康増進法」や「不当景品類及び不当表示防止法」で禁止されています。
しかしながら、「個人の感想です。」「効果を保証するものではありません。」といった効果の保証を打ち消す文言を併用すれば、規制を逃れられると誤解している事業者が根拠なく広告をおこなっている場合があるため、注意が必要です。
経済的被害
健康食品による被害には、効果のない高額な製品を購入したことによる経済的被害もあります。
高額な製品ほど効果が期待できると誤解される傾向もあるようですが、価格は販売者が自由に決めるものであり、効果が保証されるものではありません。
特にがん関連の分野では、効果を保証できないにも関わらず、効果にすがりたい利用者の心理を利用した高額商材があるのも事実です。無闇に手を出さず、医療者の意見をしっかりと聞いた上で、利用されるかどうかは判断するようにしましょう。
【引用・参考文献】
古川裕之著:「ナースのための図解 くすりの話」、学習研究社、2007.11

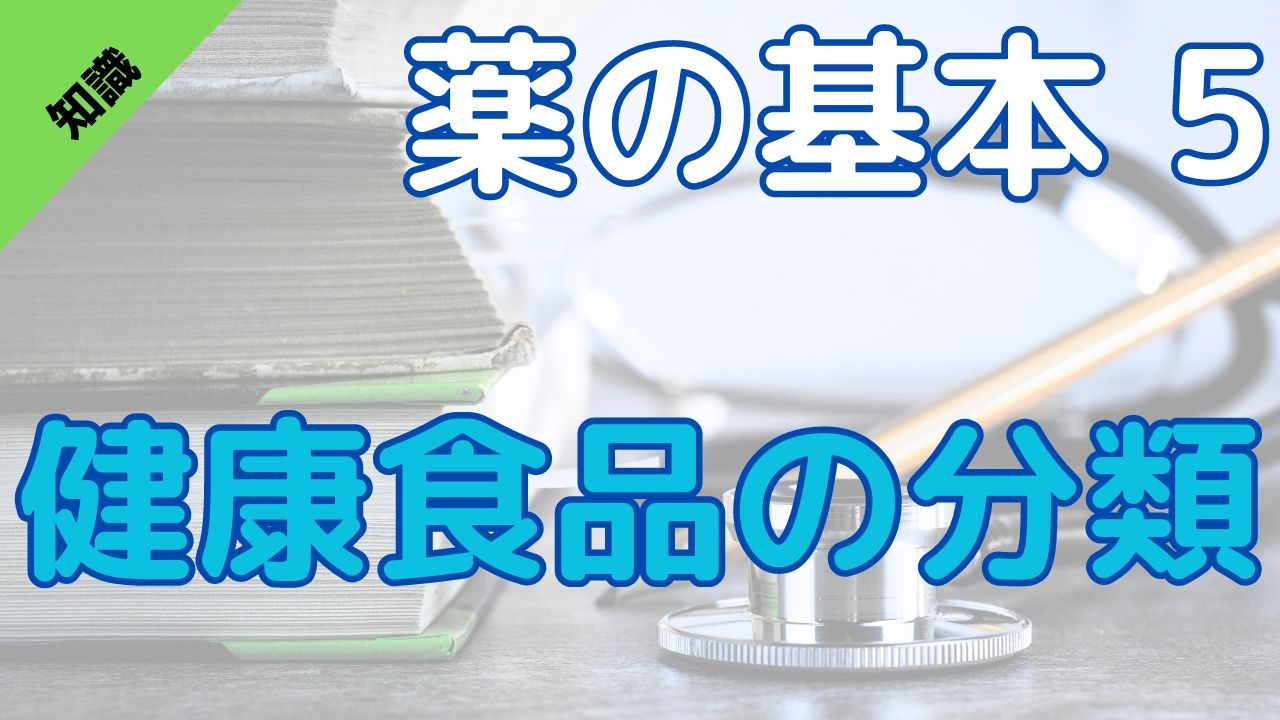


コメント