Part1に引き続き、薬の知識をつけていきましょう。
実際に使用する場面も多いため、即実践につながることでしょう。
投与経路による違い
経口では吸収が期待できない、無効な場合には、注射や他の投与経路が選択されます。
それぞれの特徴をみていきます。
注射による投与
注射による投与は、経口投与に比べて速効性があります。
また、水溶性の薬や消化管での分解や初回通過効果を受けやすい薬など、
経口投与では良好な吸収性が得られない薬においても、注射による投与で治療効果を得られます。
しかし、注射特有の有害事象もあります。
最もよく行われる静脈注射で多い合併症は、
①注射手技によるもの(注射部位の腫れ・発赤・硬結、末梢神経障害、血腫、空気塞栓、全身感染)
②投与薬剤によるもの(有害反応、過敏反応、血栓性静脈炎、薬剤の血管外漏出による局所壊死)
などがあります。
その中で、最も危険なのは、アナフィラキシー・ショックの発現です。
死亡する可能性もあるため、投与する際にまず注意しなければならない症状です。
動脈内・静脈内投与
投与された薬の100%が直接循環血中に入るため、吸収過程のない投与経路となります。
そのため、迅速かつ確実な全身作用が期待できます。
関節腔内・脊髄腔内投与
全身循環血中への移行を必要としません。
投与部位への局所作用を目的とした投与経路になります。
皮内・皮下・筋肉内投与
投与部位の組織から毛細血管壁を経て、通常は血管内に移行します。
皮内や筋肉の血管壁は、比較的薬が透過しやすい構造で、投与された薬の100%が吸収されます。
しかし、吸収速度は投与部位によって異なり、組織の血流が速いほど、
循環血中への移行は速くなると考えられます。
筋肉内>皮下>皮内の順で吸収速度が速くなります。
直腸内投与
直腸内投与では、一般に坐薬が用いられます。
坐薬を用いた直腸粘膜からの薬の吸収経路は、局所作用を期待する薬だけでなく、
全身作用を期待した薬の投与経路としても用いられます。
坐薬は体温や分泌物によって徐々に溶けます。
坐薬の挿入後に排便があると、薬剤が吸収されない(または吸収量が減少する)ので、
排便後や入浴後、または寝る前の投与が望ましいです。
直腸は、小腸に比べて表面積も狭く、薬の吸収部位としてはそれほど適した場所ではありません。
しかし、直腸下部の血管は門脈に繋がっていないので、
肝臓で初回通過効果を受けることなく、直接、大動脈から全身循環に移行します。
経口投与された薬は消化管内を移動しながら吸収されるのに対して、
直腸内に投与された坐薬は投与部位にとどまります。
そのため、吸収促進薬を確実に作用させることが可能で、
小腸に比べて吸収促進薬の効果を顕著にみられることも、直腸内投与の利点の一つです。
経皮吸収
皮膚はもともと、皮膚局所への作用を期待した製剤の使用部位でした。
しかし、外皮用配合剤のMS温湿布、MS冷湿布などは、
筋肉の炎症を抑えることを目的に皮膚に適用されるようになりました。
これは、注射投与や経口投与に比べて、薬のより高い筋肉内濃度が得られます。
また、皮膚から投与された薬は、全身循環血中へも移行することから、
現在は、経口剤と注射剤に続く第3の投与経路として、全身性経皮吸収材(虚血性心疾患、ホルモン補充、気管支拡張、がん疼痛、禁煙補助)が広く使用されています。
①経口投与が困難な患者にも適用しやすい
②小腸や肝臓における初回通過効果を受けない
③薬効発現が持続する
④副作用発現時にはすぐに投与を中止できる
AEDを使用する時の貼付剤はどうするか
電極パッドを装着する部分にあるすべての貼付物(貼付剤、ネックレスなど)を除去します。
貼付物によっては、AEDからの電極パッドから心臓への電気エネルギーが遮断されたり、皮膚に熱傷を起こす危険性があるからです。
AEDを行う人も同様に除去する必要があります。
経鼻吸収
鼻腔内への薬の投与は、鼻感冒や鼻炎などの治療のための局所作用を目的とします。
しかし、鼻粘膜から吸収されて全身作用を発現することから、
全身作用を目的とした経鼻吸収製剤があります。
鼻粘膜に投与された薬は、吸収されたのち、直接全身循環血中に移行します。
そのため、経鼻吸収は、初回通過効果を回避できる投与経路として、
消化管や肝臓で代謝されやすい薬の投与部位に適しています。
口腔粘膜吸収
口腔粘膜から吸収された薬は、初回通過効果を受けることなく、全身循環血中へ移行します。
適用されている製剤として、バッカル錠と舌下錠があります。
バッカル錠
ほほ粘膜に適用し、局所で薬を徐々に放出させて薬効を発現します。
口内炎治療薬のトリアムシノロンアセトニドを封入したアフタッチ®などがあります。
舌下錠
舌の下に薬を置くと、すぐに崩壊したのちに速やかに吸収され、薬効を発現します。
狭心症治療薬のニトロペン®などがあります。
経肺吸収
吸入剤による呼吸器への薬の投与は、気管支喘息治療薬などの局所作用を期待して用いられます。
肺から吸収された薬は、直接全身循環血中へ移行するため、初回通過効果を受けません。
また、消化管から吸収されないような高分子物質に対しても肺が高い透過性があることから、
全身作用を目的としています。
正しく薬剤が吸入されるためには、呼気に合わせて吸入することが必要です。
上手く吸入できるように、吸入方法について患者説明が大切になります。
口腔内に残っている薬を除去するため、必ずうがいをし、口腔内カンジダ症を予防します。
眼粘膜吸収
眼粘膜へ薬物を投与する場合は、一般に点眼投与が行われます。
点眼剤は、結膜炎や緑内障の治療における局所作用を目的として用いられます。
しかし、投与された薬が鼻涙管を流れ落ちて、全身作用を発現することもあります。
点眼剤を使用したのちには、目頭をしばらく押さえたり、瞬きをせずしばらく閉眼することによって、
鼻腔内への薬の流出を防止して効果を高めると同時に、薬の全身作用を軽減します。
点眼剤の汚染防止のため、投与の際は容器の先がまぶた、まつげや目に触れないよう注意が必要です。
2種類以上の点眼剤を用いる場合は、涙液の交代を考慮して、5分以上の間隔をあけることが望ましいです。水虫用薬剤や下剤の容器で、点眼剤の容器と似ているものがあり、誤って点眼される事例もあります。
間違わないように患者への十分な説明が必要です。
薬を飲むタイミング
一般的には、空腹時に薬剤を服用すると吸収は早くなり、薬理効果も早く出ます。
一方、食後に服用すると、吸収は遅くなりますが、作用の持続時間は長くなります。
服用時間が制限される薬の種類は多くはなく、
薬剤の効果を持続させるためには、食事時間と関係なく一定時間ごとの服用が基本です。
空腹時の服用による胃粘膜の刺激が心配であれば、コップ1敗の水かぬるま湯で薬剤を飲むことで、
胃粘膜への刺激を防ぐことができます。
起床時(起きてすぐ)
起床時は空腹なので、他の薬や食事の影響を受けません。
一部の骨粗鬆症の薬などは、起床時に服用します。
他にも食物中のカルシウムや鉄などの金属と結合することによって、
吸収が減少する薬剤(抗菌薬など)もあります。
食前(食事の約30分前)
胃の中に食べ物があると吸収が悪くなる薬や吐き気止めなど、
食後に飲んだのでは効果が期待できない薬は、食前に服用します。
| 当てはまる薬剤 | 理由 |
|---|---|
| リファンピシン(リファジン®)など | 食事の影響で吸収が悪くなるため |
| 吐き気止め ドンペリドン(ナウゼリン®) | 食べる頃に合わせて薬効を期待するため |
| 食欲を出す薬 メトクロプラミド(プリンペラン®) | 食べる頃に合わせて薬効を期待するため |
| 漢方薬 | 空腹時の方が吸収が良くなるため |
食直前(食事始めのすぐ後)
食事と一緒に消化されることで効果を発揮する薬や、
血糖コントロールに関係する薬は、食事の直前に飲むことがあります。
| 当てはまる薬剤 | 理由 |
|---|---|
| 糖の吸収阻害薬 α-グルコシダーゼ阻害薬 | 食べ物と混ざり合って効果を現すため |
| 速効型食後血糖降下薬 ナテグリニド(ファスティック®、スターシス®) ミチグリニド(グルファスト®) | 服用後すぐに効果が現れるため、 低血糖を防ぐため |
食後(食後30分以内)
食後に飲む意味は、薬によって胃が荒れにくいこと、飲み忘れが少ないことなどがあります。
多くの薬はこれに当てはまります。
食間(食後2時間程度)
食間とは、食事中ではなく、食事と食事の間を指します。
胃の中に食べ物がなくなる時間帯に服用します。
| 当てはまる薬剤 | 理由 |
|---|---|
| クレメジン | 食事から摂取されるビタミン類や他の薬も吸着してしまうから |
| 漢方薬 | 空腹時の方が吸収が良いから |
就寝前(寝る30分くらい前)
睡眠薬など、薬効に合わせて飲みます。
臥床したまま飲もうとする方もいますので、注意が必要です。
【引用・参考文献】
折井孝男監修:「説明力UP!臨床で役立つ薬の知識」、学習研究社、2007.3
浜田康次監修:「スラスラわかる薬のメカニズム」、医学芸術社、ナーシングカレッジ2006年10月臨時増刊号、第10巻第12号通巻148号
古川裕之編著:「ナースに必要な薬の基本 キー・ドラッグ」、学習研究社、2007.12

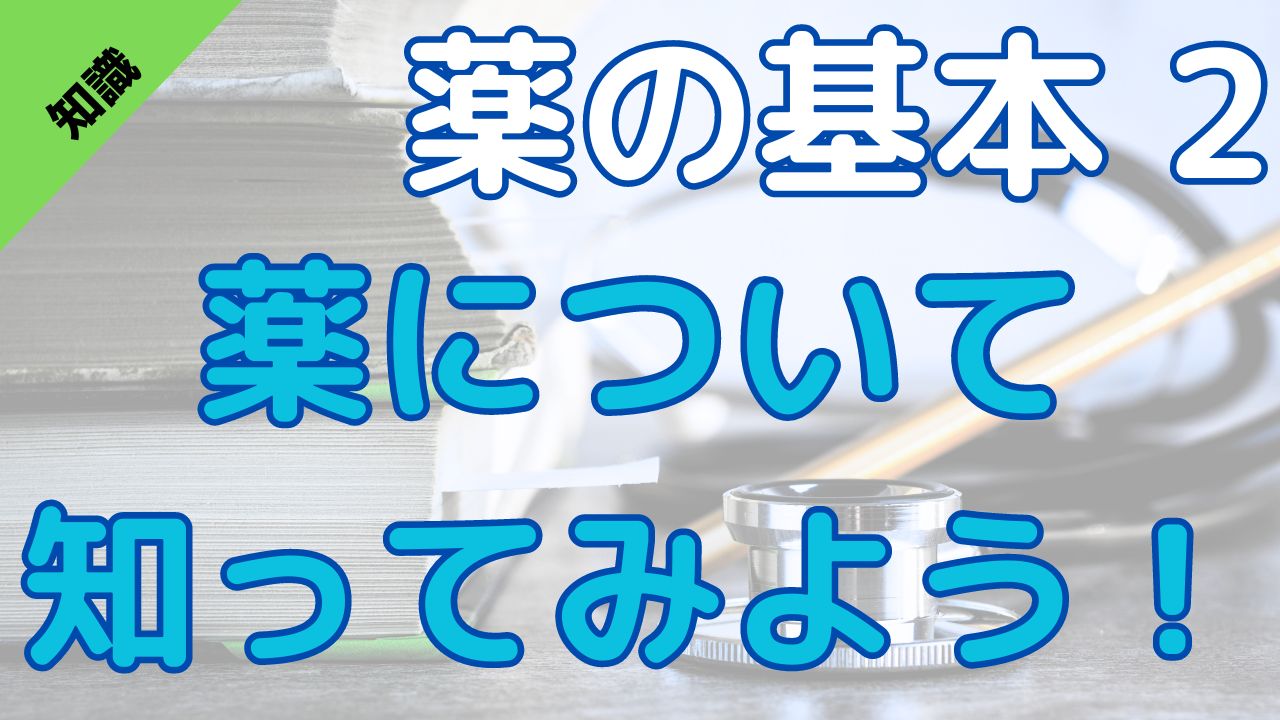


コメント