薬剤師さんがいるから看護師には薬の知識は必要ない。
そう考えることもあるのではないでしょうか。
実際に薬を使用するのは看護師が多く、その際には使用説明を行う必要があります。
患者からすれば、何の薬か分からないのに飲みたくないですよね。
ですが、看護学校では医療全般に目を向け、特に身体状況を重きに置くため、
特に薬の知識を重要視することはありません。
私も薬は苦手な分野の一つでしたが、臨床に出て必要性を感じることになりました。
薬の知識の必要性が分かるように、順を追ってみていきましょう。
薬の歴史
人類は古代から薬を使用してきました。
その営みは、傷や病を癒すために自然界にある様々なものを試して、試行錯誤してきたのです。
「薬」という字は、「楽にする植物」という意味があります。
人類史上最古の記録は、紀元前3000年頃、エジプトのチグリス・ユーフラテス川流域に栄えた
人類最初の文明とされるメソポタミア文明を築いたシュメール人の記録です。
当時の粘土板に、ヤナギやモミ、洋ナシなど約10種類の植物を
薬として使用していたことが記されています。
しかし現代の薬とは異なり、「体内に潜んだ悪魔を追い払うもの」としていたため、
わざと吐かせたり下痢をさせたりするものも多くあったようです。
近代薬理学は19世紀初頭に発展しました。
初めて薬効が確認されたのは、強心薬のジギタリスです。
アヘンからモルヒネが抽出されたり、ヤナギからサリシンを抽出しアスピリンを生成したりと、
目覚しい発展を遂げています。
薬事法で定められる定義
医薬品:人の病気の診断・治療・予防を目的とする
医薬部外品:人の病気の予防だけを目的とする。作用が緩和なもの。
化粧品:体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦・散布などして使用されるもの
日本で許可され、常用されている薬は、「日本薬局方」に明示されています。
医薬品の品質や純度に関して定めた規格書で、5年毎に改正されます。
この規格に該当しないものは、医薬品として製造・販売することはできません。
医療用医薬品
処方箋で出される薬で、医師の診断により患者の症状、年齢などから種類と量が決められ、
処方される目的も医師の判断により異なります。
医師もしくは歯科医師が医療行為を行う上で、自ら使用しまたはこれらの者の処方箋によって
使用されることを目的として供給される医薬品である。
後発医薬品とは、医療用医薬品の中で新薬の特許期限が切れたのちに製造販売される医薬品をいいます。新薬の開発は、十数年の年月と数百億円の経費がかかるといわれています。これに対して後発医薬品は、新薬の特許が切れたのちに公開された新薬の有効成分と同一成分を使用してつくられる医薬品であるため、安価で製造・販売することができます。
一般用医薬品
医師の処方なしで、市中の薬局で買うことのできる薬で、一般用医薬品・一般薬・大衆薬・OTCなど
様々な呼び方がある。患者・家族が症状を判断して選ぶため、薬の成分の種類、量が規制されている。
一般の人が医師などの診断なしに自覚症状に基づいて自己の判断で使用することを目的として供給される医薬品である
毒薬と劇薬
薬事法では、医薬品を毒薬、劇薬、普通薬の3つに分けています。
毒薬・劇薬は必ず容器にそれと示すラベルがついていて、
保管の仕方や扱い方について法律で厳しく定められています。
| ラベルの表示 | 保管 | |
|---|---|---|
| 毒薬 | 黒字に白枠、白地をもって 薬品名と「毒」の表示 | 鍵をかけた場所 他の医薬品と区別 |
| 劇薬 | 白地に赤枠、赤字をもって 薬品名と「劇」の表示 | 他の医薬品と区別 |
| 普通薬 | ― | ― |
| 麻薬 | 鍵をかけた堅固な設備 (麻薬金庫) 他の医薬品と区別 | |
| 向精神薬 | 〇の中に「向」の表示 | 鍵をかけた設備 |
薬の効き方
薬はそもそも、生体にとっては異物です。
私たちの体内で起こる生理現象には、多くの化学物質が関与しています。
何らかの異常が発生している時、正常な機能に戻すために、その化学物質を使うことが薬物療法です。
薬剤の体内動態(ADME)
薬物は体内に入ってから、食物と同じように分解・吸収され、代謝され、排泄されていきます。
その過程を吸収・分布・代謝・排泄という4つの相で説明されています。
吸収(absorption)
口から内服した薬の主な吸収先は、表面積の大きな小腸です。
薬が吸収されるために、まずクリアしなければならないのが、細胞膜の透過です。
細胞膜は、脂質二重層とよばれる構造をしており、
一般的には脂質に溶けやすい脂溶性の物質は細胞膜を透過しやすく、
水溶性の物質は細胞膜を透過しにくいと考えられています。
実際には、トランスポーターとよばれる薬の運び屋が、細胞膜の中あるいは表面で
機能することにより、生体に必要なアミノ酸やグルコース、水溶性ビタミン類なども効率よく
細胞内に取り込まれます。
逆に、細胞内から細胞外へ物質を運び出すはたらきをするトランスポーターも存在し、
脂溶性が高いにも関わらず、細胞外へ運び出され細胞膜を透過できる量が制限される薬物もあります。
また、物質の分子量によっても膜の透過性は制限されます。
細胞膜は、吸収過程における消化管壁の透過だけでなく、分布における循環血中から
各組織への移行に際しても越えなければならない障壁となります。
よって、薬が吸収部位において溶解した状態である必要があります。
経口投与された薬物は、胃、小腸、大腸において様々な環境に曝露されます。
この過程において、化学的にも生物学的にも薬が安定していることが必要となります。
初回通過効果
小腸から吸収された薬剤は門脈系に入り、肝臓を通過した後、心臓から全身に送り出され、
その後肝臓を再び通過する時に代謝されます。
一部の薬剤では、最初に肝臓を通過する時に著しく代謝を受けることが知られていて、
それを初回通過効果とよびます。
初回通過効果は主に肝臓で起こりますが、
消化管粘膜の細胞内に存在する酵素によって代謝を受ける薬も多く存在します。
アスピリン:カルボキシエステラーゼやリパーゼなどによって代謝される
シクロスポリン、タクロリムス、ベラパミルなど:CYP(チトクロームP450)によって代謝される
①口腔粘膜:バッカル錠・舌下錠
②直腸:坐薬
③皮膚:貼付剤
④肺:吸入剤・エアゾール剤
⑤鼻腔:点鼻剤
⑥静脈・動脈・筋肉内:注射剤
※脂質やタンパク質などの高分子物質も初回通過効果を受けない
分布(distribution)
吸収された薬の多くは、血液中の血漿タンパク質、
主にアルブミンと一定の割合で結合して存在しています。
血管や組織細胞膜を透過できる薬は、タンパク質と結合していない非結合型の薬のみで、
タンパク質と結合している結合型の薬は血管壁を透過できません。
そのため、結合型の薬は排泄も組織への分布もされずに、血中に留まっています。
しかし、血中の非結合型の薬が分布・代謝・排泄を受けて、その血中濃度が低下すると、
タンパク結合率に応じて結合型の薬が血漿タンパク質から遊離して非結合型となります。
血液中を流れる薬剤は、血漿アルブミンと結合してしまうと、薬理作用を発揮できなくなります。
標的となる臓器に存在する受容体と結合することによって、薬理作用を発揮します。
低アルブミン血症や妊娠時など、血漿中のタンパク濃度が低下している場合は、
薬の体内動態および薬理効果が変化する可能性があります。
腎不全などで腎機能が低下している場合は、タンパク結合率が低下しやすいため、
非結合型分率が高くなる可能性があります。
薬の総血中濃度が有効治療域濃度であっても、
非結合型の薬の濃度の上昇により毒性を発現する場合があります。
生体にとって本来異物である薬は、P糖タンパク質を代表とする排出トランスポーターによって、
吸収を妨げられ、胆汁中、尿中への排出が促進されます。
P糖タンパク質は腎臓、肝臓、小腸、血液脳関門、血液胎盤関門、血液精巣関門などに発現しています。
これらは細胞毒性の高い薬物を腸管からの吸収を制限し、生体を防御する機能として存在します。
ですが、全ての薬物をシャットアウトできるわけではなく、
脂溶性で分子量の小さいものは、これらの関門も容易にくぐり抜けてしまいます。
脳は、個体の生と行動、思考、感情などの活動を制御する非常に重要な臓器です。
脳の血管には有害な生体異物から脳を守るため、血液脳関門という防御機構が備わっています。
循環血液中の薬や栄養物質などはBBBを透過して脳内へ移行します。
しかしBBBでは、脳毛細血管内皮細胞が密着結合し、その周囲を星状膠細胞(アストロサイト)の小足が取り巻くことによって非常に密着した隙間のない構造を形成していて、薬の脳内への透過が厳しく制御されています。
逆に、生体に必要な物質を積極的に取り込む輸送系も存在します。
脳内で神経伝達物質の前駆体やエネルギー源として用いられるアミノ酸やグルコースは水溶性の物質ですが、これらを脳へ取り込む方向へ運ぶ坦体輸送系が存在し、速やかに透過できるようになっています。
代謝(metabolism)
薬剤は腎臓から排泄されやすいように、酵素の働きでより水に溶けやすいものへと代謝されます。
代謝の関所は肝臓です。
肝臓には、代謝を促進する様々な酵素があります。
最も重要な酵素はCYP(チトクロームP450)とよばれる酵素群です。
これはあらゆる薬物に対応するため、その亜種が無数に存在します。
酵素による代謝様式は、大きく2段階あります。
1つは第1相反応と呼ばれるもので、酸化・還元・加水分解などの反応がそれにあたります。
第1相反応は、薬物の分子構造を変化させることで活性を弱め、受容体と結合しにくくします。
もう1つの代謝様式は、第2相反応とよばれます。
こちらは、本来は水に溶けにくい薬物を、グルクロン酸や硫酸、
グルタチオンなどの物質で包むことで、水に溶けやすくします。
包む物質の名称により、グルクロン酸抱合、グルタチオン抱合などとよばれます。
同様の反応は、通常の生理反応でもみられます。
古くなった赤血球のヘモグロビンが分解されてできたビリルビンは、
肝臓に運ばれて不溶性から水溶性へと変化します。
これも、グルクロン酸抱合によるものです。
ある薬剤を何度も続けて投与すると、CYPの産生が増加し(酵素誘導)、
基質となる薬剤の代謝速度が高まることがあります。
逆に、薬剤によっては、CYPの酵素作用を阻害し(酵素阻害)、基質となる薬剤の代謝を
減少させることによって、薬理作用の増大や作用時間の延長を引き起こすことがある。
肝臓で代謝されて初めて薬理作用を発揮する薬のことをいいます。
プロドラッグは、肝臓による代謝を逆手にとって開発された薬です。
そのままでは受容体に結合することはできませんが、
肝臓で代謝を受けて分子構造が変化することにより、受容体と結合することができます。
例:フェナセチン、ロキソプロフェン(鎮痛薬)
エナラプリル(ACE阻害薬)
プリミドン(抗てんかん薬)
薬物代謝の重要なはたらきをしている酵素がCYPです。
約80%以上の薬がCYPにより代謝されているといわれています。
CYPは30以上の分子種が存在し、CYPの約半数がCYP3A、次にCYP2D6により代謝されています。
CYPには遺伝的に規定されたアイソタイプがあり、CYP1A2(~10%)、CYP2C9(~20%)、CYP2C19(~3%)、CYP2D6(~3%)、CYP3A4(~30%)など、主なものは11種類あり、全部で約100種類が知られています。
ある薬剤の代謝に関与するCYPが欠損していると、代謝が行われずに、体内に薬剤が長く高い濃度で貯留することになります。
また、同じサブタイプで代謝される薬剤を併用すると、互いの代謝を邪魔し合うことになり(薬剤相互作用)、予期しない有害作用が現れる可能性があります。
CYPの特徴として、多数の分子種の異なる酵素があり、かつ基質特異性が低いです。
すなわち、1つの酵素が数多くの薬を代謝するという性質があります。
同じ分子種によって代謝される薬は、同時に服用した他の薬の代謝を互いに阻害する可能性があります。
また、薬の長期投与によってCYPが誘導されることもあり、その状態では、その薬の代謝が亢進するとともに、同じCYPによって代謝されるほかの薬の代謝も亢進します。
また、1つの薬でも代謝を受ける部位によって異なるCYPで代謝されることもあります。
CYPは主に肝臓に発現していますが、小腸、肺、腎、副腎、前立腺などにも発現しています。
アルコールは主に、アルコール脱水素酵素(ADH)とアルデヒド脱水酵素(ALDH)の2つの酵素によって代謝されます。
胃や腸から吸収されたエタノールはADHによってアセトアルデヒドに代謝されて、次にALDHによって酢酸に酸化されます。
このALDHは遺伝的に代謝能が高い人と低い人があります。
アルコールを摂取した時に、頭痛や悪心などを引き起こし、いわゆる二日酔いや悪酔い状態の原因となるのが中間代謝物であるアセトアルデヒドです。
ALDHの活性が低いか欠落している人は、アセトアルデヒドが酸化されず、その血中濃度が急激に上昇して上記の症状が出てしまいます。
ちなみに日本人の約45%はこのALDHの活性が低いか欠落していると言われていて、10人に1人は体質的にアルコールを全く受け付けないと言われます。
このように薬の代謝にも個人差があります。
代謝能が低い人では、薬によっては血中濃度が高く、かつ長時間維持されて副作用が起こりやすくなっている可能性があります。
長時間の大量飲酒によってアルコールを代謝するCYPが多く誘導されて、エタノールを水と二酸化炭素に直接分解するようになります。
この状態になると、多少のアルコールでは酔えなくなります。
また、非飲酒時ではCYPが誘導されているため、CYPで代謝される薬は、代謝が促進されて薬効が減弱する可能性もあるのです。
大量飲酒者であってもなくても、飲酒時または飲酒後に薬を服用すると、アルコールにより薬の代謝が阻害されて、薬の血中濃度が高くなり、薬効が増強されることがあります。
排泄(excretion)
投与された薬剤の主な排泄経路は腎排泄と胆汁中排泄ですが、
腎臓から尿として排泄できるのは、水に溶ける物質だけです。
水に溶けない物質は、尿細管から再吸収されて再び体内を巡り、髪の毛や便に混ざって排泄されます。
なかには、小腸内の移動中に酵素による代謝を受け、小腸から再吸収され(腸肝循環)、
体内に長くとどまる薬剤もあります。
腎臓は、糸球体濾過、尿細管分泌、尿細管再吸収の3つの機能を持っています。
糸球体濾過
腎臓に入った血液は、まず糸球体で濾過されて、分子量が5000以下の血液成分は、全て尿細管内へ移行します。
このとき、血漿タンパクに結合している薬は濾過されません。
また、腎臓での薬物排泄は、酸性の薬物は、尿が酸性であるほど再吸収されやすく、
アルカリ性になるほど排泄されやすくなります。
また塩基性の薬物は、尿が酸性であるほど遊離型が増えるので、排泄されやすくなる特徴があります。
尿細管分泌
糸球体における血漿の透過率は約20%で、血漿タンパクへの結合がなくても、
糸球体濾過だけでは腎臓での薬の除去には限界があります。
尿細管分泌系はこれを補って、薬物や生体異物のより迅速な体外排出を可能にします。
また、水素イオンなども分泌されて、体内のpHを一定に保つように機能しています。
分泌は全て、トランスポーター(輸送担体)を介した能動輸送によって行われていて、
薬は血液から直接尿細管へ排泄されます。
尿細管での代表的なトランスポーターとして、有機アニオントランスポーター(OAT、OATPs)、
勇気カオチントランスポーター(OCT、OCTN)、P糖タンパク質などがあります。
これらの基質認識性は幅広く、同じトランスポーターの基質となる薬を併用した場合には、
競合阻害が起こり、体内動態が変動する可能性があります。
尿細管再吸収
1日の総糸球体濾過量は約150~190Lといわれていますが、体液量を保つために尿細管で
その約99%が再吸収され、最終的に尿として体外へ排泄されるのは、1.5L程度といわれています。
尿細管では、生体に必要な水や有機物質(糖、アミノ酸、小分子ペプチド、タンパク質など)、
無機イオン(ナトリウム、塩素、リンなど)が受動輸送、能動輸送によって再吸収されます。
尿細管管腔から水が再吸収されると、尿細管管腔中と血中に薬物の濃度勾配が生じて、
これが原動力となって薬物の再吸収が進行します。(受動輸送)
また、有機物質、無機イオンなどは特有の輸送担体を介してその大部分が再吸収されます。(能動輸送)
尿以外の排泄経路
薬の主な排泄経路は尿中と糞便中であり、糞便中の排泄は主として胆汁中の排泄により、
一部は唾液、乳汁中、消化管液、呼気中の排泄を通じて行われます。
胆汁中排泄
薬の中には、肝臓で薬物代謝酵素系によって水酸化を受け、さらにグルクロン酸抱合、硫酸抱合、
またはグルタチオン抱合などを受けて、胆汁中へ排泄されるものがあります。
胆汁中に排泄されるためには、ある程度の極性と脂溶性を持ち、
分子量が約500以上、5000以下であることが必要となります。
そのため、極性が極めて高いものは胆汁中よりは尿中に排泄され、
脂溶性が高いものは胆汁中へは排泄されないのです。
胆汁中排泄される薬は、血液中から肝実質細胞へ取り込まれ、毛細胆管側膜を通過し、
胆汁中へ移行し、一度胆嚢に蓄えられ、胆管を経て十二指腸へ送られます。
腸管内に排泄された抱合体は、消化管中の酵素や腸内細菌によって分解を受け、
再び小腸から吸収されて門脈系に入り、肝臓へ戻ることがあります。(腸肝循環)
腸肝循環により、一度排泄されたかと思われた薬が再び吸収されるため、その血中濃度は、
腸肝循環しない薬に比べて高濃度が長時間維持されることになります。
乳汁中排泄
血漿中の薬は、受動拡散によって乳汁中へ移行し、排泄されます。
低分子化合物は水溶性であっても乳汁中へ排泄されやすく、高分子化合物はほとんど排泄されません。
そのため、脂溶性が高いもの、弱電解質性の薬物では、非イオン型のもの、
および血漿タンパクと結合していない非結合型のものほど、乳汁中に排泄されやすい性質となります。
乳汁中に排泄される薬の量は、一般には低いとされています。
ですが、身体機能が未発達である乳幼児が母乳を連続して摂取した場合、その摂取量が蓄積されて、
薬によっては乳児に影響を及ぼす可能性があります。
唾液中排泄
唾液中には、脂溶性が高い薬、弱電解質性の薬では非イオン型の薬、
および血漿タンパクと結合していない非結合型の薬が、受動輸送によって排泄されます。
一般に血漿中の非結合型で、非イオン型の薬の血中濃度と唾液中濃度は同程度といわれています。
その他の排泄
気体や気化する薬の中には、肺から排泄されるものもありますが、主な経路とはいえません。
また、薬を静脈内投与したのち、薬が消化管中へ直接排泄される可能性も示唆されています。
このように、異物を代謝排泄するという行為は、とてもストレスのかかる作業です。
よって、肝臓や腎臓の機能が弱くなっている場合には注意が必要となります。
高齢者や子どもに対する、薬用量が異なるのはこのためです。
内服薬のいろいろ
薬効を有効に発揮させるために、薬剤の化学的・物理的性質を考慮して様々な剤形の製剤があります。
内服だけでも剤形を工夫することで効果的な薬効を示すことができます。
錠剤
錠剤には、表面や内部に特殊な加工をしたものが多くあります。
例えば、味の良くない薬の表面をコーティングすることによって飲みやすくした糖衣錠やフィルムコート錠、胃では溶けずに小腸で溶けるようにした腸溶錠、作用を持続させるために胃で溶ける部分と腸で溶ける部分を混合した錠剤があります。
このように加工された錠剤は、かみ砕いたり、つぶして服用すると、
その加工の意味がなくなるので注意が必要です。
他にも口腔内で唾液によって容易に崩壊する口腔内崩壊錠(D錠、OD錠、ザイディス錠)は、
水なしでも服用できるので、高齢者や嚥下機能低下患者、仕事や学業で多忙であったり、
すぐに水を用意できない時でも容易に服用できる便利な剤形です。
厳密には、水なしで服用できるものは口腔内崩壊錠、少量の水で服用できるものを速崩錠と区別されますが、臨床的には同じように使用されています。
徐放性製剤は、薬を徐々に放出するメカニズムを組み入れて、投与後数時間にわたって薬の放出を持続させることにより、少ない投与回数で、薬物血中濃度を維持できるように加工した製剤です。
徐放性製剤の商品名には、L(long)、LA(long acting)、CR(controlled release)、SR(sustained release)、R(retard)などの接尾語がつけられています。
これらには、エラー防止の立場から、紛らわしいアルファベットを使用しない、
一文字のアルファベットを使用しないなどの指導が行われています。
注射薬の場合は、ホルモンをマイクロカプセル化した製剤を4週間に1回皮下に注射するだけで薬理作用を持続できるものがあります。
内服薬の場合は、消化管を通過し、下部消化管を経由して体外に排泄されるため、24時間以上の徐放性を持たせたとしても製剤自体が排泄されるので、期待できる時間には限度があります。
胃の酸性条件下で変化する薬および胃の消化酵素で分解される薬を、胃で溶解せずに製剤が小腸に排出されて環境pHが上昇してから崩壊・溶解するように、被膜を施した製剤です。
腸溶錠の適用は、①胃粘膜を強く刺激する薬、②胃酸により分解し効力が低下する薬、③薬効発現時間を遅らせて作用持続時間を延長したい場合、があります。
カプセル剤
カプセル剤は、錠剤と同じように、薬剤の味の悪さ、においの強さ、
胃内での分解を防ぐためにカプセル化しています。
カプセル剤が錠剤と異なるのは、内容が粉末だけでなく、
マイクロカプセルやゼリー状の液体を入れることができる利点があります。
カプセル剤も、カプセル表面または内容物のマイクロカプセル表面に加工したものがあるので、
むやみにカプセルを外して中身だけを服用したり、マイクロカプセルをかみ砕いたりつぶしたりして
服用すると、薬効が低下するだけでなく、吸収される薬剤の量が増えて思わぬ有害反応が現れることがあります。
散剤と顆粒剤
散剤は粉薬のことで、ドライシロップ剤もあります。
顆粒剤は、散財より粒が大きいもので、粒1つずつの表面を薄い膜で覆うことにより、
胃や腸の中で溶ける時間を調節したり、薬効が持続するように加工できます。
現在は、製剤技術の進歩により、服用のしやすさ、保存性、携帯性、特殊加工性に優れた
錠剤やカプセル剤がつくられるようになり、日本のように散剤や顆粒剤を多用している国はないです。
散剤は白色のものが多く、薬剤識別が容易でないので、安全管理面からも問題があります。
液剤とシロップ剤
液剤は、薬剤を水などに溶かして液状にしたものです。
薬剤の成分が溶けているので、小腸での吸収も良好で、効果が早く現れます。
液剤の中で、甘味と芳香のあるエタノールを含む透明な液状の内容剤をエレキシル剤といいます。
シロップ剤は、幼小児が飲みやすいように甘味を加えた液剤です。
しかし、最近は虫歯予防を理由に、シロップ剤を拒絶する保護者もいるようです。
作動薬と拮抗薬
【作動薬】
アゴニスト(agonist)、刺激薬(stimulant)ともいいます。
正常であれば受容体に結合する物質が生成されなかったり、少なすぎたりする場合、
それを補って結合したり、離れたりする薬のこと。
受容体との結合のしやすさを親和性といいます。
また、特定の受容体と結合する能力は、特異性または選択性といいます。
【拮抗薬】
本来結合するはずの物質が、結合することで不具合を起こす場合、
その受容体に結合してブロックしてしまう薬のことをいいます。
アンタゴニスト(antagonist)、遮断薬(blocker)、阻害薬(inhibitor)ともいいます。
拮抗薬には以下の種類があります。
- 競合性拮抗薬:受容体と可逆的に結合するため、作用薬の用量を増加すれば、受容体との結合の確率が増加するため、生理反応を正常に戻すことができる。
- 不可逆的拮抗薬:受容体との結合が強固であるため、作用薬の濃度を増加しても結合できる受容体が限られているので、生理反応を完全に正常に戻すことはできない。
- 非競合性拮抗薬:受容体に結合しないで、受容体以降に作用して生理反応を抑制する。
体内から薬が消えるまで
体内で代謝・排泄された薬物が、完全に消失してしまうまで、どのくらいの時間がかかるのか。
生物学的半減期といって、吸収された薬の血中濃度が半分になる時間を
T1/2(ティーハーフ)という記号で表されます。
一般的に薬は投与されるとすぐ、全身の各組織へと移行し、肝臓で代謝され、腎臓から排泄されます。
薬剤によって大きく異なりますが、短いもので30分、長いものでは60~120時間かけて、
半減期まで到達するものがあります。
完全に消失するためには、T1/2の5倍はかかると覚えておきましょう。
ただし、患者の状態によっても異なりますので、一般的に5倍ということです。
薬の血中濃度は非常に重要で、多すぎると副作用が発現し、少なすぎると薬効を得られません。
このそれぞれの限界値の中に、血中濃度を保つようにしますが、その状態を測るためにモニタリングを行います。
モニタリングを対象とする薬は、安全域が狭いことが多く、投与量と投与速度の確認も重要です。
【対象薬】
抗けいれん薬、抗うつ薬、抗不整脈、アミノグリコシド系抗生物質、免疫抑制薬、気管支拡張薬
【モニタリングが必要な時】
①治療域の薬物血中濃度が狭い薬を使用
②体内動態に個人差が大きい薬を使用
③体内動態に非線形性(ある地点から濃度が急上昇する)が認められる薬を使用
④排泄臓器である肝機能・腎機能低下時
【引用・参考文献】
折井孝男監修:「説明力UP!臨床で役立つ薬の知識」、学習研究社、2007.3
浜田康次監修:「スラスラわかる薬のメカニズム」、医学芸術社、ナーシングカレッジ2006年10月臨時増刊号、第10巻第12号通巻148号
古川裕之編著:「ナースに必要な薬の基本 キー・ドラッグ」、学習研究社、2007.12

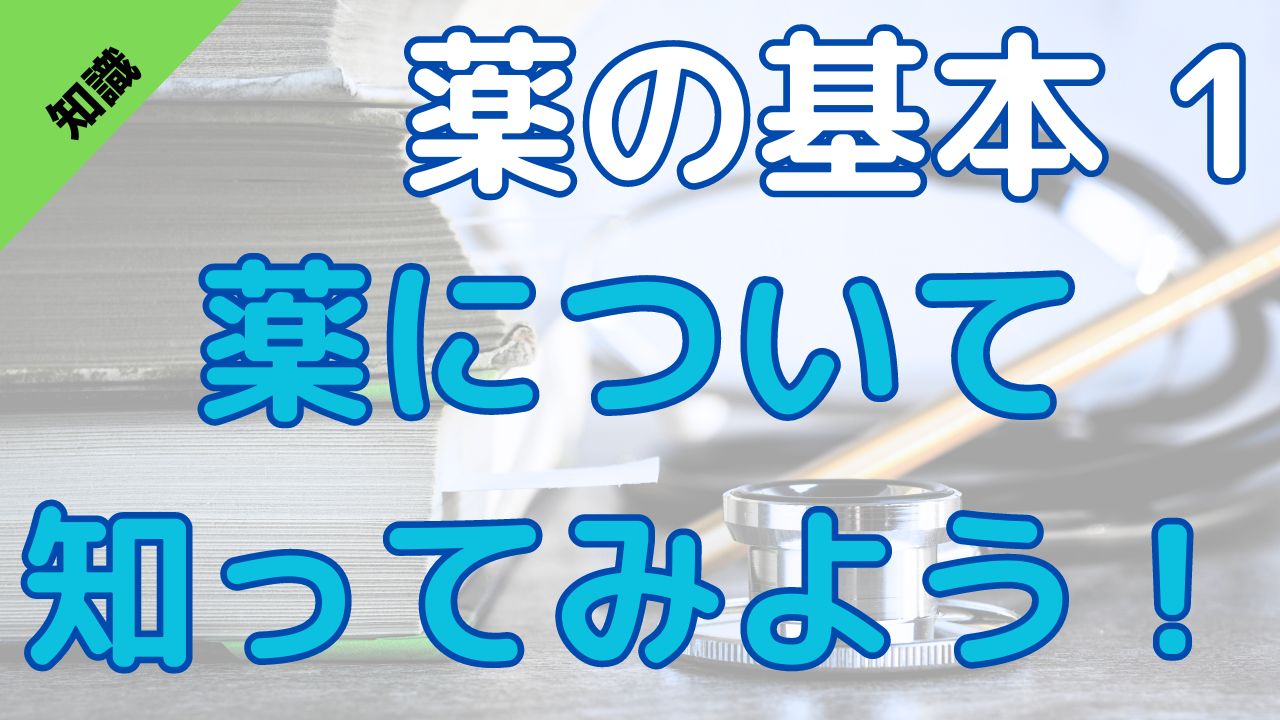


コメント