がん治療にも感染症の危険性はつきものです。
免疫低下、創部の状態などで、原因菌や感染源を調べる必要がでてきます。
感染症の診察では、どこの臓器に、どんな菌が感染しているかを判断して抗菌薬を選択します。
可能な限り、抗菌薬を投与する前に検査をして、原因菌を同定し、適切な抗菌薬を選択します。
どのような検査があるのか、その際の看護についてみていきます。
感染症を疑った場合、一般的に行う検査
発熱などがあり、感染症を疑う場合に、まず行われる検査には次の3つがあります。
①血液培養・各種培養検査
②画像検査
③尿検査
どれも簡便に行えるもので、ここから原因菌と感染源を同定します。
これでも分からない場合もあるのですが、その際には追加の検査を行い、正しい診断を行います。
それぞれ簡単な検査なのですが、看護師はどのような目的で行うのかを伝えなければなりません。
医師から説明を受けているのですが、心配事を聞ける心理状態にないことが多いです。
患者さんは、まず医師から検査が必要であることの説明を受けます。
自分の状態はどのようなものか、もし感染源が分かったら何をするのか、どうなるのかなど、
心配事が次々と浮かんでくるでしょう。
医師は説明をしたらすぐにその場を離れることが多いので、すぐに質問できない方がいます。
そんな時に話を聞くのは看護師です。
どのような現状で、今後起こりうる状態などを伝える必要が出てきますので、看護師は多くの知識を持ち、対応できる力が必要になるのです。
全ては患者さんの要望に応え、不安なく検査を受けることができる状態にすることなのです。
3つの検査をそれぞれみていきましょう。
血液培養検査(各種培養検査)
培養検査は、検体に菌が混入していないかを調べる検査です。
血液検査だけでなく、先に挙げた髄液検査や尿検査、喀痰検査も対象となります。
採取時には、極力雑菌が入らないようにする必要がありますので、注意する点を記載します。
①雑菌が入らないように注意して採取する
②決められた滅菌容器に採取する
③必要十分な量を採取する(規定量以上でも以下でも正確な検査ができない)
④検体を採取後は、速やかに検査室に提出する(遅くても2時間以内)
血液培養検査
血液培養には専用の2本のボトルが使用され、上記の注意点以外にも注意することがあります。
その点を説明していきましょう。
好気性菌:酸素があるところで増殖する菌(ブルーキャップ)
嫌気性菌:酸素がないところで増速する菌(オレンジキャップ)
これら両方を調べて、確実に原因微生物をみつけるために、2種類(2本)で1セットとなります。
2セット(計4本)採取するのは、感染症の原因微生物ではない菌を、誤って原因微生物と判断しないためです。
これは、本来の感染症の原因微生物ではない菌、例えば常在菌が混入され、これを治療対象と考えないために、本当に常在菌ではないのかを判断するために2セット行います。
採取はそれぞれ別々の部位から採血しなければなりません。
右手で採取したら、2セット目は左手という具合です。
この時に注意が必要なのは、どちらかの腕で静脈点滴を行っている場合です。
点滴をしている血管で採血をしてしまうと、点滴成分が混入してしまいます。
その場合、同側の別血管で採取する、もしくは下肢から採取する必要もあります。
どうしても採取しにくい場合は、医師に動脈穿刺を行ってもらう対処も考慮します。
また、採取した血液を血培ボトルに注入する際も決まりがあります。
採取したシリンジの中には空気も混入されます。
血培ボトルに注入する際、空気はシリンジの上に溜まりますので、
嫌気性ボトルから注入することで、ボトル内に空気が入る危険性を低くするため、
①嫌気性ボトル(オレンジキャップ)、②好気性ボトル(ブルーキャップ)の順に注入します。
髄液検査
髄膜刺激兆候やけいれんなどがあり、髄膜炎が疑われるときには、髄液検査をします。
髄膜刺激兆候とは、発熱、頭痛、嘔吐、頚部硬直がありますが、
意識障害、けいれん、麻痺がある場合もあります。
髄液検査は、骨髄に針を刺して髄液を採取します。
腰から針を刺しますので、検査に対しての患者さんの不安は大きくなります。
一昔前に比べて針が細くなりましたので、耐えられないほどの痛みを伴うものではないことを説明しましょう。
また検査後は、2時間ほどの安静が必要になります。
刺した場所から髄液が漏れると、低髄液圧になり一時的に頭痛が起こる場合があるからです。
一般的には自然に治まっていくことを説明し、安心して検査が受けられるように準備します。
髄液は血液と同じで無菌部位です。
通常は無菌的に採取された検体の培養検査で菌が認められた場合には原因菌と判断します。
しかし、抗菌薬投与後に髄液検査をした場合、原因菌が判明しない場合もあります。
また、無菌性髄膜炎といってウイルス性の髄膜炎もあります。
髄膜炎で多い原因菌を紹介します。
| 年齢 | 原因菌 |
|---|---|
| 新生児~3ヶ月 | 大腸菌、B群溶血性レンサ球菌、リステリア菌、ブドウ球菌 etc. |
| 乳幼児 | インフルエンザ菌、肺炎球菌 etc. |
| 学童 | インフルエンザ菌、肺炎球菌、髄膜炎菌 etc. |
| 成人 | 肺炎球菌、インフルエンザ菌 etc. |
| 高齢者(50歳以上) | 肺炎球菌、インフルエンザ菌、腸内細菌、黄色ブドウ球菌 etc. |
| 脳外科術後 | 好気性グラム陰性桿菌(緑膿菌を含む)、黄色ブドウ球菌、 コアグラーゼ陰性ブドウ球菌(特に表皮ブドウ球菌) etc. |
| CSFシャント | 好気性グラム陰性桿菌(緑膿菌を含む)、黄色ブドウ球菌、 コアグラーゼ陰性ブドウ球菌(特に表皮ブドウ球菌)、アクネ菌 etc. |
画像検査
X線、CT、MRIが一般的に行われる検査です。
その中で一番簡便に行えるのがX線で、疑いを向ける部位の全体像をみるのに適しています。
CT、MRIはX線で分かりにくく、詳細に調べる必要がある場合に選択される検査になります。
例えば、発熱があり胸部X線で肺炎と診断し、抗菌薬の投与を始めました。
しかし解熱せず、CT検査をしたら腹腔内膿瘍があることが判明し、排膿したら速やかに解熱したという例もあります。
画像検査の際に患者さんが心配されるのは、放射線被曝と閉所恐怖症がある場合です。
X線よりCTの方が放射線量は大きくなりますが、短期間に複数回の検査を受けたとしても、身体に影響が出るほどの線量を浴びることはないと説明する必要があります。
当然無駄な被曝リスクを与えないためにも、必要最低限の回数で行うことも伝えます。
閉所恐怖症の方は、検査室にその旨を伝えます。
アイマスクやヘッドホン、コール用のブザーを渡すなどして、不安を和らげます。
極力声をかけ、短時間で終わるように計らってもらえます。
尿検査
検尿コップに尿を採取して検査室に出すものです。
基本的には中間尿といって、おしっこの最初と最後の部分を捨てて採取します。
おしっこが出始めたら一旦止めて、コップ1/3程度を採取後コップは外します。
残っている尿も出し切って終了です。
自分でコップに採取できない場合は、オムツにラップなどのビニールを敷き、吸収されないようにします。
尿道の周囲にガーゼなどを当てがい、採取できたガーゼを絞って提出します。
上記の方法が不快なく採取できますが、コストや労力の問題から、
明け方に検尿コップを直接オムツ内にセットし、採取できた頃にコップを除去する方法が一般的です。
ですが上手くコップをセットしておかないと、オムツ内でこぼれてしまっていて吸収されてしまっていることも多く経験します。
どうしても清潔尿が必要な場合は、導尿が必要になります。
尿検査の必要性ですが、肺炎でも必要な検査になるのです。
理由は、原因が肺炎以外にないかどうか、原因菌でレジオネラ・肺炎球菌の尿中抗原を調べるためです。レジオネラや肺炎球菌は重症肺炎になる可能性があるので、早期に診断が必要です。
尿中抗原を調べることで、ある程度の診断ができるために行うのです。
発熱の原因が分からない時にも、尿検査で尿路感染症が判明し、胸部X線で肺炎が疑われる場合もあります。
CRPについて 炎症反応をみる
CRP(C-reactive protein:C反応性タンパク)といいます。
感染症になると、サイトカインという物質が出て、その影響でCRPが増加します。
通常は感染が成立してから6時間過ぎたぐらいから上昇し始めます。
感染症の中でも細菌感染症ではCRPが高めの値を示します。
CRP値は感染症の状態より少し遅れて反応します。
その理由の1つに、身体の中でのCRPの半減期が数時間あるということも関係しています。
したがって、CRPが完全に陰性化するまで必ずしも抗菌薬を投与する必要はなく、
CRPが陽性であっても臨床的に感染症の状態が改善していれば、
抗菌薬は終了しても問題ないことも多いです。
白血球数はCRP値よりも早く反応します。
感染症に罹患すると、通常は白血球数は増加しますが、
重症感染症や免疫学的異常がある場合は、白血球数が減少する場合があります。
白血球には分画があり、顆粒球、リンパ球、単球の3種類があり、
顆粒球は、好中球、好酸球、好塩基球に分類されます。
好中球には微生物を貪食する働きがあり、一般的に細菌感染では好中球が増加します。
ウイルス感染ではリンパ球が、寄生虫感染では好酸球が増加します。
例外として、乳児期には、生理的に好中球に比べてリンパ球が優位になっています。
抗がん剤などで好中球数が500/µL以下になり、発熱を認めた場合は、
FN(Febrile neutropenia:発熱性好中球減少)とよばれる状況になります。
プロカルシトニンは、重症細菌感染症において、CRP値より早く上昇します。
本来は甲状腺で作られて、代謝によりカルシトニンというホルモンに変化します。
カルシトニンは、カルシウム代謝に関わる大切なホルモンです。
重症な細菌感染症では、甲状腺以外のどこかでプロカルシトニンが作られ、
そのまま血液中に分泌されるため、この物質を測定しているのです。
【特徴】
①細菌感染症の重症例で上昇し、ウイルス感染症では上昇しない
②CRP値に比べて早く上昇するため、早期対応が可能になる
③CRP値に比べて早く低下するため、治療効果を反映する
④すべての医療機関で検査できるわけではない
⑤定性検査と定量検査があるが、定量検査はまだ十分に普及していない
【参考・引用文献】
三鴨廣繁監修:「ナースのための抗菌薬つぎの一歩」、南山堂、2011初版

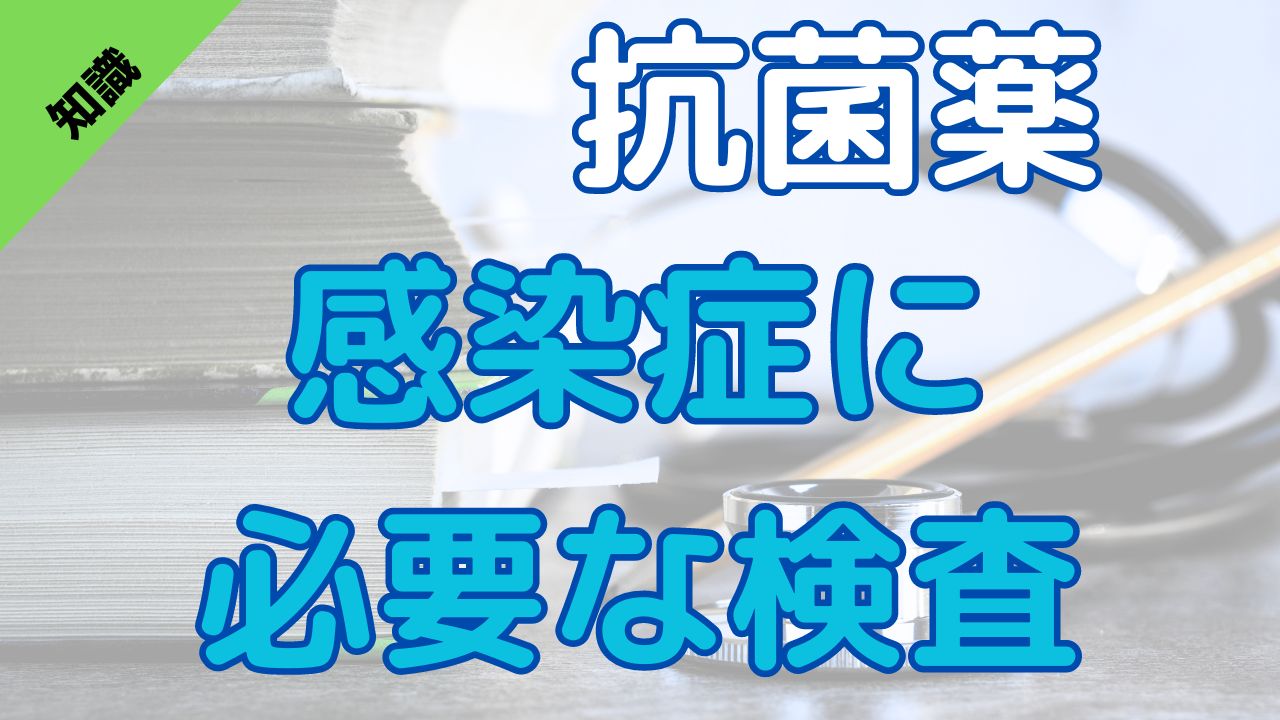


コメント