看護師もキャリアアップを!と、多くの場所で言われませんか?
管理職になるってこと?師長さんとかいつも遅くまで残って大変そう…
色んなスキルを身に付ける?あちこち病院探すのも大変だよな…
「キャリアアップ」と聞くと、何やら仕事が増えそうな印象です。
残念ながら仕事は増えます(笑)
しかし、その仕事がやりがいや給与につながるなら、頑張りたい!と思いませんか?
どうせ仕事をしないといけないなら、自分が楽しいと思える働き方をしたいですよね。
参考の一事例として、
なぜ認定看護師を目指したのか、自己のキャリアをどのように育んできたのか、
についてご紹介したいと思います。
なぜ認定看護師を目指したのか
実は看護師が取っておけば、差別化できるような資格は多く存在します。
看護師に実用的な資格 10選
3学会合同呼吸療法士
呼吸療法士は人工呼吸器だけではありません。
吸入療法、酸素療法、呼吸理学療法、NPPV(在宅酸素療法)などを習熟し、
呼吸療法を行う医療チームの構成要因を養成し、かつそのレベルの向上を図ることなどを目的とします。
| 受験資格 | 更新 | 更新要件 | 受講料 |
| 2年以上の実務経験 講習会などで12.5点以上 | 5年毎 | 認定講習・学会などで 50点以上取得 | 4千円程度 各講習費用 |
リンパ浮腫セラピスト
医師の指示に基づき、リンパ浮腫の患者さんにリンパドレナージ、弾性包帯や弾性着衣を用いた圧迫療法と運動療法、スキンケアや日常生活の指導などの複合的治療を行う施術者です。
病院によっては、所定の養成講座で補助金支援をしてくれるところもあります。
セラピスト講習を受けたのち、学会認定のリンパ浮腫療法士の受験資格を得られます。
| 受験資格 | 受講料 |
| 国家資格保有者 | 養成講座によるが、 40万~60万程度 |
消化器内視鏡技師
医師の監督指導のもと、内視鏡業務を行うものとして認定されます。
機器の管理、補助、整備、修理や介助などが行えると証明できる資格になります。
内視鏡室に従事する看護師さんに特化した資格でもあります。
| 受験資格 | 更新 | 更新要件 | 受講料 |
| 看護師資格をもち、 過去5年以内に専門医が従事する 内視鏡室で、2年以上の実務経験があること 学会などに所定の回数出席していること | 5年 | 研修会などの出席ポイントを30点 講習ポイント10点、計40点が必要 | 試験料1万 認定料1万 |
終末期ケア専門士
臨床ケアにおけるスペシャリストです。
患者・利用者さんの一番近くで「支える人」として、
エビデンスに基づいたケアの実践を行えることを目指す資格です。
| 受験資格 | 更新 | 更新要件 | 受験料 |
| 臨床経験2年以上 | 5年 | セミナー・講習会の受講 ステップアップもあり | 1.6万円 登録料1.1万円 |
認知症ケア専門士
認知症ケアに対する優れた学識と高度の技能、および倫理観を備えた専門技術士。
認知症ケア技術の向上、保健・福祉に貢献することを目的としています。
| 受験資格 | 更新 | 更新要件 | 受験料 |
| 3年以上の認知症ケア実務経験 | 5年 | セミナー・講習会の受講 ステップアップもあり | 2.6万円(登録料含む) |
糖尿病療養指導士
糖尿病の自己管理を患者に指導する医療スタッフです。
高度でかつ幅広い専門知識をもち、患者の糖尿病セルフケアを支援します。
合格するより、更新し続けることの方が大変なようです。
| 受験資格 | 更新 | 更新要件 | 受験料 |
| 過去10年以内に2年以上継続 通算1000時間以上療養指導を行った | 5年 | レポート10例 学会参加などで20P 関連学会などで20P | 講習3.3万円 受験料2.2万円 |
ACLSプロバイダー/PALSプロバイダー
成人心停止に対する心原性二次救命処置トレーニングをした証明です。
PALSは小児に対する二次救命処置です。
プロバイダーはコース終了証明、インストラクターは指導技術の証明です。
エビデンスの更新や、救命技術の維持向上のため、更新には再受講が必要です。
| 受験資格 | 更新 | 更新要件 | 受験料 |
| 医療従事者 または医療系学生 | 2年 | コースの再受講 | 約4万円 |
心不全療養指導士
心不全患者へ質の高い療養指導を通し、病院から在宅、地域医療まで
幅広く心不全患者をサポートすることを目指します。
循環器専門ナースという民間資格もありますが、受講費用が高いため、ハードルは上がります。
| 受験資格 | 更新 | 更新要件 | 受講料 |
| 日本循環器学会会員 心不全療養指導に従事 eラーニング講習を修了 | 5年 | 日本循環器学会学術集会に参加 50単位取得 症例報告5例 | 1.5万円 |
LTFU(造血幹細胞移植後長期フォローアップ外来)
造血幹細胞移植後の患者さんに対して、長期的にフォローアップをしていくための研修です。
慢性移植片対宿主病(GVHD)や感染症、骨疾患、内分泌代謝疾患などの晩期合併症の早期発見、
日常生活全般のサポートを行う外来です。
この研修を受けることで、外来で患者さんを看ていく資格を得られます。
| 受講資格 | 継続要件 | 受講料 |
| 5年以上の実務経験 かつ造血細胞移植に2年以上従事 血液・造血器腫瘍疾患看護に関わる 看護師のクリニカルラダーⅢ以上 | 日本造血・免疫細胞療法学会員 フォローアップ研修の受講 | 1.8万円 |
栄養サポートチーム専門療法士
静脈栄養・経腸栄養を用いた臨床栄養学に関する優れた知識と技能を提供します。
栄養管理が必要な患者さんを対象に、チームで検討・提案を行い、
個々の患者さんに合った栄養摂取を支援します。
| 受講資格 | 更新 | 更新要件 | 受講料 |
| 3年以上の実務経験 かつ栄養サポート業務に従事 | 5年 | 日本栄養治療学会会員 30単位の取得 | 1万円 認定料2万円 |
このように民間資格を含めると、看護師から取得できる資格は多数あります。
その中で臨床で活躍できると思われる資格を厳選しました。
モチベーションの向上に役立ててください。
専門看護師と認定看護師
看護師を継続し同一施設に勤務していると、
管理者を目指すのか、スペシャリストを目指すのかの方向を検討する時期があります。
管理者でも管理者講習を受けていき、ステップアップを図るのですが、
スペシャリストになりたい方のために、専門看護師と認定看護師を深堀していきます。
専門看護師(Certified Nurse Specialist)
患者・家族に起きている問題を総合的に捉えて判断する力と広い視野を持って、専門看護分野の専門性を発揮しながら専門看護師の6つの役割「実践・相談・調整・倫理調整・教育・研究」を果たし、施設全体や地域の看護の質の向上に努めます。
下記に具体的な活動内容を紹介します。
- 複雑で対応が困難な課題を抱える患者・家族の、病気とその背後にある不安や葛藤等の様々な要因を総合的に捉え、どのような看護が必要か判断して実践します。
- 患者・家族によりよい看護を行うにはどのような関わりが必要か等、看護師や他の医療職の相談に乗り、専門知識を活かしたアドバイスを行って問題の解決を図ります。
- 療養の場が病院から自宅へ移行しても必要な医療を円滑に受けられるよう、医師や看護師、地域の訪問看護ステーションやケアマネジャー等、様々な職種・施設に働きかけて調整し、連携を推進します。
- 治療方針の決定など倫理的問題が生じやすい場面に関わり、患者・家族の思いを尊重して治療や療養を行えるよう、他の看護師や医師等、関係する人々に働きかけます。
- 専門知識や技術に基づき看護師に教育を行い、施設全体や地域の看護の質の向上に努めます。
- 日々の看護における課題を研究対象としてとらえ探求します。研究成果を実践に還元することで、看護の質の向上に貢献します。
専門看護師の6つの役割
- 個人、家族及び集団に対して卓越した看護を実践する(実践)
- 看護者を含むケア提供者に対しコンサルテーションを行う(相談)
- 必要なケアが円滑に行われるために、保健医療福祉に携わる人々の間のコーディネーションを行う(調整)
- 個人、家族及び集団の権利を守るために、倫理的な問題や葛藤の解決を図る(倫理調整)
- 看護者に対しケアを向上させるため教育的役割を果たす(教育)
- 専門知識及び技術の向上並びに開発を図るために実践の場における研究活動を行う(研究)
専門看護師の分野(14分野)2022.12時点
| がん看護 | がん患者の身体的・精神的な苦痛を理解し、患者やその家族に対してQOL(生活の質)の視点に立った水準の高い看護を提供する。 |
| 精神看護 | 精神疾患患者に対して水準の高い看護を提供する。また、一般病院でも心のケアを行う「リエゾン精神看護」の役割を提供する。 |
| 地域看護 | 産業保健、学校保健、保健行政、在宅ケアのいずれtかの領域において水準の高い看護を提供し、地域の保健医療福祉の発展に貢献する。 |
| 老人看護 | 高齢者が入院・入所・利用する施設において、認知症や嚥下障害などをはじめとする複雑な健康問題を持つ高齢者のQOLを向上させるために水準の高い看護を提供する。 |
| 小児看護 | 子供たちが健やかに成長・発達していけるように療養生活を支援し、他の医療スタッフと連携して水準の高い看護を提供する。 |
| 母性看護 | 周産期の母子および家族への支援、女性のライフサイクル全般にわたる健康への援助等、水準の高い看護ケアを提供する。 |
| 慢性疾患看護 | 生活習慣病の予防や、慢性的な心身の不調とともに生きる人々に対する慢性疾患の管理、健康増進、療養支援などに関する水準の高い看護を行う。 |
| 急性・重症患者看護 | 緊急度や重症度の高い患者に対して集中的な看護を提供し、患者本人とその家族の支援、医療スタッフ間の調整などを行い、最善の医療が提供されるよう支援する。 |
| 感染症看護 | 施設や地域における個人や集団の感染予防と発生時の適切な対策に従事するとともに感染症の患者に対して水準の高い看護を提供する。 |
| 家族支援 | 患者の回復を促進するために家族を支援する。患者を含む家族本来のセルフケア機能を高め、主体的に問題解決できるよう身体的、精神的社会的に支援し、水準の高い看護を提供する。 |
| 在宅看護 | 在宅で療養する対象者及びその家族が、個々の生活の場で日常生活を送りながら在宅療養を続けることを支援する。また、在宅看護における新たなケアシステムの構築や既存のケアサービスの連携促進を図り、水準の高い看護を提供する。 |
| 遺伝看護 | 対象者の遺伝的課題を見極め、診断・予防・治療に伴う意思決定支援とQOL向上を目指した生涯にわたる療養生活支援を行い、世代を超えて必要な医療・ケアを受けることができる体制の構築とゲノム医療の発展に貢献する。 |
| 災害看護 | 災害の特性をふまえ、限られた人的・物的資源の中でメンタルヘルスを含む適切な看護を提供する。平時から他職種や行政等と連携・協働し、減災・防災体制の構築と災害看護の発展に貢献する。 |
| 放射線看護 | 放射線がもたらす身体、心理社会的影響の特性をふまえ、放射線事故・災害における平時からの体制構築と健康課題を有する対象へ長期的な看護を提供する。また、放射線診療を受ける対象者とその家族へ水準の高い看護を提供するとともに、職業被ばく低減の方策など、施設における体制を構築する。 |
専門看護師になるまで
- 日本国の看護師免許を有すること
- 看護系大学院修士課程修了者で、日本看護系大学協議会が定める専門看護師教育課程基準の所定の単位(総計26単位または38単位)を取得していること
- 実務研修が通算5年以上あり、うち3年間以上は専門看護分野の実務研修であること
- 「資格認定制度 審査・申請システム」よりWEB申請を行い、20900円を振り込む
- 書類審査と筆記試験(論述式)にて合格する
- 認定申請で認定料51700円振り込む
認定看護師(Certified Nurse)
患者・家族によりよい看護を提供できるよう、認定看護分野ごとの専門性を発揮しながら認定看護師の3つの役割「実践・指導・相談」を果たして、看護の質の向上に努めています。
下記に具体的な活動を紹介します。
- 専門的な治療や看護が必要な患者・家族に対して最適な看護は何か、認定看護分野の専門知識に基づき判断し、実践します。
- 他の看護師に対し、自らが手本となり専門知識や看護技術などを指導し水準の高い看護を行えるように働きかけたり、看護の現場で直面する問題や疑問の相談に乗り、改善策を導き出せるよう認定看護分野の専門知識に基づき支援します。
認定看護師の3つの役割
- 個人、家族及び集団に対して、高い臨床推論力と病態判断力に基づき、熟練した看護技術及び知識を用いて水準の高い看護を実践する(実践)
- 看護実践を通して看護職に対し指導を行う(指導)
- 看護職等に対しコンサルテーションを行う(相談)
認定看護師の分野(19分野)2024.5現在
| 感染管理 | ・医療関連感染の予防・管理システムの構築 ・医療管理感染の予防・管理に関する科学的根拠の評価とケア改善 ・医療関連感染サーベイランスの立案・実施・評価 ・身体的所見から病態を判断し、感染兆候があるものに対する薬剤の臨時投与ができる知識・技術 |
| がん放射線療法看護 | ・放射線治療を受ける対象の身体的・心理的社会的アセスメント ・再現性確保のための支援 ・急性期および晩期有害事象に対する症状マネジメントとセルフケア支援 ・医療被曝を最小限にするための放射線防護策、安全管理技術 |
| がん薬物療法看護(がん化学療法看護より名称変更) | ・がん薬物療法の適正な投与管理とリスクマネジメント、曝露対策 ・がん薬物療法に伴う症状緩和 ・自宅での治療管理や有害事象に対応するための個別的な患者教育 ・患者・家族の意思決定支援と療養生活支援 |
| 緩和ケア(がん性疼痛看護と統合) | ・痛みやその他の身体的・心理社会的・スピリチュアルな問題のアセスメント ・全人的問題を緩和し、QOLを向上するための症状マネジメント ・家族の喪失や悲嘆への対応 |
| クリティカルケア(集中ケアと救急看護が統合) | ・急性かつ重篤な患者の重篤化回避と合併症予防に向けた全身管理 ・安全・安楽に配慮した早期回復支援 ・身体所見から病態を判断し、侵襲的陽圧換気・非侵襲的陽圧換気の設定の変更、人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整、人工呼吸器からの離脱ができる知識・技術 ・身体所見から病態を判断し、持続点滴中の薬剤(カテコラミン、ナトリウム、カリウム又はクロール、降圧剤、糖質輸液又は電解質輸液、利尿剤)の投与量の調整を安全・確実にできる知識・技術 |
| 呼吸器疾患看護(慢性を削除し名称変更) | ・呼吸症状のモニタリングと評価、重症化予防 ・療養生活行動支援及び地域へつなぐための生活調整 ・症状緩和のためのマネジメント ・身体所見を病態判断し、侵襲的陽圧換気・非侵襲的陽圧換気の設定の変更、人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整、人工呼吸器からの離脱ができる知識・技術 |
| 在宅ケア(訪問看護より名称変更) | ・生活の場におけるQOLの維持・向上とセルフケア支援 ・対象を取り巻くケアシステムの課題に対する解決策の提案 ・生活に焦点をあてた在宅療養移行支援及び他職種との調整・協働 ・意思決定支援とQOLを高めるエンド・オブ・ライフケア ・身体所見から病態を判断し、気管カニューレの交換が安全にできる知識・技術 ・身体所見から病態を判断し、胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換が安全にできる知識・技術 ・身体所見から病態を判断し、褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去が安全にできる知識・技術 |
| 手術看護 | ・手術侵襲およびそれによって引き起こされる苦痛を最小限に留めるためのケア ・手術中の患者の急変および緊急事態への迅速な対応 ・患者および家族の権利擁護と意思決定支援 ・身体所見から病態を判断し、経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整ができる知識・技術 ・身体所見から病態を判断し、侵襲的陽圧換気の設定の変更、人工呼吸器からの離脱ができる知識・技術 ・身体所見から病態を判断し、硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与および投与量の調整ができる知識・技術 ・身体所見から病態を判断し、持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整ができる知識・技術 |
| 小児プライマリケア(小児救急看護より名称変更) | ・重篤な状態にある児もしくは医療的ケア児に対する重症化予防 ・外来及び地域等のプライマリケアの場におけるトリアージ ・家族の家庭看護力・育児力向上に向けたホームケア指導 ・不適切な養育または虐待の予防、早期発見と、子どもの事故防止 ・身体所見及び気管カニューレの状態を病態判断し、気管カニューレの交換が行える知識・技術 |
| 新生児集中ケア | ・ハイリスク新生児の急性期の全身管理 ・障害なき成育のための個別ケア ・ハイリスク新生児と親への家族形成支援 ・不適切な養育または虐待のハイリスク状態の予測と予防 ・身体所見及び気管カニューレの状態を病態判断し、気管カニューレの交換が行える知識・技術 |
| 心不全看護(慢性を削除し名称変更) | ・心不全症状のモニタリングと評価、重症化予防 ・療養生活行動支援及び地域へつなぐための生活調整 ・症状緩和のためのマネジメント ・身体所見から病態を判断し、持続点滴中の薬剤(カテコラミン、ナトリウム、カリウム又はクロール、降圧剤、糖質輸液又は電解質輸液、利尿剤)の投与量の調整を安全・確実にできる知識・技術 |
| 腎不全看護(透析看護より名称変更) | ・疾病の進展予防、合併症の早期発見と症状マネジメント、セルフケア支援 ・腎代替療法の選択・変更・中止にかかわる自己決定に向けた支援 ・透析療法における至適透析の実現に向けた支援 ・急性血液浄化療法における血液透析器又は血液透析濾過器の操作及び管理を安全・確実にできる知識・技術 |
| 生殖看護(不妊症看護より名称変更) | ・性と生殖の機能、その生涯とリスク因子に関する知識に基づく妊孕性の評価 ・性と生殖の健康課題に対する、多様な選択における意思決定支援 ・患者・家族の検査期・治療期・終結期の安全・安楽・納得を守る看護実践とケア調整 ・妊孕性温存及び受胎調節に関する指導 |
| 摂食嚥下障害看護(摂食・嚥下より名称変更) | ・摂食嚥下機能とその障害の評価 ・摂食嚥下機能の評価結果に基づく適切な援助・訓練方法の選択 ・誤嚥性肺炎、窒息、栄養低下、脱水の憎悪防止に向けたリスク管理 |
| 糖尿病看護 | ・血糖パターンマネジメント ・病気に応じた透析予防、療養生活支援 ・予防的フットケア ・身体所見から病態を判断し、インスリンの投与量の調整ができる知識・技術 |
| 乳がん看護 | ・術後合併症予防及び緩和のための周手術期ケアと意思決定支援 ・ライフサイクルの課題をふまえた、治療に伴う女性性と家族支援 ・乳房自己検診、リンパ浮腫等の乳がん治療関連合併症の予防・管理 ・身体所見から病態を判断し、創部ドレーンの抜去ができる知識・技術 |
| 認知症看護 | ・認知症の症状マネジメント及び生活・療養環境の調整 ・認知症の病期に応じたコミュニケーション手段の提案と意思決定支援 ・家族への心理的・社会的支援 ・身体所見から病態を判断し、抗けいれん剤、抗精神病薬及び抗不安薬の臨時の投与ができる知識技術 |
| 脳卒中看護(脳卒中リハビリテーション看護より名称変更) | ・重篤化回避のためのモニタリングとケア ・早期離床と生活の再構築に向けた支援 ・在宅での生活を視野に入れたケアマネジメントと意思決定支援 ・身体所見から病態を判断し、抗けいれん剤、抗精神病薬及び抗不安薬の臨時の投与ができる知識・技術 |
| 皮膚・排泄ケア | ・褥瘡のトータルマネジメント ・管理困難なストーマや皮膚障害を伴うストーマケア ・専門的な排泄管理とスキンケア ・脆弱皮膚を有する個人・リスクがある個人の専門的なスキンケア ・地域包括ケアシステムを視野に入れた同行訪問実施とマネジメント ・身体所見から病態を判断し、褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去及び創傷に対する陰圧閉鎖療法ができる知識・技術 |
認定看護師になるまで
- 日本国の看護師免許を有すること
- 看護師免許取得後、実務研修が通算5年以上あること(うち3年以上は認定看護分野の実務研修)
- 認定看護師教育機関での研修を受ける
※2026年度より特定行為を組み込まない教育機関は廃止され、半年の教育期間から1年間の教育期間へ延長される
- 「資格認定制度 審査・申請システム」よりWEB申請を行い、審査料51700円を振り込む
- 筆記試験(マークシート方式・四肢択一)に合格する
- 認定申請で認定料51700円を振り込む
まずは好きな分野を探しましょう
スペシャリストを目指す、またはそうでなくても、自分が好きな分野を探すことは重要です。
様々な資格を紹介していますが、民間資格でも十分にモチベーションアップを狙えます。
実際、専門・認定看護師を取得すると、その分野での責任を負っていくことになります。
それを責務と思って遂行できるか、もう少し違う形で強みとして持っておきたいかで、
道は随分と変わるでしょう。
私が認定看護師を目指したきっかけ
看護師になって初めて家族以外の死に立ち会いました。
その方はがんによって徐々に弱っていく自分を、情けなく感じると話していました。
当時の私にはその方の苦しみに対して、話を聞いて、顔を見せる事しかできませんでした。
そして本当に動けなくなってきた時には、何もできない私ではなく、
先輩達が担当につくようになり、お顔を見にいくのも躊躇うようになりました。
より状態が悪くなってきた時、何日かぶりに顔を出すとその方は、
「来てくれたんや。もう動けなくなってしもたわ」と笑いながら話していました。
その時に何も声をかけれず、自分の不甲斐なさに落胆していたのです。
先輩が来てその人と話すのを見て、「自分も同じように関われるようになりたい」
と思うようになりました。
同時にこのような関わりの時間があるのが、がんという病気なんだと学び、
その方の苦痛を少しでも和らげられる何かを、
提供できるスキルを、身に付けたいと思ったのが最初でした。
がんの分野でも化学療法分野を選んだ理由
がん看護に興味を持った最初の頃は、緩和ケアがしたいと思っていました。
ですがこの頃は経験も浅く、患者さんの苦痛に上手く対応できずに悩む日々でした。
先輩の看護をみても、自分にはこうはできないと思ってしまい、
当時よく分からなかったがん治療を学んでみようと思うようになりました。
自分で参考書を開いてみても、現在のようにたくさんの書籍がありませんでした。
何から手をつけていいのか分からず、点と点を結ぶことができませんでした。
そこで本格的に学んでみたい、他の人にも知識を共有したいと思うようになり、
認定看護師の入試問題に取り組む事にしたのがきっかけです。
認定看護師を取得して良かったこと
- 好きな分野に強みを持てる
- 患者さんの信頼度が向上する
- 患者さんとの親密度を容易に向上させることができる
- 自分のやり方次第で、その分野のシステムやケア体制を変更していける
認定看護師を取得してのデメリット
- 当該分野での責任が重くなる
- 委員会や提出物、他職種調整など単純に仕事量が増える
- 資格手当は多くなく、人によっては夜勤が減少し、その分の補填ができないことがある
メリットがあればデメリットがあるのは、全ての共通事項です。
どれだけのベネフィットを得られるかは、その人それぞれの価値観です。
つたない経験談ですが、ご参考にしていただければ幸いです。
今回は以上です。

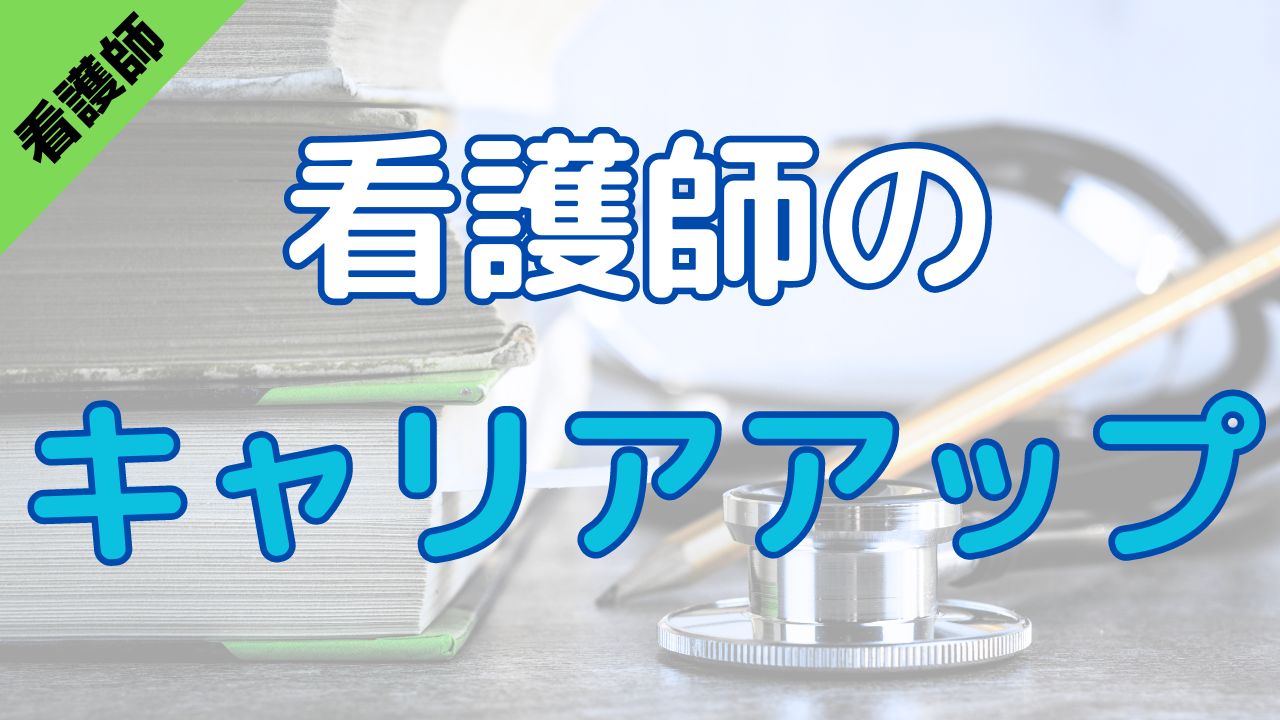
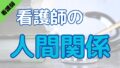

コメント